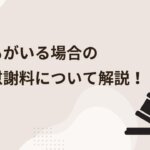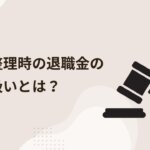盗撮が発覚したときに考えるべき話し合いのポイント
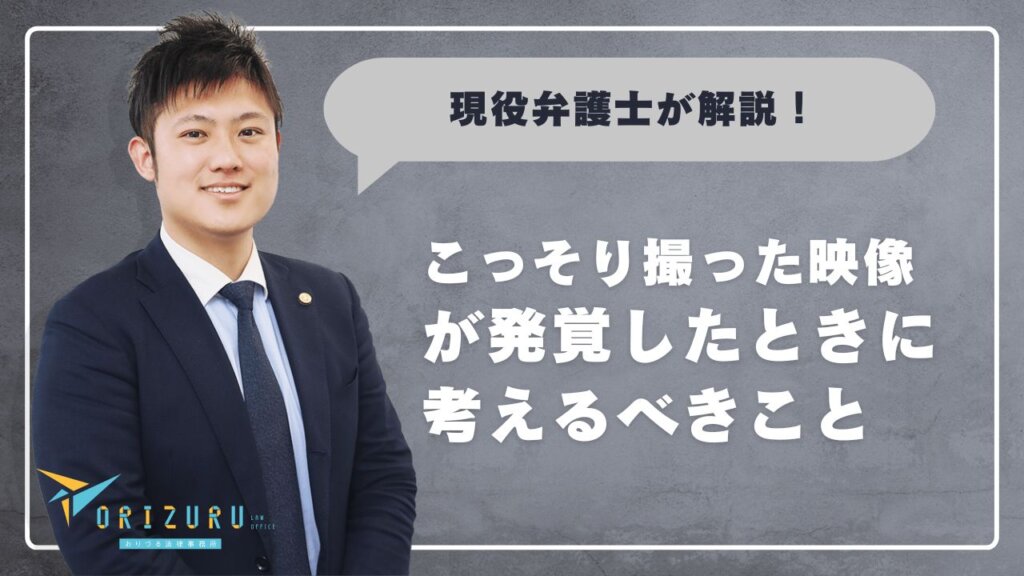
公共の場所や店舗の中、あるいはプライベート空間で、こっそりと撮影や録音を行ってしまい、それが発覚して大きなトラブルに発展する――昨今、この種の問題はニュースでも頻繁に取り上げられています。いわゆる「盗撮」を行った側は、その行為が発覚した瞬間、社会的にも大きなリスクを背負うことになるでしょう。
本記事では、発覚した場合に「何をどのようにすればトラブルを最小限に抑えられるのか」を、撮影を行ってしまった当事者の立場(以下、「加害者側」と表現)から解説します。具体的には、どのような法的リスクがあるのか、相手との話し合いで解決する場合のメリット・デメリット、実際の手続きや注意点などを網羅的にまとめました。
「違法だと知りつつも、好奇心や出来心で撮ってしまった」「酔った勢い、または軽い気持ちでやってしまった」など、そのきっかけはさまざまでしょう。とはいえ、ひとたび問題が明るみに出ると、相手に与えた精神的苦痛やプライバシーの侵害は重大なものとみなされ、厳しく追及される可能性があります。自分はどう責任を負うべきか、取り返しのつかない事態をどう収束させるか――今、まさに悩んでいる方にとって、本記事が一助となれば幸いです。
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
なぜ隠し撮りは問題化しやすいのか
プライバシー侵害が深刻
秘密裏に撮影された映像は、被写体のプライバシーを大きく脅かします。「自分の知らないところで、勝手に撮影されていた」という事実は、それだけで相手に強い不快感や不安を与えるものです。撮られた側がそのデータの拡散を恐れるのは当然でしょう。
撮影機器の小型化・高性能化
スマートフォンや小型カメラの普及で、手軽に高品質な画像や動画を撮れる時代になりました。以前よりも発覚リスクが高まりつつ、実行行為自体も簡単になってしまったため、その分トラブルも増えています。一方、店舗の防犯カメラやセキュリティ対策も進んでおり、少しでも怪しい行動があれば監視映像などを根拠にすぐに問題化するケースが増えています。
社会的非難が強い
隠し撮りに対する社会の目は厳しく、たとえ軽い気持ちでやったとしても重大な犯罪行為とみなされることが少なくありません。個人情報の取り扱いが重視される現代においては、どのような目的であれ、相手の了承を得ない撮影は強い非難の対象となります。
加害者側が直面する法律的リスク
刑事罰の可能性
無断撮影には、各種の県条例違反や法令違反が該当する可能性があります。具体的には、都道府県の迷惑行為防止条例や軽犯罪法、場合によっては性的な意図が絡むとわいせつ関連の罪にも問われることがあります。犯罪として立件されれば、逮捕や罰金、実刑判決などのリスクがあるでしょう。
民事上の賠償責任
撮影行為によって被害者のプライバシー権や人格権を侵害したとみなされれば、加害者には損害賠償責任が発生し得ます。精神的苦痛に対する対価として、慰謝料を請求される例も多々あり、相手が弁護士を立ててくると高額になる傾向が強まります。
社会的信用の喪失
刑事事件化や裁判沙汰になれば、会社や周囲に事実が広まる可能性が高まります。隠し撮りが原因で職場を失ったり、家族に多大な迷惑をかけたりする深刻な事態にもつながりやすいため、早期に問題を収束させたいと考える加害者は多いでしょう。
お店や被害者との話し合いによる解決の必要性
外部への拡散・刑事事件化を防ぐ
お店や撮影された当事者との話し合いを通じて何らかの合意を得られれば、警察への被害届提出や周囲への情報拡散を留保してもらえる可能性があります。表沙汰になる前に当事者間で落としどころを見つけることができれば、社会的ダメージを比較的抑えられるでしょう。
迅速な収束が期待できる
訴訟や警察の捜査が入ると、手続きにかなりの時間と費用がかかります。それに比べて話し合いによる解決であれば、比較的早い段階で決着をつけられる可能性が高いです。
双方が納得できる条件設定が可能
裁判所を通さない解決方法は、柔軟な合意形成が可能です。たとえば「すべてのデータを消去し、しかるべき金額を支払う」「二度と行為を繰り返さないと誓約する」といった条件を取り決めることで、被害者側も多少は安心感を得られるかもしれません。
話し合いを検討するうえで押さえておきたい基本姿勢
嘘をついてごまかさない
相手がお店や警察に相談していれば、証拠映像や目撃証言を持っている可能性が非常に高いです。悪あがきで否定し続けても、後から事実が明るみに出たときに状況がさらに悪化します。
早期の謝罪で誠意を示す
秘密撮影をしてしまった事実があるなら、被害者や関係者に対して早めに誠意を示すことが、問題収束への近道です。加害者側が謝罪の気持ちを示すだけで、相手の怒りが多少なりとも和らぎ、話し合いに応じてもらいやすくなります。
感情的な応酬を避ける
被害者側は精神的ダメージを受け、怒りや不安を抱いています。そこで加害者まで声を荒らげたり、相手を脅すような態度を取ったりすれば、交渉は一瞬で頓挫してしまうでしょう。あくまで冷静に、相手の主張に耳を傾ける姿勢が大切です。
実際の交渉ステップと注意点
事実関係の把握
- 撮影時間や場所、目的
- どの程度の映像を保存しているか
- 第三者への送信やインターネット上へのアップロードの有無
相手に求められる情報は正直に開示し、自分自身もどのような証拠を相手が握っているかを確認してください。曖昧な対応や矛盾があると、相手の不信感を高めるだけです。
謝罪と今後の対応策
相手が最も気にしているのは、「撮影された映像がどこかに拡散されるかもしれない」という不安です。データを完全に削除すること、今後一切このような行為をしないことなど、具体的な対応策を言葉や書面で示すと安心感を持ってもらいやすくなります。
相手の要求内容の確認
- 金銭的な補償(慰謝料、手数料など)
- 再発防止を約束させる文書(誓約書)の提出
- 警察への被害届提出の取り下げ・保留
相手が希望する内容を明確にし、それに対してどの範囲で応じられるか検討していきましょう。もし相手が法外な条件を提示してきていると感じたら、その根拠を確認する必要があります。
合意書の作成
話し合いがまとまったら、口頭だけでなく合意内容を文書に残します。主な記載事項は以下のとおりです。
- 当事者の氏名・住所など
- 撮影行為の概要と責任の所在
- 金銭補償がある場合の具体的金額や支払い期日
- データの完全削除、再発防止策の明文化
- 今後追加で請求しない旨の条項(ただし重大な違反があれば別途)
- 作成日と双方の署名捺印
必要に応じた専門家(弁護士)への相談
相手から極端に高額な補償を求められた場合
「数百万円を支払え」「とんでもない金額で和解しろ」というような要求があった場合、法外な請求かどうかを判断するためにも、専門家のアドバイスを仰ぐのがおすすめです。
脅迫的な言動がある場合
「職場や家族に全部バラすぞ」「ネットに流すからな」などと脅してくる場合、脅迫や恐喝の可能性があります。下手に一人で対応すると危険な場合もあるため、弁護士や警察に相談することで身を守りつつ、適切に交渉を進めやすくなります。
自分自身が精神的に追い詰められている場合
秘密撮影行為が発覚したショックと、その後の対立でメンタルが限界になってしまう方もいます。そんなときほど冷静な判断が難しくなるので、早期に弁護士へ相談してみてください。客観的な視点でアドバイスをもらうことで、焦って不利な条件を飲んでしまうリスクを軽減できます。
金銭的負担や条件はどう決まる?
被害内容・心理的ダメージの大きさ
誰が、どのような場面で撮影され、どれほどの精神的苦痛を受けているかによって金額の相場は変動します。更衣室やトイレ内など、特にプライバシー度の高い場所での撮影は、重い責任を問われることが多いでしょう。
社会的地位や職業への影響
被害者が芸能関係者や公的立場の人物である場合、データが拡散されることで甚大なイメージ損害が発生する可能性があります。その場合、通常より高額な補償を求められても不思議ではありません。
加害者側の対応姿勢
早期に謝罪し、誠実に話し合いに応じれば、金銭負担を抑えられる場合があります。一方、言い逃れや誤魔化しを続けた結果、相手の怒りが膨れ上がり、高額請求につながることも珍しくありません。
弁護士費用など付随コスト
相手が弁護士を立てている場合、加害者側が弁護士費用の一部を負担するよう求められることもあります。交渉の中で話が出たら、請求内容が妥当かどうかも検討すべきでしょう。
再発防止のためにできること
デバイスの管理とルールづくり
撮影機器やスマートフォンを持ち歩く際、安易に撮影しないルールを自分に課すことが大切です。いざというときに衝動的に撮影してしまわないよう、意識を変えるところから始めましょう。
カウンセリングや専門機関のサポート
もし「やめたくてもやめられない」という深刻な依存的状況があるなら、専門家によるカウンセリング(再犯防止プログラム)を検討する価値があります。根本的な問題を改善しなければ、トラブルを繰り返す可能性が高まります。
周囲への信頼回復
家族や職場の人に迷惑をかけてしまった場合、正直に事情を話して反省の意を示すことも重要です。早期解決だけでなく、その後の社会生活での信頼回復にも努める必要があります。
よくある疑問Q&A
Q1:秘密(無断)撮影がバレた場合、すぐに警察に逮捕されますか?
A1:状況によります。被害者やお店側が警察に被害を申告した場合、証拠が明確であれば逮捕される可能性は否定できません。ただし、話し合いで問題を解決して被害届を出さない形にもっていければ、刑事事件化を回避できることもあります。
Q2:話し合いがまとまった後、再度追加請求されることはありますか?
A2:正式な合意書(示談書)を作成し、「今後は追加の請求を行わない」旨を明記していれば、原則として追加請求される可能性は低くなります。しかし、書面の内容が曖昧だとトラブル再燃のリスクもあるため、注意が必要です。
Q3:撮影したデータを本当に消去していると証明するにはどうすればいいですか?
A3:厳密に言えば、データを完全に証明するのは容易ではありません。弁護士立会いのもとで消去手順を踏む、ストレージを初期化するなどの方法を提示して、誠意を示すことが重要です。第三者の専門業者に依頼して検証してもらう場合もあります。
Q4:相手から高額な金額を要求されました。支払わないと必ず裁判になりますか?
A4:一概に「必ず裁判になる」とは限りませんが、相手が不満を持ったままだと裁判や刑事告訴の道を選ぶ可能性は高まります。話し合いの中で妥協点を探るか、専門家のサポートを受けて適正金額を模索するのが得策でしょう。
まとめ
秘密撮影が発覚した場合、加害者側は大きなリスクを抱えます。刑事事件として処分を受けるだけでなく、多額の賠償責任を負ったり、社会的信用を失ったりする事態になりかねません。しかし、正しい手順を踏んで話し合いを行い、真摯な態度を示すことで、問題を比較的穏便に解決できる可能性もあります。
- 事実を隠そうとせず、早期の謝罪で相手の不安を和らげる
- 相手の要求を正確に把握し、対応可能な範囲を慎重に検討する
- 合意内容は必ず書面にし、再燃を防ぐための条項を盛り込む
- 必要に応じて弁護士などの専門家に相談する
- 二度と繰り返さないための具体的な対策を講じる
たとえ軽い気持ちであっても、相手のプライバシーを踏みにじる行為には重い責任が伴います。示される金額や条件をめぐってトラブルがさらに拡大しないよう、冷静かつ誠実な話し合いに取り組みましょう。今後同じ過ちを繰り返さないために、自身の行動を改めるとともに、必要があれば専門機関の助けを借りることも視野に入れてください。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。