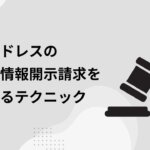熟年離婚での財産分与|分け方のルールと注意点を現役弁護士が解説
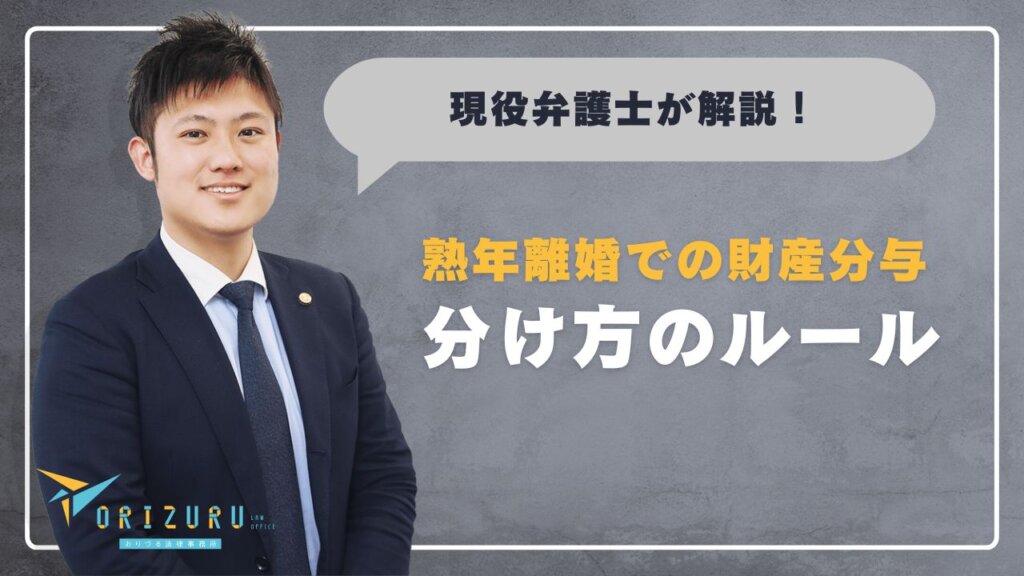
近年、結婚して20年、30年以上の長い婚姻生活を経た夫婦が離婚を選択する「熟年離婚」が増加傾向にあります。長い年月をともに暮らしてきた分、夫婦が築いた財産は多岐にわたり、高額になることも少なくありません。その結果、財産分与によって離婚後の生活設計が大きく左右される点が、若年層の離婚とは異なる大きな特徴です。特に、再就職が難しい年代に差しかかる場合は、離婚後に十分な収入を確保することが難しくなるため、婚姻中に形成された財産をいかに適切に分割するかが重要な課題となります。
本記事では、熟年離婚における財産分与の基本的な考え方や、実際の進め方、注意点などをできるだけ分かりやすく解説します。老後の生活に直結する重要なテーマですので、ぜひ最後までご覧ください。
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
熟年離婚における財産分与の基本
夫婦が離婚をするとき、民法768条に基づいて「財産分与」の手続きを行うのが原則です。これは、夫婦が婚姻生活中に協力して築いた財産を公平に分配し、離婚後の経済的な基盤を整えるための制度です。名義がどちらであっても、婚姻中に形成された財産は夫婦共有の婚姻財産として扱われ、基本的には2分の1ずつ分与されるケースが多くなっています。
ただし、婚姻前に取得していた財産や、親の相続や贈与によって取得した財産などは、原則として財産分与の対象外となります。また、熟年離婚の場合は専業主婦(主夫)の間接的な貢献が大きく評価される傾向があり、専業で家事や育児をしていた配偶者であっても、長年の婚姻生活による貢献を認められやすいのが特徴です。
熟年離婚で特に注意が必要なポイント
熟年離婚では、若い夫婦の離婚と比べて、以下のような特徴やリスクがある点に注意しましょう。
まず、婚姻期間が長いため、夫婦で形成した財産の総額が大きくなりがちです。また、高齢になるほど再就職のハードルが高くなるため、いったん離婚してしまうと、以前の生活水準を取り戻すのが難しくなる可能性もあります。さらに、健康状態や介護の問題などが重なってくると、財産分与の話し合いだけでなく、離婚後の生活設計全般を見据えた検討が必要となります。
加えて、熟年離婚ならではの大きな課題に「年金分割」があります。専業主婦(主夫)として家事・育児を担ってきた場合、厚生年金や共済年金の被保険者である配偶者の年金を2分の1まで分割することができる制度が存在します。これは老後の収入を安定させるうえで非常に重要な制度ですが、手続きには期限や必要書類など一定のルールがあるため、事前に調べておくことが大切です。
財産分与の対象となる主な資産と評価方法
熟年離婚では、自宅や投資用不動産、預貯金、有価証券、退職金、生命保険といったさまざまな種類の財産が分与対象になります。特に、老後の生活資金として積み立ててきた退職金や保険関係の資産は多額になることもあるため、評価方法をきちんと把握し、適切に算定する必要があります。
不動産を評価する際には、固定資産税評価額や路線価、不動産鑑定士の鑑定など、複数の基準が存在し、どれを採用するかで金額が大きく変動する可能性があります。また、預貯金や有価証券は、婚姻期間中に積み立てられたものかどうかを区別しなければなりません。退職金は、すでに受け取っている場合はその金額を、まだ受け取っていない場合には婚姻期間の勤続年数を考慮しながら取り扱うことが多くなります。生命保険についても、解約返戻金の有無や契約時期・保険料の支払い状況が重要なポイントです。
財産分与に際して気をつけたい問題点
財産分与は、単に表面上確認できる資産を分割すれば終わりではありません。特に熟年離婚では、長年にわたる婚姻生活で形成された財産が多岐にわたり、高額になりがちです。そのため、以下のようなポイントに注意しておくことが重要です。
隠し財産の有無を徹底的に調査する
長い婚姻期間の中で、配偶者が自分名義以外の銀行口座に資金を隠していたり、株式や仮想通貨を秘密裏に保有しているケースがないとはいえません。もし離婚後に隠し財産が発覚した場合、財産分与のやり直しを求めることは可能ですが、離婚後に再び手続きを進めるための時間や労力がかかるうえ、請求権の消滅時効(離婚から2年)といった法的な制約もあります。そうしたリスクを避けるために、離婚前の段階で徹底的に財産を洗い出し、配偶者の預金口座や投資状況、保険加入状況などを確認しておくことが望ましいでしょう。
借金(債務)の存在を確認しておく
財産分与ではプラスの資産だけでなく、マイナスの財産である借金も対象になります。たとえば住宅ローンや自動車ローンなど、夫婦の共同生活を維持するうえで必要な支出に伴う債務は、夫婦の共同債務とみなされるケースが多いです。一方で、ギャンブルや浪費など個人的な理由でつくられた借金は、夫婦の共有債務とは認められず、その借金をつくった本人が負担すべきであると判断される可能性があります。どの債務が夫婦の共同債務であり、どの債務が個人の債務にあたるのかは、具体的な事情や契約内容によって変わるため、離婚前に整理しておくことが大切です。
財産分与に伴う税金問題を見落とさない
一般的に、財産分与そのものは所得税や贈与税の課税対象となりません。しかし、不動産や株式などを売却して現金化した場合には譲渡所得税がかかったり、財産分与の範囲を超えて過度に偏った移転とみなされる場合には贈与税が課される恐れがあります。熟年離婚の場合、高額資産の売却が発生することも多いため、譲渡所得税がどの程度になるのか、どのタイミングで納付義務が生じるのかといった点を、税理士などの専門家に相談しながら事前にシミュレーションしておくことが望ましいでしょう。
相続との関係を明確にする
熟年離婚の場合、既に親の相続が発生している、もしくは近い将来に相続が見込まれるケースもあります。相続によって得た財産は原則として夫婦の婚姻財産には含まれませんが、相続した不動産を夫婦でリフォームして生活の基盤に組み込んでいたり、相続財産を元手に夫婦名義で投資を行っていたりすると、どこからが個人財産で、どこからが婚姻財産なのかが不明確になる場合があります。こうした線引きのあいまいさは、後々のトラブルにつながりやすいため、相続財産と婚姻財産を明確に区分し、どの部分が財産分与の対象に該当するのかを慎重に検討する必要があります。
実際の財産分与の進め方
熟年離婚での財産分与は、夫婦が築いた財産を整理し、どのように分けるかを具体的に決めていく必要があります。まずは、あらゆる資産や債務をリストアップし、そのなかから婚姻前の個人財産や相続・贈与で得た財産を除いて、婚姻財産を確定させます。次に、不動産や退職金など高額な資産の評価方法を決め、どちらがどの財産を取得するかを話し合っていきます。
たとえば、自宅をどちらか一方が住み続ける場合には、もう一方に代償金を支払う形をとることが一般的です。預貯金や有価証券については、口座名義に関係なく婚姻後に増えた分を対象とするため、時期や額を精査しながら公平に分ける必要があります。協議離婚の場合は夫婦間で合意が成立すればよいのですが、話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所で調停や審判を行い、その過程で財産分与の内容が定まることもあります。
弁護士に依頼するメリット
熟年離婚では、夫婦の共有財産が多額になるうえ、不動産評価や税金、退職金の算定など専門性の高い分野が絡んでくるため、スムーズに合意を形成するのが難しくなりがちです。弁護士に依頼することで、財産調査のノウハウや、書類作成・交渉・調停・裁判などの法的手続きを一括して任せることができるため、時間や労力を大きく節約できるという利点があります。
また、弁護士は不動産鑑定士や税理士などの専門家と連携して、正確な資産評価や税金対策についてアドバイスを得ることが可能です。夫婦だけの話し合いでは感情的な対立が先行しがちですが、第三者的な立場で冷静に事案を整理し、公平な解決を目指すことができます。
まとめ
熟年離婚における財産分与は、長年の婚姻生活で形成された財産をどのように分けるかによって、離婚後の生活が大きく変化する非常に重要な手続きです。特に再就職の難しさや健康問題など、若年層の離婚とは異なるリスクが伴うため、正確な資産の把握や専門家のサポートを得ながら慎重に進めることが望ましいでしょう。
一度決まった財産分与を後からやり直すのは容易ではありません。したがって、熟年離婚を検討している段階で早めに情報収集を行い、必要に応じて弁護士や税理士、不動産鑑定士などに相談することが重要です。公平な分与を実現し、離婚後の生活を安定させるためにも、焦らず確実に準備を進める姿勢が求められます。
よくある質問
Q1: 熟年離婚では専業主婦(主夫)でも財産の半分をもらえるのですか?
A1: はい。婚姻期間が長い場合、専業で家事や育児に携わっていた配偶者の貢献度も高く評価されます。名義がどちらであっても、婚姻中に共同で形成した財産は基本的に2分の1ずつが分与の基準となります。
Q2: 夫名義の家しか財産がありませんが、妻にも取得できる権利がありますか?
A2: 夫名義であっても、婚姻期間中に購入した自宅であれば財産分与の対象になります。名義を問わず、婚姻生活で築いた財産かどうかが重要なポイントです。
Q3: 離婚時に受け取っていない退職金は対象になりますか?
A3: 将来受け取る予定の退職金は、その性質や時期によっては財産分与の対象とならない場合もありますが、すでに支給が確定している部分や退職直前のケースでは、婚姻期間に応じて対象になることがあります。専門家と相談し、具体的な事情を踏まえて判断するのが望ましいでしょう。
Q4: 隠し財産があるかもしれません。どのように調べればいいですか?
A4: 配偶者の預金口座や投資状況をできるだけ正確に把握することが大切です。弁護士であれば、弁護士会照会や文書送付嘱託などの法的手段を使って調査を進めることも可能です。隠し財産が後から発覚すると、時間や手間が余計にかかるため、離婚前の段階から徹底的に調べておくことが推奨されます。
Q5: 財産分与の手続きは自分たちだけでできますか?
A5: 夫婦間の協議でスムーズにまとまるのであれば、手続き自体は可能です。ただし、不動産評価や退職金の算定など専門的な判断を要する場合は、弁護士や税理士などに相談するほうが安全です。公正証書などの形で合意内容を残せば、後のトラブルを防ぎやすくなります。
熟年離婚は、これまでの夫婦関係を清算し、新たな人生をスタートさせるうえで重大な決断です。長年にわたって積み重ねてきた財産をどのように分けるかは、今後の生活を安定させるためにも非常に大切なテーマとなります。おりづる法律事務所では、経験豊富な弁護士が丁寧にご相談をお受けし、必要に応じて各種専門家と連携しながら、最適な解決策をともに模索いたします。お悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。