【保存版】ハラスメント研修って義務なの?会社が知っておくべきこと全部まとめ
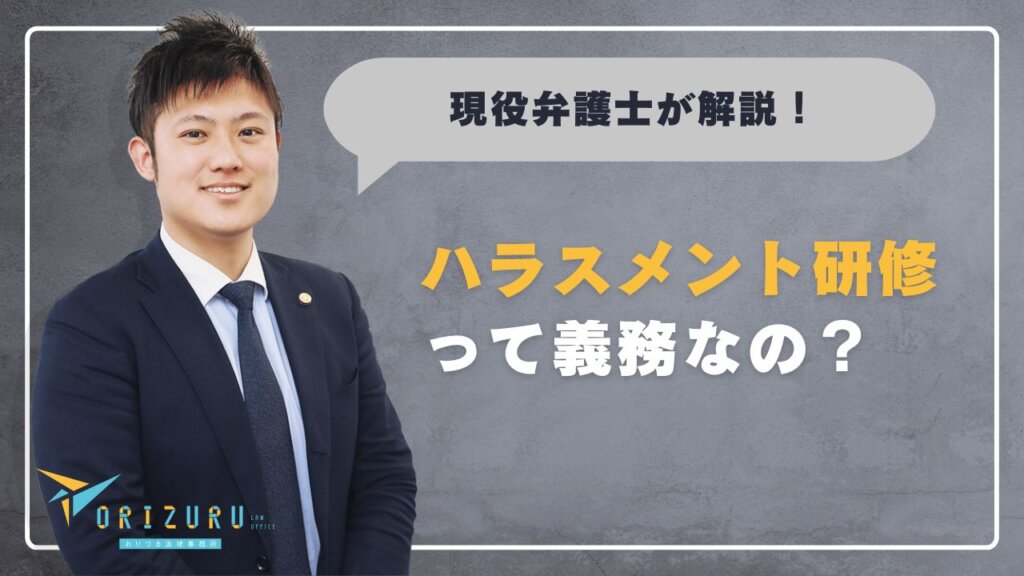
最近、「ハラスメント研修ってやらないといけないんですか?」って聞かれること、本当に増えました。
それもそのはず。パワハラやセクハラ、マタハラなど、職場での嫌がらせや不適切な言動は、ニュースやSNSで取り上げられることも多くなり、昔よりずっと社会の目が厳しくなっています。
被害を受けた従業員にとっては大きな苦痛になりますし、会社にとっても生産性の低下や人材流出、信用の失墜など大きな損害につながります。
じゃあ研修って法律で義務なのか?やらないと罰則があるのか?この記事では、そのあたりをしっかり整理しつつ、「どうせやるなら意味のある研修」にするためのポイントもあわせてお伝えします。
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
そもそもハラスメントって何?
「ハラスメント」という言葉、広く使われすぎてて少し曖昧ですよね。会社で防止対象になる代表的なものはこの3つです。
- パワハラ:立場の強さを利用して、業務の適正な範囲を超えて相手を追い詰めること
- セクハラ:性的な言動で相手を不快にさせたり、職場環境を悪くすること
- マタハラ:妊娠・出産・育休に関連して不利益な扱いや嫌がらせをすること
最近はこれに加えて、飲み会でお酒を強要する「アルハラ」、男性の育休取得を妨げる「パタハラ」、お客様からの理不尽な要求である「カスハラ」なんかも耳にします。社会の変化とともに、ハラスメントの種類はどんどん増えているんです。
ハラスメント研修って法律で義務?
ここが一番気になるところですよね。結論から言うと、「研修をやらなかったら即アウト」という法律はありません。
でも実際は、研修をやらないと法律に違反してしまう可能性が高いんです。なぜかというと、次の法律が関係しているから。
- パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)
- 男女雇用機会均等法(セクハラ防止)
- 育児・介護休業法(マタハラ防止)
これらの法律では、会社に「ハラスメントを防ぐための方針明確化」「相談窓口の設置」「周知・啓発活動」を義務付けています。この「周知・啓発活動」の中に、研修が含まれるわけです。
特にパワハラ防止法は2020年6月に大企業から先行して施行され、2022年4月からは中小企業も対象になりました。「法律で義務」と書いてないからセーフ…ではなく、やらないと義務違反に近い状態になってしまう、というのが現実です。
義務化の背景って?
なぜ国はこんなにハラスメント防止を強く押し出しているのか。
理由はシンプルで、「被害が減らないから」です。
厚労省の調査によると、過去3年でパワハラを受けたことがある人は3割以上。セクハラやマタハラも依然として高い数字です。さらにSNSでの告発も増えていて、会社の名前が一度出れば、その影響は計り知れません。
企業にとっても、ハラスメントは「人が辞める原因」「訴訟リスク」「信用失墜」など大きな損失を生みます。これを防ぐために「法律で防止策をやれ」という流れになっているわけです。
会社がやらなきゃいけないこと
法律で義務化された対応は、大きく3つあります。
- ハラスメント禁止方針を作って周知する
就業規則や社内掲示板、ポータルサイトなど、誰でも見られる形で明示します。 - 相談窓口を設置する
社内だけじゃなく、外部の専門機関や弁護士と連携すると安心感が増します。匿名相談もできる体制がベストです。 - 周知・啓発活動(研修など)を行う
新入社員、管理職、全社員向けに定期的に実施します。内容は法律だけじゃなく、事例やロールプレイもあると理解が深まります。
研修のやり方
研修は「誰に向けてやるか」で内容を変えるのがポイントです。
- 管理職向け:部下への指導とパワハラの境界線、相談が来たときの対応
- 一般社員向け:被害に遭ったらどうするか、加害者にならないための注意点
- 人事・総務向け:事後対応の流れ、証拠の残し方、外部機関との連携方法
形式は集合型でもオンラインでもOKですが、オンラインなら質問や意見交換の時間を必ず確保しましょう。
効果的な研修にするコツ
やるなら「眠くならない研修」にしましょう。
- 事例ベースで話す
抽象的な話より、リアルなケースや裁判例のほうが理解されやすいです。 - 双方向にする
一方的に説明するより、ディスカッションやロールプレイで参加してもらうと身につきます。 - 定期的にやる
年1回だけじゃ忘れます。短時間でもフォロー研修を続けるのがコツです。
よくある質問(FAQ)
- Q. 中小企業も対象ですか?
→ はい。2022年4月から義務化されています。 - Q. 外部講師に頼んだほうがいいですか?
→ 社内に専門知識がないなら頼むのが安心です。逆に社内の事情に即した内容にしたい場合は、内部実施との併用がおすすめです。 - Q. eラーニングだけでいいですか?
→ 可能ですが、理解度チェックや質問の場を作ったほうが効果は高いです。
研修料金・お問い合わせ

ハラスメント研修は「知識を伝えるだけのセミナー」では意味がありません。
当事務所では、労務問題に精通した弁護士が直接登壇し、最新の法律・裁判例や実際のトラブル事例を交えながら、会社の現場に即した研修を行います。
基本料金:1回(90分) 77,000円(税込)+交通費
追加料金:1コマ増えるごとに 33,000円(税込)
「弁護士がやるからこそ安心できる研修」をぜひご体感ください。
法律的な知識だけでなく、「これをやったらパワハラになるのか?」という実務的な線引きや、相談を受けたときの具体的な対応方法まで踏み込んで解説します。
「管理職にしっかり意識づけをしたい」
「相談窓口を設けたけど、うまく機能していない」
「裁判になったら…と考えると不安」
そんな企業様にこそおすすめです。
まずはお気軽にお問い合わせください。
御社の現状をヒアリングし、最適な研修プランをご提案いたします。
まとめ
ハラスメント研修は「法律に書いてあるから仕方なくやる」ものではありません。会社を守るため、そして社員が安心して働ける環境をつくるための大事な仕組みです。
まずは方針の明確化、相談窓口の整備、そして研修を定期的に回すこと。この3つを押さえるだけでも職場は変わります。
やるなら形だけじゃなく、中身で「やってよかった」と思える研修にしていきましょう。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。












