【父親の視点】母親が子どもの権利を失うのはなぜ?“クズ” (=不適切・不適当なのではないか)と感じた行動と親権争いの真実
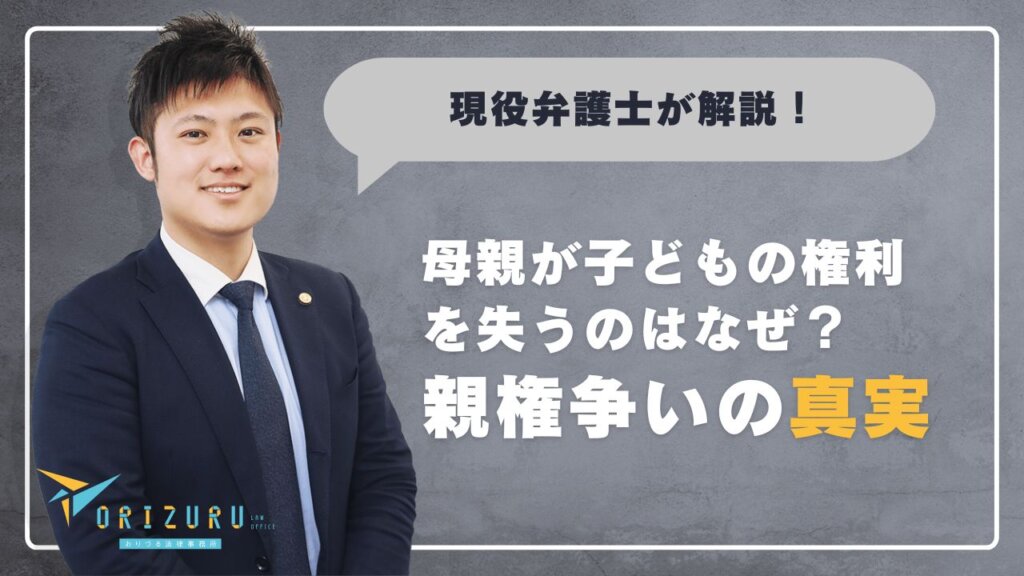
結婚生活がうまくいかず、離婚を考え始めたとき、父親として最も頭を悩ませるのが「子どもの親権」の問題ではないでしょうか。一般的には、子どもが幼いほど母親が優先されるイメージが強いものの、実際にはそうでないケースも少なくありません。
私自身が経験した離婚調停では、「どうして母親であるはずの人が子どものことを考えていないのか」と憤りを感じる場面もありました。そうなると、やはり父親としては「自分が子どもの親権を取ったほうが子どもの将来のためになる」という思いが強くなります。
本記事では、私が体験した離婚調停や親権争いをもとに、「なぜ母親が親権を取れないのか」という疑問や、父親から見て「子どもにとって母親としての責任を果たせていない」と感じる瞬間、さらには家庭裁判所や調停でどのように主張を展開すればいいのかなどについて詳しく述べていきます。あくまで私の体験談をベースにしつつ、同じように悩む男性の参考になる情報をお伝えできればと思います。
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
離婚を決意した理由:夫婦のすれ違いから始まった
結婚生活の破綻は、何か特別な事件が起こったからというより、むしろ日々の些細なすれ違いの積み重ねから始まることが多いのではないでしょうか。私の場合も、最初はちょっとした会話の中で「なぜそんな言葉を使うのか」と違和感を覚えたり、家事や育児の分担をめぐって不満を抱えたりといった小さな亀裂が徐々に大きくなっていきました。
特に子どもが生まれた後は、生活リズムが一変し、夫婦の意思疎通が難しくなります。夜泣きやオムツ替えなど、休む間もなく続く育児に追われる中、私も妻も精神的に余裕を失っていました。しかも、妻が子育ての苦労をあまり口にしないタイプだったこともあり、「何も言わない=大丈夫なのだろう」と思い込んでしまい、お互いの溝が深まっていったのです。
その結果、夫婦生活はますます冷え込み、子どもがまだ小さいうちに「離婚して別々に暮らすほうがいいのでは」と考えるようになりました。しかし、子どもの存在があるため、一度冷静になって「この先どうするか」を真剣に話し合う必要がありました。
子どもの親権をめぐる現状:一般的には母親優位?
離婚の際、子どもの親権を、父親と母親のどちらが持つかという問題は非常に大きなテーマです。一般的には、「子どもは母親が育てるほうがいい」という社会的通念が根強く、裁判所でも母親が親権を得やすい傾向があると聞いたことがある方も多いでしょう。
実際、私も離婚を考え始めた当初は、「どうせ子どもは妻のもとに行くのだろう」と半ば諦めていました。なぜなら、養育・監護の実態が母親中心であるケースや、乳幼児期は母親のケアが重要視されるため、家庭裁判所でも母親が有利になることが多いとされていたからです。
ですが、最近の傾向としては、必ずしも母親が優先されるわけではありません。「母性優先の原則」は、古い考えと言われています。家庭環境や子どもの福祉を総合的に判断し、「どちらの親と暮らしたほうが子どもにとって幸せか」という視点で裁判所が判断を行うようになっています。つまり、父親側に子どもを守る環境や育児への関心、具体的なサポート体制があると見なされれば、親権が認められる可能性は十分にあるのです。
母親側が子どもの将来を考えていないと感じた瞬間
では、どのような場合に「母親なのに子どもの幸せを考えていないのでは?」と感じるのでしょうか。私自身の体験から、以下のような行動があったときに強い疑念を抱きました。
1.育児放棄や過剰な外出
子どもが小さい時期に、妻が友人との飲み会や遊びに頻繁に出かけ、深夜になっても帰ってこないことが続くと、当然育児は私に一方的に押し付けられます。仕事で疲れていても夜遅くまで子どもを見なければならない状況に、正直「これって母親のやることなのか」と言いたくなる気持ちを抑えられませんでした。
2.子どもへの暴言や暴力の気配
疲れていてイライラするのはわかりますが、それを子どもにぶつけてしまう言動があると、夫としては「子どもの安全を守れるのか?」と疑問を感じます。私の元妻も、子どもが言うことを聞かないときに大声を上げたり、物に当たったりするなど、精神的に不安定な面を見せることが増えました。
3.金銭的なルーズさ
家計を担う上で、お金の使い方が杜撰だと子どもの生活に悪影響が及びます。必要な支払いを優先せず、自分の娯楽やブランド品に浪費してしまう姿を見ると、子どものために貯金や生活費をきちんと管理できるのか不安になります。
こうした行動が続くと、父親としては「自分のほうが子どもをきちんと育てられるんじゃないか」という思いが日に日に強くなりました。そして、それを具体的に裏付ける証拠を集めることが、親権取得への大きな一歩となります。
親権を得るために夫が注意したポイント
子どもと一緒に暮らしたい。子どもの成長を間近で支えたい。その思いを叶えるには、感情だけではなく、調停や裁判で「父親としての役割をしっかり果たせている」ことを示す必要があります。そこで私が意識したポイントをいくつか挙げてみます。
1.日常の育児実績を記録する
例えば、何時に子どもを保育園や幼稚園に送迎したのか、食事の準備やお風呂など、どのタイミングでどのようなケアをしているかをメモやスマホのアプリなどで管理しました。これを続けると、「実際にどれだけ父親が育児に関わっているか」という客観的な証拠になります。
2.子どもに対する態度を周囲に証言してもらう
親族や友人、保育士さんなど、子どもの成長を見守っている第三者の証言は非常に強力です。特に、父親が子どもとの接し方をきちんとしている様子を見ている人がいれば、その意見は調停や裁判の際に大きな説得力を持ちます。
3.就労状況と経済基盤
子どもを育てるには、安定した収入と時間的な余裕、また周囲の協力体制が不可欠です。私の場合、職場の理解を得て育児休暇の取得や勤務時間の調整ができるように働きかけました。祖父母のサポートや保育所の確保など、生活基盤をしっかり整えていることを示すことで、「父親が親権を持っても生活面で問題がない」と認めてもらいやすくなります。
調停・裁判での主張と母親の対応
私が離婚調停を申し立てたときは、まずは家事や育児の現状を丁寧に説明しました。妻側からは「母親としての愛情はある」「育児もちゃんとしている」という主張がありましたが、具体性が乏しかったのです。
一方、私のほうは先ほど挙げたような育児記録や、妻の夜遊びが多いこと、金銭管理のずさんさなどを時系列でまとめて提出しました。ここで重要なのは、あくまで「妻の悪口を言う」のではなく、「子どもの利益が損なわれている事実を証拠付きで提示する」というスタンスを貫くことです。
- 妻の主張:
- 「子どもへの愛情は人一倍ある」
- 「仕事が忙しい夫は子どもと過ごす時間が少ない」
- 「私が子育ての中心だったからこそ、子どもも私に懐いている」
- 私の反論:
- 育児記録に基づき「どれだけ自分が具体的に子どもの世話をしてきたか」を提示
- 妻が不在の日付や理由を具体的にリストアップ
- 収入や職場のサポート体制、さらに祖父母の協力が得られること(監護補助者がいること)を証明
裁判官や調停員は、一方的な感情論ではなく「子どもの現状と将来の安定」を判断材料にします。そのため、客観的なデータと証拠が何よりも効果的だったと感じています。
子どもへの影響を最小限に抑える方法
離婚や親権争いは、夫婦間の問題であると同時に、子どもにとって大きなストレスとなります。私も、一時期は子どもの前で妻と言い合いをしてしまうことがありましたが、今思えば大きな反省点です。子どもは状況を理解できないまま、親同士の不仲を目の当たりにしますから、心に深い傷を負うリスクがあります。
- 子どもには正直に、でも配慮して話す
「パパとママは喧嘩してるけど、それはあなたのせいじゃない」ということを、子どもの理解力に合わせて伝えました。離婚が決まったあとも、「パパとママは離れて暮らすけど、あなたを大事に思っていることは変わらない」と繰り返し伝えることが大切です。 - 子どもの環境を安定させる
保育園や学校、習い事など、子どもの生活リズムはできる限り変えないようにしました。親の都合で転園・転校を繰り返すと、子どもの心はさらに乱れます。 - 両親で話し合える態勢をつくる
たとえ離婚したとしても、子どもにとってはかけがえのない母親と父親です。必要最低限のコミュニケーションを取り、子どもの行事や誕生日など、協力できる部分は協力するよう努めました。
母親が信頼を失う行動パターンと父親としての心情
私のケースでは、妻の言動を「母親として信頼できない」と感じた瞬間がいくつもありました。そこには、「母性を期待している自分の価値観」と、「母親と呼べるのか疑うような妻の行動」とのギャップがあったからです。
- 子どもよりも自分の楽しみを優先する
しょっちゅう飲み歩きや友人との旅行を計画し、その費用も家計から出す。育児費用が足りなくなり、家賃や光熱費が滞ることもあったのに、まったく意に介さない様子を見て、「本当に子どもの将来を考えているのか」と疑問を抱きました。 - 反省せず、責任転嫁を繰り返す
上記のような問題が起きても、「夫がもっと稼げばいいじゃない」と開き直ったり、「夜泣きがストレスだから仕方ない」と言い訳をしたりする。自分の非を認めず、周囲に責任を押し付ける姿勢は、信頼関係を崩壊させます。 - 子どもの気持ちをないがしろにする
子どもが母親に甘えたがっているのに拒否したり、叱責しすぎたりする場面を見るたびに、「子どもにとってこの環境は健全なのか」と胸が痛みました。
父親としては、こうした行動を目の当たりにすると、自分が「子どもの成長に必要な存在」にならなければという責任感と同時に、「この人に任せたら子どもが不幸になる」という焦りも感じます。
親として「クズ」だ(不適切・不適当ではないか)と感じる行為とは何か
「どうして母親なのにこんなことをするんだ?」という怒りに近い感情を抱いたことも正直ありました。世間的には「母性は美徳」「子どもを最優先に考えるもの」というイメージがあり、私自身もそれを半ば当然のように思っていたからです。
- 約束を破り続ける
子どもを迎えに行く時間や、保育園の行事など、何度言ってもすっぽかす。結果的に私が穴埋めしなければならない状況が続く。そこに当たり前のようにあぐらをかかれると、「自分勝手すぎる」と思わざるを得ません。 - 子どもの教育をおろそかにする
子どもの学費や習い事の費用を平気で浪費に回し、子どもがやりたいことに協力しない。その一方で、自分の趣味や買い物には積極的。これでは子どもの将来を考えていないと思われても仕方ありません。 - 家庭内暴力やモラハラを行う
一見、女性のほうが被害者になるケースが多いと思われがちですが、実は母親から子どもへの暴力や夫へのモラハラもあり得ます。私の場合は直接的な暴力はありませんでしたが、妻が子どもを激しく叱責する場面を見るたびに恐怖を感じました。
もちろん誰しも完璧な親ではありませんが、子どもの安全や将来をまったく考えない姿勢を繰り返されると、正直「親としての資格がないのでは」と感じてしまいます。
子どものために最終的に選ぶべき選択肢
結論から言えば、「子どもの幸せを最優先に考えたとき、どちらが親権を持つべきなのか」が重要です。私の場合は、最終的に私が親権を持つ形で離婚が成立しましたが、それは妻を一方的に否定した結果ではありません。調停や裁判所の判断材料として、子どもの生活状況、妻の育児放棄気味の行動、金銭管理の杜撰さなどが挙げられたのは事実です。しかし、離婚後も母親として子どもとの面会交流は認めています。
- 面会交流の必要性
親がどんな問題を抱えていても、子どもにとっては大切な存在であることに変わりはありません。私は子どもが母親と過ごす時間も必要だと考え、できる限り連絡を取り合うようにしています。もっとも、子どもの安全が第一ですから、状況によっては監督付きの面会にするなどの配慮が必要になる場合もあるでしょう。 - 子どものメンタルケア
両親の離婚は子どもに大きなストレスを与えます。私は離婚後、子どもが情緒不安定になったり、母親を恋しがったりすることを想定して、スクールカウンセラーや公的な相談窓口を活用しました。子どもが自由に気持ちを話せる場があると、少しずつ心が安定していくのを感じています。
まとめ:父親目線で考える親権取得のポイント
- 母親の行動を客観的に把握する
母性を過度に理想化するのではなく、実際にどんな行動をしているのか記録し、子どもの安全や生活が脅かされている事実があれば証拠として示しましょう。
- 父親自身の育児実績と環境整備が重要
「自分なら子どもを幸せにできる」という主張には、相応の裏付けが必要です。育児記録、第三者からの評価、就労環境や家庭環境の整備など、子どもの将来をしっかり守れる準備を整えましょう。 - 子どもの気持ちを最優先に考える
親権争いが激化すると、つい感情的になりがちです。しかし、子どもは親の対立に巻き込まれる形で傷つくことが多いので、話し合いは冷静に進めることが肝心です。 - 離婚後の面会交流も視野に入れる
たとえ親権を得ても、母親を一切排除するのではなく、子どものメンタルケアを考慮しながら面会交流を設けるなど、子どもにとってベストな方法を模索するのが望ましいでしょう。
私が離婚を決意したころは、正直なところ「母親は当然親権を持つもの」という先入観が強く、「自分が親権を取れるのか?」という疑問ばかりでした。しかし、いざ蓋を開けてみると、裁判所は私が用意した客観的な証拠や妻の生活態度に対する証言を慎重に評価し、「子どもにとって最善の環境」を重視してくれました。
もちろん、すべてのケースに当てはまるわけではありません。中には母親がしっかり育児をしていて、父親側に問題がある場合もあるでしょう。大切なのは、誰が「クズ」か(不適切・不適当なのではないか)というレッテルを貼ることではなく、どちらが子どもをより健全な環境で育てられるのかを見極めることです。
もし、読者の方で「妻が子どもを顧みない」「育児を放棄しているのではないか」と悩んでいる方がいたら、まずは冷静に記録を取り、証拠を集めることをおすすめします。いざ調停や裁判になったとき、感情論だけでは通用しません。証拠と周囲の証言が揃えば、父親が親権を得る可能性は十分にあります。
最後に、どのような形になっても、子どもにとってはかけがえのない父と母であることを忘れずにいてほしいと思います。親権争いが長引くと、子どもの心に大きな傷を残してしまいます。離婚後も必要な範囲で協力し合い、お子さんの幸せを最優先に考えて行動していくことが、親として何より大切なのではないでしょうか。
以上が、私の経験を踏まえた「子どもの親権をめぐる父親の視点」です。同じような境遇で悩んでいる方々の参考になれば幸いです。子どもの将来を守るためにも、一人で抱え込まずに弁護士や行政のサポート機関を上手に活用し、正しい手続きを踏んで冷静に行動しましょう。子どもの笑顔を取り戻すために、最良の選択ができるよう応援しています。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。












