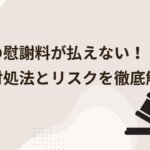【最新法改正】不同意わいせつ罪の時効はどうなる?いま知っておきたい被害者保護の重要ポイント
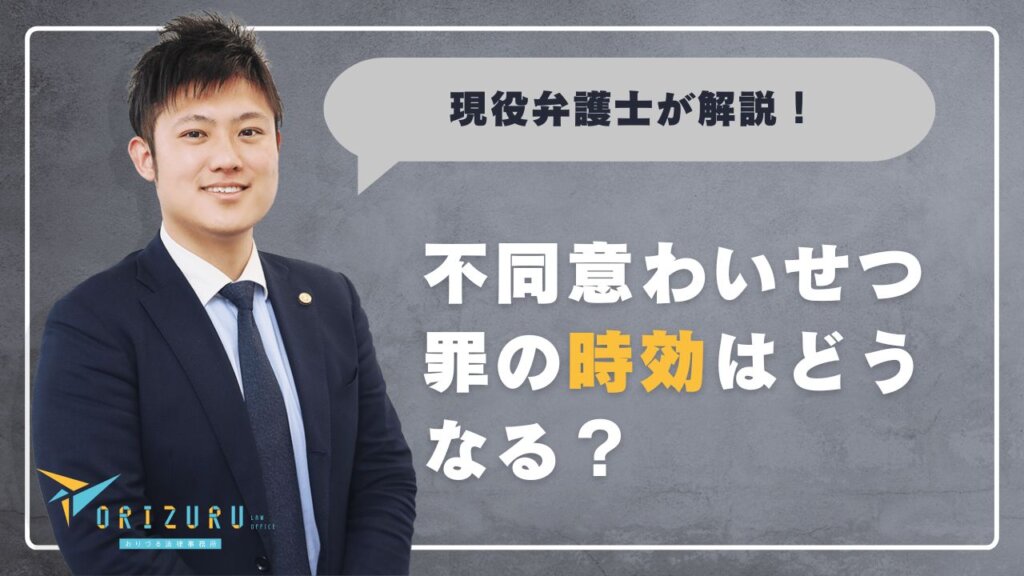
近年、日本の性犯罪に関する法律が見直され、被害者保護の観点から新たな条文が注目を集めています。その中でも、「相手の意思を十分に確認せず、性的な行為に及ぶ罪」として位置づけられる新設の概念に関心が高まっています。この改正は被害者側が抵抗できない状況や拒否の意思を示しづらい状況など、多様なケースを考慮するために行われたものです。こうした新たな法整備にともなって、加害者を処罰できる期間、いわゆる刑事手続における時効についても多くの疑問が寄せられています。
本記事では、従来の性犯罪との違いや改正の背景を踏まえながら、「被害者の同意なしに行われる性的な行為に対して適用される罪」とその時効に焦点を当てて解説します。具体的な時効の期間や、その算定方法、被害者保護の強化策に関する情報をわかりやすくまとめました。さらに、法律の改正に至る社会的背景や、今後の課題についても考察します。法律の専門家でない方でも理解しやすいよう、できるだけ用語を噛み砕いて説明しますので、最後までぜひご覧ください。
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
改正の背景:性犯罪をめぐる日本の現状
日本の刑法は、長らく明治時代に制定された規定をベースに改正が進められてきました。しかし、社会構造の変化や被害者の視点を重視した世界的な潮流などを受け、近年は性犯罪に関する規定を中心に大幅な見直しが行われています。
たとえば、以前の「強制わいせつ」や「強姦」(後に「強制性交等罪」と改められた)などの条文は、被害者が物理的な暴行・脅迫を受けていることが立証されないと適用しづらい面があると指摘されてきました。また、被害者が恐怖で抵抗できなかったケースや、加害者が優位な立場を利用して抵抗を封じるようなケースに対応しきれないという問題点も浮上していたのです。
そうした背景から、新たな概念として「被害者が明確に拒否しているにもかかわらず、または拒否できない状況を利用して行われる性的行為」が取り上げられ、これを処罰対象とするための法改正が注目を集めました。
新たに注目される「同意なき性的行為」とは
ここでいう「被害者の合意なく行われる性的な行為」とは、従来の暴行や脅迫といった強制力だけでなく、被害者の心理的・環境的要因を考慮して、実質的に同意が得られていない状況を広くカバーすることを目的にしています。
具体的には、相手の拒否を黙殺するケースや、職場内の上下関係や家庭内での力関係を悪用するケース、さらには被害者が酔いつぶれて自分の意思を示せない場合なども含まれます。このような状況で行われる性的行為は、従来の「暴行・脅迫」が立証できなければ罪に問えない場合がありました。しかし、新たな規定では、被害者の自発的な同意の有無をより重視することで、こうしたグレーゾーンにも明確な法の適用を図ろうとしています。
従来の「強制わいせつ」や「強制性交」との相違点
新たな規定と従来の「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」との大きな違いは、「暴行や脅迫の有無」に加えて「被害者が同意していたかどうか」という点がより重要視されるようになったことです。
- 強制わいせつ罪との相違
従来は、明確な暴行や脅迫を用いてわいせつ行為を行ったときに適用され、法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と定められています。新しい規定では、暴行や脅迫が立証できなくても、被害者が拒否しているのが明らかであったり、拒否できない状況にあることを知りながら性的行為を行った場合にも処罰対象となります。 - 強制性交等罪との相違
強制性交等罪は、性行為に踏み込んだ場合に適用され、法定刑は「5年以上の有期懲役」と比較的重いものです。これも、暴行や脅迫が前提になっていた部分がありましたが、新たな規定では「暴行や脅迫以外の手段によって被害者を実質的に支配し、その意思を無視した」という事実があれば、適用される可能性が出てくるわけです。
刑事手続における時効の基本的な考え方
刑事手続における「時効(公訴時効)」とは、犯罪が行われた後、一定期間が経過すると訴追(起訴)できなくなる制度を指します。犯罪の証拠が散逸したり、社会的な法感情が変化したりすることなどを理由として、一定期間を設けているものです。
日本の刑法では、罪の重さ(法定刑)に応じて時効期間が決められています。一般的には、法定刑が重いほど時効期間も長く設定されます。また、過去には性犯罪全般において被害届や告訴の期限が厳しく定められていたことが原因で、多くの被害者が「時間が経ちすぎて告訴できない」と諦めざるを得なかったケースが存在しました。
しかし、近年は被害者の心情や性的被害の特殊性を考慮し、時効や告訴期間の見直しが議論されてきたのです。性的被害は、加害者との関係性や社会的立場、被害者の心的外傷などから、被害届の提出が遅れがちになる傾向があります。そのため、時効が過度に短いと被害者の保護が十分に図れない恐れがあるという問題意識が高まっていました。
「同意がない状態でのわいせつ行為」の場合の時効期間
新しい規定が適用される罪についての時効期間は、基本的には従来の「わいせつ関連の犯罪」と同程度、もしくはそれ以上に設定される可能性が高いです。法改正の段階で示された要旨や現行の刑法の体系を考慮すると、以下のように整理されることが多いでしょう。
- わいせつ行為レベルの犯罪
従来の強制わいせつ罪は懲役6月以上10年以下なので、その重さに準ずる場合、時効は10年程度となる可能性があります。もっとも、新たな規定により行為態様が拡張されても、基本的な刑の枠組みが同レベルであれば、公訴時効はおおむね10年となります。 - 性交レベルにあたる犯罪
強制性交等罪に相当するレベルの行為であれば、法定刑は5年以上の有期懲役です。この場合、従来の公訴時効は15年が適用されることがあります。よって、新たな法整備が同程度の法定刑を想定するなら、時効期間も15年前後になるでしょう。
ただし、これはあくまで現行制度や従来の犯罪類型に基づく一般的な基準です。最終的には法律改正の具体的な条文や運用方針によって変わる可能性もあるため、最新の情報を確認することが重要です。
時効が問題となる具体的な事例と留意点
性犯罪、とりわけ被害者が自らの意思を表明しづらい環境下で起こった場合には、次のような状況で時効問題がクローズアップされます。
- 子どもの頃に受けた被害
未成年が家庭内や親族、周囲の大人から被害を受けたケースでは、子ども自身が「これが犯罪だ」と認識するまでに時間がかかったり、家庭環境から逃げられないために証拠を残せなかったりします。その結果、大人になってからようやく被害を訴えるケースも少なくありません。このような場合、すでに時効が成立してしまっていることが問題となるのです。 - 精神的ショックやトラウマで被害を言い出せない
性的被害を受けた方は、強いトラウマに苦しみ、周囲に相談するまでに長い時間がかかることがあります。特に、加害者が身近な存在だった場合、被害を打ち明けることで社会的に孤立するリスクを恐れたり、職場・学校を失う不安から告訴をためらったりすることも珍しくありません。そうして時間が経過するうちに時効が迫り、結果として法的措置が困難になるケースがあります。
こうした事例からもわかるように、性犯罪における公訴時効は被害者にとって非常にシビアな問題です。法改正によって時効期間が見直されることは、被害者が勇気を出して声を上げやすくするためにも重要なステップとなります。
被害者保護のための特例や時効延長の動き
社会的な要請の高まりを受け、性犯罪の時効に関しては以下のような特例や延長の動きがあります。
- 未成年被害に関する時効の延長や停止
子どもの性被害については、加害者が保護者などであるケースも多いため、「成人になるまでは時効を進行しない」とする仕組みが各国で検討されています。日本でも、性的虐待などの深刻な事態を考慮し、被害者が一定の年齢に達するまで時効を停止または延長する案が議論されたことがあります。 - 重大な性犯罪の時効廃止または大幅延長
性行為まで至った場合など、重大性が高いとみなされるケースについては、欧米の一部の国で時効を撤廃する動きが出ています。日本においても、殺人などの極めて重大な犯罪と同様に、極端に長期あるいは廃止を検討してはどうかという議論が一部で行われています。 - 告訴期間の延長や撤廃
以前は、性犯罪を警察に告訴するための期間が「6カ月」という制限が設けられていました。すでに撤廃された規定ではありますが、これが被害者に二次被害をもたらしていたとの声が多かったのです。現在も、一部の犯罪類型で告訴が必要とされる場合があるため、被害者が無理なく告訴できるよう制度を整備していく必要性が議論されています。
告訴期間や告訴権の放棄に関する誤解と注意
刑事手続上、性犯罪の被害者は告訴を行うことで加害者を刑事裁判にかけられる可能性が高まります。しかし、告訴を行わなかったとしても、検察官が独自に起訴する「親告罪ではない犯罪」もあります。
- 親告罪と非親告罪の違い
従来の強制わいせつ罪や強制性交等罪などは、非親告罪化されており、被害者の告訴がなくても検察官が起訴できる形になっています。一方で、痴漢などの比較的軽微とされる性的犯罪については、親告罪として処理される部分も残っており、告訴の有無が捜査や起訴に影響する場合があります。 - 告訴権の放棄に関する注意
被害者が一度「告訴しない」と表明しても、法的には取り消すことができるケースも存在します。また、加害者との示談が成立した場合でも、必ずしも刑事責任を免れるわけではありません。ただし、示談の成立が量刑に影響する可能性は高いので、法的手続きを検討する際は弁護士等の専門家に相談するのが望ましいでしょう。
被害に遭ったらどうすればいいか:相談先や支援体制
もしも性的被害に遭ったときは、以下のようなポイントを押さえつつ、なるべく早めに行動することが大切です。
- 証拠の保全
身体に付着しているものや、着衣などを洗濯せずに保管することは重要です。また、LINEやメール、SNSのやり取りなど、加害者とのコミュニケーションが残っている場合は削除せず記録しておきましょう。 - 医療機関の受診
病院に行って診断書を作成してもらうことは、身体的・精神的なケアを受けるだけでなく、証拠の一部にもなります。特に産婦人科などで検査を受けることに抵抗がある方もいるかもしれませんが、自分の健康を守るうえでも早期受診が望ましいです。 - 警察や相談窓口への連絡
迷った場合でも、専門の相談窓口に連絡してみることをおすすめします。「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」など、各都道府県でさまざまな窓口が設置されています。弁護士に相談する際の費用補助などもあるため、一人で抱え込まずに支援機関を活用しましょう。 - 法律の専門家への相談
弁護士や支援団体に相談することで、時効の問題や告訴の手続き、示談交渉など具体的なアドバイスを得られます。早めに専門家と連携することで、必要な手続きを整え、証拠をしっかり固めることができます。
今後の課題とまとめ
被害者の同意が得られない状態で行われる行為への処罰規定は、日本の性犯罪法制を大きく変える可能性を秘めています。暴行や脅迫がなくても、被害者の拒否を無視したり、拒否できない状況を利用したりする行為が処罰対象となることで、被害者の救済の幅は確実に広がるでしょう。
一方で、適用範囲が広がることへの懸念や、法改正の認知不足などの課題も残されています。被害者が自分の受けた行為が犯罪にあたると気づかないまま、時効が成立してしまうケースは依然として存在するかもしれません。被害にあったときに速やかに証拠を確保し、支援窓口へ相談できるよう、社会全体で情報を普及させる必要があります。
また、被害者の心情やトラウマを考慮すれば、時効制度そのものを見直し、より柔軟な運用を可能にする議論も必要です。特に、未成年の被害や長期にわたる虐待など、被害者がすぐに声を上げづらいケースに対しては、さらなる保護措置の検討が期待されます。
まとめると、被害者の合意がないまま行われるわいせつな行為は、法改正を通じて従来より幅広く処罰される方向に向かっています。その時効期間も性犯罪の重大性に応じて長期化や特例の導入が検討されており、被害者が適切なタイミングで法的救済を求められる環境づくりが進んでいるといえるでしょう。
しかしながら、現時点では法整備が完全に追いついていない部分もあり、今後の改正動向を注視することが大切です。被害を受けてしまった場合は、一人で悩まずに早めに専門家や支援機関に相談し、証拠の保全と自分自身の心身のケアを優先してください。法的手続を行うかどうかは、その後にゆっくり考えても遅くはありません。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。