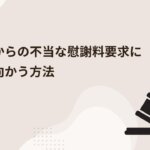高校生が大麻で逮捕されたとき、どうなる?知らないでは済まされない現実と対応法
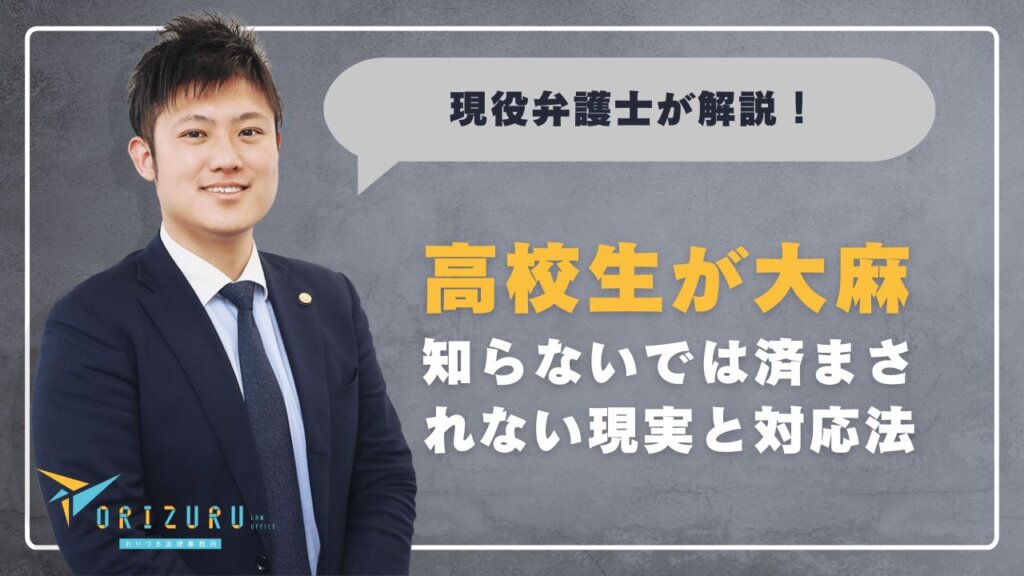
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
「遊び」のつもりが人生を変える現実
インターネットやSNSの普及により、違法薬物との距離は高校生にとっても格段に近くなりました。中でも大麻は「海外では合法」「依存性が低い」といった誤解が広まりやすく、「少しだけなら平気」「バレなければ問題ない」といった安易な気持ちで手を出してしまうケースもあります。
しかし、現実はそんなに甘くありません。高校生であっても、大麻の所持や使用が明らかになれば、厳しい法的措置を受ける可能性があります。この記事では、そうした事態に直面したとき、何が起こるのか、そしてどう対応すべきかを丁寧に解説していきます。
大麻は「軽い薬」ではない
よく「酒やタバコより害が少ない」と語られることもありますが、日本では大麻取締法により、所持・譲渡・栽培・使用すべてが明確に違法とされています。未成年であっても例外ではなく、法的には「刑罰の対象」となり得る極めて重大な問題です。
また、最近では電子タバコ型の製品やSNSを介した売買により、入手経路が巧妙かつ匿名化されていることから、家庭や学校が気づかぬうちに常習化するケースも少なくありません。
高校生が大麻で逮捕された場合の流れ
高校生が大麻に関して警察に摘発された場合、大人とは異なる「少年事件」として扱われます。ただし、手続きは厳格に行われ、場合によっては身柄拘束もあり得ます。
【高校生が大麻で逮捕された場合の一般的な流れ】
- 所持・使用が発覚し、警察に連行される(現行犯または捜査に基づく逮捕)
- 家庭への連絡、児童相談所・学校への通達
- 取調べと証拠の確保(スマホ・所持品の押収など)
- 少年鑑別所への送致(必要に応じて)
- 家庭裁判所での審判
- 保護観察、医療的措置、少年院送致などの処分決定
この間、学校生活が停止するのはもちろん、退学処分や推薦の取り消しなども現実味を帯びてきます。
家庭への影響と学校側の対応
事件が発覚すれば、本人だけでなく家庭全体にも大きな波紋が広がります。
学校への連絡は原則として行われ、内容によっては停学や退学、出席停止などの処分が下される可能性があります。学校によっては、再発防止の姿勢や家庭の対応次第で進学支援などを継続することもありますが、基本的には進学や就職に深刻な影響が出ることを覚悟しなければなりません。
また、報道によって氏名や顔が公開されることは基本的にありませんが、SNS上で特定されたり、地域で噂になるリスクもあるため、保護者としても情報管理や対応に十分な配慮が求められます。
再出発のために家庭がすべきこと
大麻に手を出した高校生が、今後再び同じ過ちを繰り返さないためには、家庭の対応が極めて重要になります。
【保護者が取るべき具体的な行動】
- 事実を受け入れ、子どもの話に冷静に耳を傾ける
- 自宅でのスマホ・インターネットの使用状況を見直す
- 医療機関や専門家に相談し、依存傾向の有無を確認する
- 法律の専門家(弁護士)と連携し、再発防止策を明確に示す
- 学校や第三者と協力し、復学・進学の道筋をつける
感情的に怒るのではなく、「なぜそうなったのか」を一緒に掘り下げ、環境を整えていくことが、再出発への第一歩になります。
弁護士への相談で得られる安心
高校生の薬物事件は、家庭だけでは対応しきれない領域です。法律の知識と交渉力を備えた専門家のサポートによって、本人の将来を守る手段が広がります。
特に次のような点で、弁護士の関与は大きな意味を持ちます。
- 家庭裁判所での審判に向けた準備と助言
- 医療的措置や保護観察への移行を提案し、少年院送致を回避
- 被害者や関係者がいる場合の謝罪・示談の調整
- 学校や進路への影響を最小限に抑えるための支援
「高校生だから大丈夫だろう」と楽観視せず、早期に適切な対応を取ることで、未来の選択肢を残すことが可能になります。
まとめ:若さゆえの過ちを「一度きり」で終わらせるために
高校生であっても、大麻を所持・使用すれば法律違反です。そしてその結果として逮捕されれば、人生設計が大きく狂ってしまうのが現実です。
とはいえ、一度の過ちですべてを失う必要はありません。大切なのは、事実から目を背けず、周囲の大人が共に向き合い、子どもがもう一度立ち直れる環境をつくることです。
「若いからこそ、やり直せる」――その可能性を信じて、正しい支援と対話を始めてください。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。