慰謝料はどこまで認められる?不同意なわいせつ行為がもたらす民事責任とは
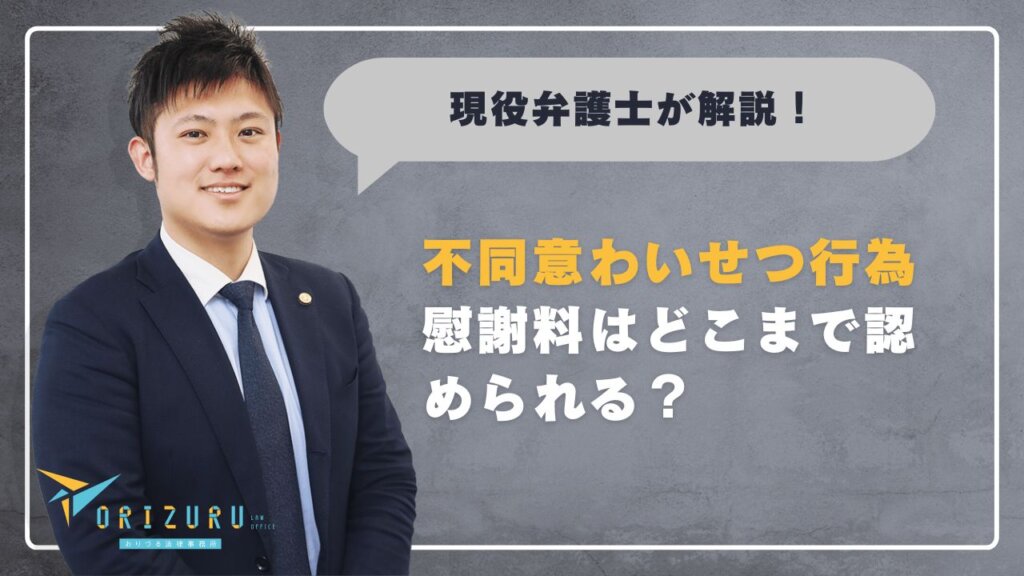
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
刑事処分だけでは終わらない責任
性的な同意がない状態で行われた接触行為が社会問題として広く認識されるようになった現在、法的な責任は刑事だけにとどまりません。加害者側にとっては、「不起訴になった」「執行猶予がついた」としても、そこで全てが解決するわけではないのです。
民事上の責任、すなわち被害者に対する損害賠償請求──とくに精神的苦痛に対する慰謝料の支払い義務が発生する可能性は極めて高いと言えるでしょう。
慰謝料とはなにか?その意味と目的
慰謝料とは、他人から不法な行為を受けたことによって生じた精神的苦痛に対して、金銭によってなされる償いです。性的なトラブルにおいては、被害者の尊厳や人格を侵害したことに対する責任として、重大な意味を持ちます。
特に、相手の意思に反してわいせつな接触があったと認定されれば、加害者は刑罰とは別に、慰謝料の請求を受けることになり、判決に基づいて支払いを命じられるケースも少なくありません。
請求される金額の目安とその判断基準
実際にどの程度の金額が求められるのかは、被害の内容や加害者の態度、社会的地位などによって大きく異なります。
【慰謝料の相場感(同意のないわいせつ行為があったとされる場合)】
- 接触は軽微、未遂にとどまる:10万円〜30万円程度
- 一時的な接触が確認されている:30万円〜100万円程度
- 継続的・計画的、悪質性が高い:100万円以上
また、精神的後遺症(不眠やPTSDなど)の診断がある場合は、さらに金額が増える傾向にあります。
示談の段階で支払われることも多いですが、示談が成立しない場合には民事訴訟で請求されることもあります。
加害者側が知っておくべきこと
加害者とされる立場の人にとっては、「謝ったのに許してもらえなかった」「示談金を払ったのにまた請求された」といった感覚を持つこともあるかもしれません。
しかし、刑事事件の示談と、民事の慰謝料請求は別の手続きです。前者で合意が得られても、後者で請求が出されることは十分にあり得ます。
また、民事で争う場合は、示談書の内容や被害者の意思表示、損害の証明などが大きな争点となります。感情的に否定するのではなく、冷静に対応することが求められます。
被害者の立場から見た慰謝料の意味
精神的な傷を負った人にとって、慰謝料の請求は「お金の問題」ではなく、「自分が受けた被害に対して正当な評価をしてほしい」という想いの表れであることが多くあります。
そのため、金額の多寡以上に、「真剣に向き合ってくれているか」「責任を認めた上で償おうとしているか」という姿勢が、加害者側には問われることになります。
法的対応を誤らないために大切なこと
慰謝料に関するやり取りは、法的な書式や時効、証拠の扱いなど複雑な要素が絡むため、当事者同士で進めるのは非常にリスクが高いです。
そこで、次のような場面では必ず法律の専門家に相談することをおすすめします。
【弁護士のサポートが必要になる場面】
- 被害者から慰謝料請求書や通知書が届いた
- 示談書の作成や確認を求められた
- 裁判を起こされた、または起こすことを検討している
- 請求額が高額で、支払能力に不安がある
- 加害の認識に争いがあり、交渉がこじれている
弁護士が関与することで、感情的な衝突を避けつつ、法的に有効な手続きで早期解決を目指すことが可能になります。
慰謝料を通じて責任と向き合う
慰謝料の支払いは、単なる“罰”ではなく、自分が相手に与えた傷に対して、真摯に向き合う姿勢を形にする手段でもあります。そこに誠意がこもっていれば、被害者との関係性が改善されるケースもあります。
逆に、「払えば済む」といった表面的な対応では、相手の怒りや不信感を深め、問題がさらに長期化することもあります。
まとめ:慰謝料は責任を示す行為でもある
性的な同意のない接触行為によって心身にダメージを負わせた場合、その責任は刑事だけでなく、民事にも及びます。慰謝料の請求があるということは、被害者がそれだけの苦痛を受けたという意思表示でもあるのです。
逃げずに、否定せずに、適切な対話と解決を図ることで、失った信頼や信用を少しずつでも回復していくことは可能です。
自分の行動が誰かを傷つけてしまった。その事実にしっかりと向き合い、責任を果たすことが、次の一歩を踏み出すためのはじまりとなります。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。












