“無理やり行為”が問題となった場合に考えるべきポイント
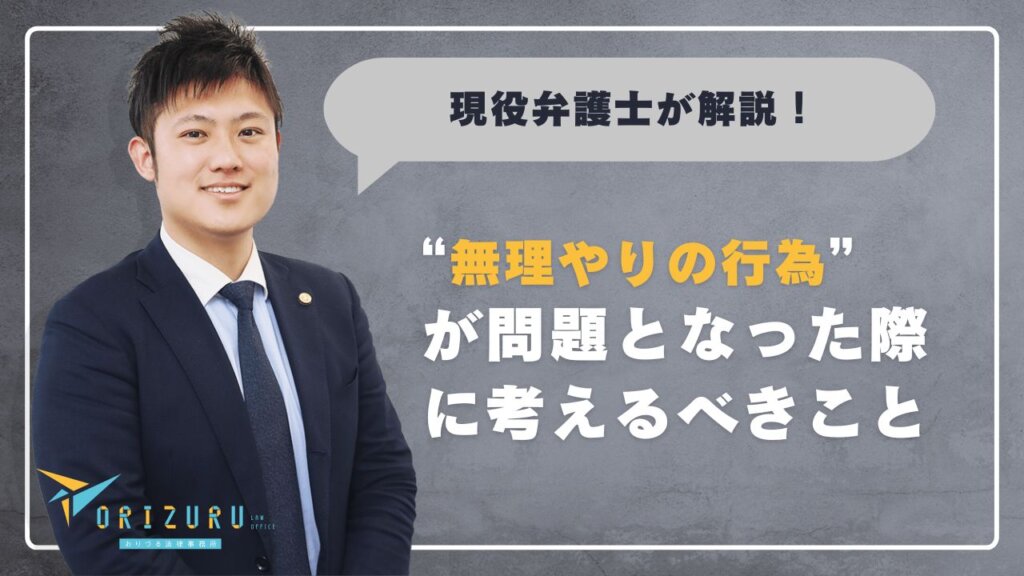
周囲から「自分の意思に反した行為を受けた」という申立てをされ、それが刑法上の重大な事件に該当すると認定されるとき、多くの場合「これまでの日常を大きく損ねるリスク」が生じます。もしあなたが、そうした行為を疑われてしまった立場(以下、本記事では「加害者側」と表現)であるなら、今後の対応次第で結果は大きく変わるでしょう。
特に、当事者同士の話し合いによって解決を図る方法(法律用語でいう“示談”)は、さまざまなリスクを軽減するうえで検討する価値があります。実際、この種の出来事では「相手との交渉次第で、刑事事件化の回避や処分の軽減につながる可能性がある」と言われることも少なくありません。
本記事では、問題の重大性を十分に理解しながら、どのように話し合いのテーブルに臨むべきか、そして最終的に円満な合意を得るにはどうすればよいかを解説します。すでに警察や弁護士が動いている可能性もあるため、焦りから独断で不適切な交渉をしてしまわないよう、基本的な注意点をしっかり押さえておきましょう。
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
なぜ深刻な疑いを受ける事態に至るのか
相手の同意を誤解していた
大きな問題となる行為の多くは「本人は相手が嫌がっていないと思っていた」「合意があると思い込んでいた」という認識のズレに端を発します。しかし、相手が結果的に強い拒否感や恐怖を抱けば、非常に深刻な事態に発展します。勘違いであっても相手が被害を訴えれば、刑事事件化する可能性は否定できません。
お酒や薬物の影響
アルコールや薬物の影響下にあったがゆえに、自制心が薄れて境界線を越えてしまうケースも少なくありません。たとえ泥酔していたとしても、「意識が朦朧としていたから仕方ない」という言い分は、法的に通用しないことがほとんどです。
周囲の通報・目撃情報
当事者同士のみならず、周囲の人が通報したり被害を目撃したりすることで事態が表面化することがあります。第三者の証言は警察の捜査でも重視されるため、言い逃れが難しくなる可能性が高いでしょう。
どのような法的リスクが存在するか
刑事処分
問題となった行為が刑法の規定に触れる場合、逮捕や起訴という形で刑事手続が進むことがあります。もし有罪が確定すれば、執行猶予付き判決もあり得ますが、状況次第では実刑となり、刑務所に服役するケースもあります。
民事上の損害賠償責任
相手に対する人格権の侵害や精神的苦痛が認められた場合、加害者側には損害賠償責任(慰謝料など)の負担が生じる可能性が高いです。請求金額が大きくなることもあるので、慎重に対応しなければなりません。
社会的信用の喪失
刑事事件や訴訟となれば、会社や家族、友人にも知られるリスクがあります。社会的評価に大きく影響するだけでなく、職場を解雇されたり、退学処分や免許取り消しなど、今後の生活に甚大な支障をきたす可能性があります。
話し合いによる解決が選択肢となる理由
刑事事件化を回避または処分の軽減につながる可能性
相手との合意が成立し、相手が告訴・被害届の提出を取り下げるなどの対応をしてくれれば、刑事事件化が回避できる場合があります。また、すでに捜査が進行していても、相手と示談が成立すれば検察官や裁判所の判断で処分が軽減される余地があります。
早期解決と負担の軽減
裁判手続などに移行すると、長期にわたる精神的・経済的負担が生じることが多いです。一方、示談であれば、当事者同士の合意によって比較的早期に決着する可能性があります。
被害者側の意向を尊重しやすい
刑事・民事の手続きに進むと、被害者側も手続きに時間と労力を費やすことになります。示談であれば、相手が望む謝罪の形や損害補償を柔軟に調整し、ある程度は被害者側の希望に沿った解決が図りやすいです。
加害者側が押さえておきたい心構え
自分の非を否定しすぎない
相手が強い苦痛を訴えている以上、加害者側が全面否定を貫くと、話し合いのテーブル自体が成立しなくなる恐れがあります。もちろん事実と異なる主張は認められませんが、少なくとも相手を傷つけてしまった可能性を真摯に受け止めることが大切です。
早期謝罪を検討する
もし自分に落ち度があると感じるなら、できるだけ早めの段階で謝罪の気持ちを示すことを検討しましょう。言い逃れや責任逃れの姿勢は逆効果となり、示談が難しくなるケースが多いです。
感情的な対応を避ける
激しい口調や脅し文句は絶対に控えてください。相手やその家族などに対して威圧的に振る舞えば、かえって警察への通報を促す結果になりかねません。冷静かつ誠意ある姿勢が、話し合いを継続するための最低限のマナーです。
話し合いの進め方と実践ステップ
相手(被害者)側の意思を確認
まずは相手が示談に応じてくれるかどうかを確認します。すでに弁護士に依頼している場合は、その代理人を通じて交渉する形になるでしょう。無理に連絡を取ろうとすると「証拠隠滅や脅迫と受け取られる」可能性もあるので注意が必要です。
事実関係を整理し、誤解を排除する
当日の状況や会話の経緯など、客観的に確認できる情報を整理しましょう。可能であれば、第三者の証言や関連する資料(防犯カメラ映像など)も確認して、相違点を洗い出します。大事なのは「自分に都合のいい事実ばかりを主張しない」ことです。
相手の要求を聞き出す
- 金銭的補償(治療費・慰謝料など)
- 謝罪の方法(直接面会、文書、代理人を通じる等)
- 再発防止策(約束・誓約書など)
被害者が何を望んでいるかを正確に把握することが重要です。金銭だけが目的というわけではなく、誠意ある謝罪や具体的な対策を求められるケースも多々あります。
合意内容の調整と書面化
話し合いが前進したら、示談書などの合意書を作成します。口頭だけでは後で「そんな話はしていない」と言われるリスクがあるので、以下の項目を盛り込むのが一般的です。
- 当事者の情報(氏名・住所等)
- 争点となった行為の概要
- 責任の所在と加害者の謝罪・再発防止策
- 支払いがある場合の金額・方法・期日
- 今後追加の請求を行わないこと(※ただし刑事処分には国家の判断があるので注意)
- 作成日と双方の署名・捺印
専門家(弁護士)に相談すべきケース
相手が法外な条件を提示してくる
何百万円、何千万円といった高額を要求されたり、到底受け入れられないような文言を突きつけられた場合、自己判断だけでは対処しきれない可能性があります。法的にみて妥当な範囲かどうか、専門家に相談してみるとよいでしょう。
脅迫的な言動がある
「家族や会社にバラすぞ」などの発言や、身体的危害をほのめかす行為があれば、それ自体が違法行為にあたる可能性もあります。無理に個人で応じると危険な場合があるので、速やかに弁護士・警察へ相談し、安全を確保しましょう。
すでに刑事事件として捜査が進んでいる
警察から呼び出しを受けている、逮捕や勾留の可能性があるという状況なら、弁護士に即時相談すべきです。早期の段階から適切なアドバイスを得ることで、結果が大きく変わることがあります。
必要となり得る費用・金銭交渉のポイント
慰謝料の相場
「いくらぐらいが相場なのか?」という問いに、画一的な答えはありません。被害の内容や精神的苦痛の程度、当事者同士の関係などにより大きく変わります。一方で過去の事例から、大まかな金額の範囲を弁護士が提示してくれることもあります。
分割払いの交渉
一括で高額を用意するのが難しい場合は、分割払いを申し出るのも一案です。ただし、相手側が応じるかどうかはケースバイケースであり、分割の際には具体的な支払期間・回数、利息や遅延損害金の扱いなどを明記する必要があります。
弁護士費用の負担
被害者側が弁護士を立てている場合、「弁護士費用も負担してほしい」と要求されることがあります。これについても妥当性を検討しながら、どこまで加害者側が負担するかを話し合うことになります。
再発防止と社会復帰に向けて
カウンセリングの利用
もし自分自身の行動コントロールが難しいと感じるなら、専門家によるカウンセリングや治療を受けることが有益です。問題の根本原因を探り、再犯を防ぐための具体的な方策を学ぶことができます。
周囲のサポートを得る
家族や信頼できる友人に協力を仰ぐことも検討しましょう。一人で抱え込むと、精神的なストレスから誤った判断をしてしまうリスクが高まります。周囲の理解と支援を得ることで、生活の立て直しもしやすくなるはずです。
社会的信用の回復
大きなトラブルに巻き込まれると、どうしても周囲の目が厳しくなりがちです。示談が成立して一定の決着を得た後も、謙虚な姿勢で生活を送り、再発防止への努力を続けることが社会的信用の回復につながるでしょう。
よくある疑問Q&A
Q1:話し合いによる合意が成立すれば、絶対に刑事事件にならないの?
A1:必ずしもそうではありません。相手が告訴を取り下げたり被害届を出さない場合、刑事事件化を回避できる可能性は高まりますが、内容が重大であると警察や検察が独自に動くケースもあります。
Q2:合意書に署名してもらえれば、もう相手から追加の請求を受けることはない?
A2:原則として、示談書に「今後追加の請求は行わない」と明記しておけば再度の請求は難しくなります。しかし、書面の内容が不十分だったり、新たな事実が出てきた場合には再燃する可能性がゼロとは言い切れません。
Q3:示談金が高額すぎると感じたときは、どうすればいい?
A3:弁護士など専門家に相談し、金額が法外かどうかを客観的に判断してもらうのがおすすめです。一方的に「高すぎる!」と突っぱねるだけでは交渉がこじれる恐れがあります。
Q4:事件後に相手との接触は禁止されたりするの?
A4:場合によっては警察や弁護士から接触禁止の要請が出ることもあります。勝手に連絡を試みると、逆に脅迫や証拠隠滅の疑いを持たれる場合があるため、必ず専門家の指示に従いましょう。
まとめ
一線を越えた行為が疑われ、その結果大きなトラブルに直面した場合、加害者側としては「どうすれば最悪の事態を回避できるのか」「これ以上問題を拡大させずに解決するにはどうすればいいのか」という切実な悩みを抱えるでしょう。話し合いによる解決(示談)は、そうした不安を多少なりとも軽減できる有力な手段です。
- まずは事実を正直に受け止め、相手の気持ちを認める姿勢を示す
- 焦らず冷静に相手の要求や状況を把握し、誠意を持って交渉する
- 合意に至ったら口約束で終わらせず、書面に残して後日のトラブル再燃を防ぐ
- 相手や周囲への脅迫や恫喝は絶対に行わない
- 必要に応じて弁護士やカウンセラー、家族のサポートを活用する
一度大きな問題を引き起こすと、社会的な信用や人間関係を取り戻すのは容易ではありません。しかし、適切な方法で当事者と向き合い、誠意ある対応に努めることで、状況を改善できる可能性は残されています。もし自力での対応が難しいと感じたら、迷わず専門家の助けを求めましょう。問題を先送りにして放置すると、取り返しのつかない事態に陥る危険性が高いという点を強く意識してください。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。












