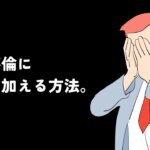性加害の法的リスクと期限――被害を受けたときに知っておきたいポイント
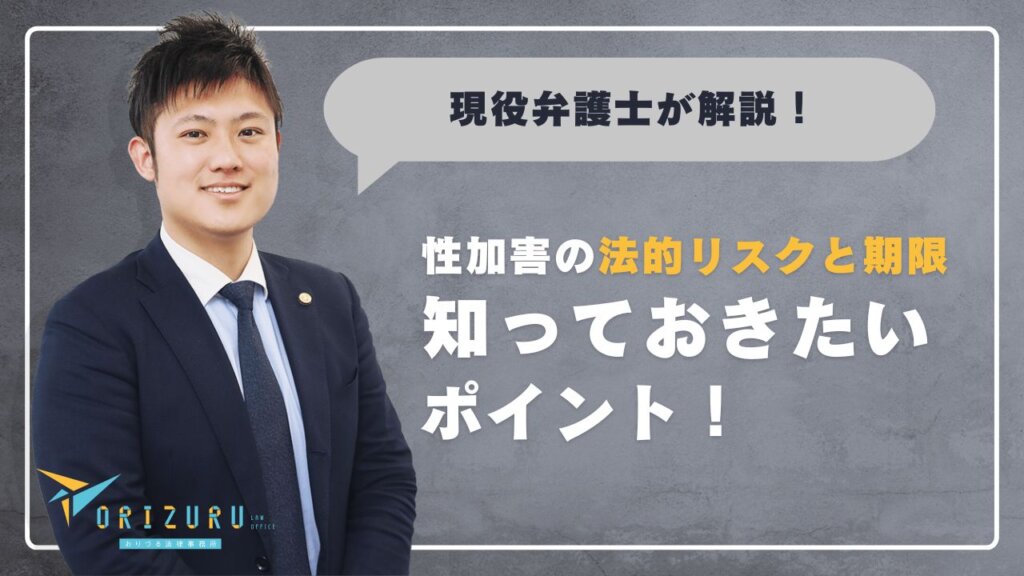
近年、日本の刑法における性犯罪の規定が大きく改正されました。その中でも、従来の「強制わいせつ」と呼ばれていた行為が、当事者の同意を欠いたわいせつ行為として再定義され、実質的な内容も明確化されています。こうした変更は被害者の保護をより厚くすることを目指す一方、これまでにない疑問や不安も生じやすくなっているのが現状です。
特に気になるのが、加害者を刑事責任に問う際の“法的な期限”です。被害を受けたものの、心の傷や恐怖心からすぐには告訴できない場合も少なくありません。その間に法的な追及の期限が過ぎてしまうのではないかと悩む方は多いでしょう。本稿では、改正後の法律がどのように合意のないわいせつ行為を規定し、加害者を裁くための期限がどのように設定されているのかを詳しく解説します。
あわせて、実際に被害に遭ってしまった方、あるいは家族や支援者の方々に向けて、どのタイミングでどのような行動を取ればよいのか、証拠収集や相談先の選び方なども紹介していきます。性犯罪被害は人生を揺るがす深刻な問題ですが、法制度は複雑でわかりにくい部分も多いです。少しでも不安を解消し、適切な対処を取るうえで参考にしていただければ幸いです。
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
改正後の性犯罪規定と合意のない行為の意義
近年の刑法改正では、従来「強制わいせつ」「強制性交等」などと表現されていた行為が、より幅広く“承諾のない性行為”“合意を欠いたわいせつ行為”として再編されました。大きなポイントは、暴行や脅迫の有無だけでなく、「被害者が自由に拒絶できる状況だったか」「しっかりした同意が得られていたか」が判断材料として強く考慮されるようになった点です。
これによって、相手が職場の上司や取引先で逆らいづらい立場にあったり、飲酒・薬の影響で思考がはっきりしない状態だったり、家族内で強い力関係の差があったりといった、従来の暴行・脅迫という文言だけでは十分にカバーできなかったケースも違法性を立証しやすくなりました。被害者が「断れなかった背景」を多面的に考慮する方向へ法律がシフトしているのが特徴です。
そもそも法的な期限とは何か
刑事事件において犯罪を起訴できる期間には制限があり、これを公訴時効(こうそじこう)と呼びます。具体的には、事件発生から一定の年数が経過すると刑事手続きを行えなくなる仕組みです。たとえば、ある罪の最大刑が懲役10年であれば、原則として事件から10年が経過すると起訴できない可能性が高まります。
公訴時効が存在する理由としては、証拠が散逸して事実認定が難しくなることや、社会の法的安定を保つため、また被疑者・被告人の防御権を保証するためなどが挙げられます。とはいえ、当事者の承諾を欠く性的被害の場合、被害者がすぐに警察へ通報や告訴を行える状況とは限りません。心身のダメージや周囲の理解の欠如など、さまざまな要因があるため、気づけば時効が迫っていたというケースも少なくありません。
改正によりどのように期限が変わったのか
令和5年(2023)年に成立した刑法の改正では、わいせつ行為や性交等に関する規定が見直され、量刑の上限が引き上げられた罪もあります。法定刑が上がると、それに伴い公訴時効の期間も従来より長く設定される場合があります。
また、被害者が子どもの場合には、成人(18歳あるいは20歳)に達してから公訴時効の期間をカウント開始とする特例が適用されるなど、子どもを対象とした性被害については特に厳罰化と長期化が進められています。行為の態様や被害の重大性によって個別に判断されるため一概には言えませんが、全体的に「従来よりも長く起訴できる余地が増えた」という理解を持っていただければと思います。
ただし、法改正によって期限が延びたとしても、やはり時間が経てば立証は難しくなるのが現実です。証拠や証言を集めるうえでも、できるだけ早く行動に移すことが望ましいといえます。
被害者が知っておきたい告訴・相談の進め方
当事者の承諾がないわいせつ行為の被害者は、公訴時効の存在を念頭に置きながら、できるだけ速やかに下記のステップを検討すると安心です。
・信頼できる相手に相談
家族や友人、または専門の相談窓口などにまずは話をする。自分だけで抱え込むと、精神的につらくなり行動を起こしづらくなるため。
・証拠を確保
事件後の診断書、当時の衣類(洗わずに保管)、現場に残された物などをそのまま残しておく。会話やSNSなどのやり取りを削除せず保存しておくのも重要。
・警察や弁護士に相談
警察への被害届提出、弁護士への依頼による告訴状の作成など、具体的な法的手続きに備える。専門家の助力を得ることで、精神的負担も軽減される。
・告訴のタイミング
告訴を迷う被害者も多いが、公訴時効の影響を考慮すると早めの決断が有利に働く場合が多い。
期限内に準備すべきこと:証拠収集・証人の確保
加害者を刑事責任に問うためには、客観的な証拠が必要となります。合意のない性行為であったことを示すには、以下のような記録や資料が重宝します。
・診断書
負傷や精神的ダメージがあれば、医師の診断書をすぐに取得する。PTSDの診断を受けた場合も含め、書面で証明できるようにしておく。
・衣類・物的証拠
事件当時の服や下着には加害者の体液やDNAが付着している可能性があるため、捨てたり洗濯したりせずに保管。
・連絡やSNSの履歴
加害者とのやり取りで、被害者が拒否していた様子や脅迫を受けていた事実などが示されれば、立証の材料になり得る。
・第三者の証言
被害直後に相談した友人や、現場付近にいた人などの証言があると、当時の状況がより具体的に裏付けられる。
時間が経過すると、証拠や証人の記憶が失われたり、物理的痕跡が消えてしまったりするリスクが高まります。公訴時効が延長されていても、立証の難易度は上がるので、やはり早めに動くのが望ましいです。
もし期限が経過してしまったらどうなる?
公訴時効が成立してしまうと、刑事裁判を行って加害者に刑罰を科すのは不可能になります。しかし、それですべての法的手段が閉ざされるわけではありません。
・民事訴訟による損害賠償請求
刑事での訴追が難しくなっても、損害賠償を求めるために民事裁判を起こすことは可能。ただし、こちらにも消滅時効があるため、起こせる期間に制限がある。
・示談交渉
加害者が任意に謝罪や補償を行う可能性もゼロではない。示談を成立させることで金銭的な補償を得たり、今後の加害行為を防止する約束を取り付けるケースも。
・被害者支援制度の活用
公的機関やNPOが提供する心理的・生活支援の制度を利用できる。たとえ刑事裁判が実現しなくても、被害後の生活を改善するためのサポートを得られる。
もちろん、加害者を刑事罰に問えない悔しさは大きいかもしれません。心のケアや生活の再建に目を向け、利用できるサポートを受けることが、その後の人生をより穏やかにする第一歩になるでしょう。
民事手続きとの違いと留意点
当事者の承諾を欠く性的行為による被害では、刑事手続きと民事手続きの2つのルートがあります。性質が異なるため、それぞれの特徴を把握しておきましょう。
・刑事手続き
警察・検察が捜査を進め、立証も主導する。公訴時効があり、期間を超えると起訴が不可能になる。被害者はあくまで“証人”という立場。
・民事手続き
被害者が原告として加害者に損害賠償などを請求する。立証は原告が主導し、刑事時効とは別に消滅時効があるものの、比較的余裕がある場合も。
刑事で加害者が有罪判決を受けると、民事裁判で賠償が認められやすくなる一方、刑事時効が過ぎても民事で争う余地が残るケースがあります。どちらを優先するか、または同時進行するかは状況によりますので、弁護士や支援団体とよく相談して決めるのが賢明です。
被害に遭ったらまず行動したいステップ
心身のダメージが大きい状況では、冷静さを保つのは難しいですが、以下のステップを早めに意識するだけでも後の手続きがスムーズになります。
- 身の安全を確保
加害者から物理的に距離を置き、可能であれば医療機関を受診する。 - 誰かに相談
家族や信頼できる友人、公共の相談窓口などへ連絡して、自分ひとりの力で抱え込まない。 - 証拠の保存
着衣や体液が付着した可能性のある物品、メールやSNSなどのやり取りは消さずに保管。 - 専門家への連絡
精神的に厳しい場合は弁護士が代理で警察と連絡を取ってくれることもある。 - 心のケア
トラウマが残る可能性があるため、カウンセリングや医療機関を積極的に活用する
専門家や支援機関の活用方法
合意のない性行為の被害を受けた方が、すべてを自力で対応するのは非常に負担が大きいです。以下のサポートを活用しながら進めるとよいでしょう。
・弁護士
被害届や告訴状の作成、警察や検察とのやり取りなど法律実務の専門家。民事での賠償請求も含め、全般的なアドバイスが受けられる。
・医療機関
産婦人科や精神科での診断書は後の証拠になるほか、心身の回復にもつながる。
・被害者支援センター、NPO
カウンセリングや行政手続きのサポートを実施。必要に応じて弁護士や他の専門家を紹介してくれる場合もある。
・警察の性犯罪相談窓口
地域によっては専門窓口を設け、プライバシーに配慮した形で相談を受けている。女性警察官が対応してくれるケースなどもある。
まとめ:適切なタイミングで声を上げるために
当事者の意思に反するわいせつ行為に関する法律は厳罰化の方向へ進んでおり、かつ公訴時効の期間にも改正の影響が及んでいます。とはいえ、期限が多少延びたとしても、時間が経つと証拠の散逸や記憶の風化など、立証が難しくなる要素は増える一方です。
被害者の方にとっては、心理的ショックや周囲からの偏見を恐れて行動を起こせない状態が続くことも珍しくありません。それでも、公訴時効の存在を念頭に置くなら、できるだけ早く相談し、動き出すことが結果的に自分を守ることにつながります。
まずは自身の安全と心身の健康を守りながら、身近な人や信頼できる機関に声をかけてみてください。そのうえで、証拠の保全や医療的サポート、警察や弁護士への相談などを行い、刑事罰や民事上の救済を検討していきましょう。告訴するかどうかにかかわらず、早期に情報と手段を確保することで、被害後の生活を少しでも前向きに再建する道を選びやすくなります。
社会全体で性加害を厳しく捉える動きが強まっている今、決して一人で苦しまず、期限や法制度の仕組みも踏まえつつ周囲と連携して進んでいただければと思います。勇気を出して声を上げることが、少しでも早い心の回復と、安全な生活を取り戻す第一歩となるでしょう。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。