【要注意】“不同意によるわいせつ”で逮捕されるケース急増!最新法改正を踏まえた実態と対処法
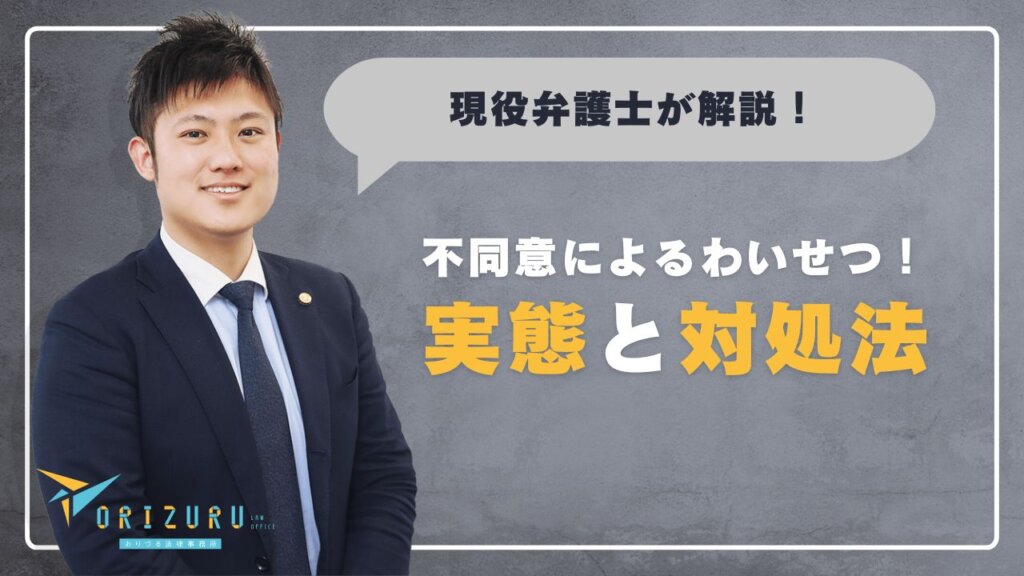
近年、日本社会では性被害に対する意識が高まり、相手の意思がないまま行われる行為に対して厳しい処罰がなされる傾向が強まっています。これは被害者の心身への深刻なダメージが社会的に認識されるようになったことや、加害行為を取り締まる法整備が進んできたことも背景にあります。さらに、令和5(2023)年の刑法改正によって合意を得ずに行われる行為の範囲が広がり、法的な罰則も強化されました。
本記事では、いわゆる相手からの同意を得ていない性行為がどのように扱われ、どのような場合に検挙されるのかを中心に解説します。法的な視点はもちろんのこと、実際に当事者になった場合の対処法や、もし自分や身近な人が疑われたときの注意点などについても触れています。記事を通じて、合意の重要性や適切な対処方法を理解していただくことが大切です。
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
合意のないまま行われる行為とは
「合意のない」行為の定義
法律の観点から見た「合意のない性的行為」は、当事者の一方が真摯に同意していないにもかかわらず行われる、あらゆる性的な接触や行為を指します。ここでポイントになるのは、単純に「嫌だと言ったかどうか」だけではなく、相手が拒否できない状況に追い込まれていたかや、逆らうことが困難な力関係があったかなども考慮される点です。例えば、酒に酔っていて明確に意思表示ができなかったり、相手が強い威圧感を受けて何も言えなかったりするケースも合意がないと見なされることがあります。
「わいせつ行為」の範囲
わいせつ行為というと、身体の特定の部位に触れる行為だけを思い浮かべるかもしれませんが、実際の範囲は広範です。下着の上から触れる程度であっても、相手の性的羞恥心を害し、社会的に容認されないと判断されれば該当しうるのです。さらに、不同意性交等に該当するような直接的な行為だけでなく、相手の意思に反して行われる性的な目的をもった行為全般が対象になります。
法律上の位置づけ:何が処罰されるのか
不同意わいせつ罪
日本の刑法176条では、「暴行または脅迫を用いるころ又はそれらを受けたこと」(1号)、「心身の障害を生じさせること又はそれがあること」(2号)、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること」(3号)、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること」(4号)、「同意しない意思を形成し、表明し又全うするいとまがないこと」(5号)により、同意しない意思を形成するなどして、わいせつな行為を行った場合、不同意わいせつ罪とし、6か月以上10年以下の懲役刑(令和7年6月1日以降は、「拘禁刑」と言われます。)が定められています。この罪は、相手が嫌がっていることを知りながら行う行為だけでなく、結果的に相手に拒否の意思を示す手段がなかった場合にも適用されます。
刑法改正による新たな規定
令和5(2023)年の刑法改正で、大きな注目を集めたのが「合意のない性交等に関する罪」(不同意性交等罪)の新設です。これは、従来の強姦罪、準強姦、強制わいせつ致死傷罪、強制性交等致死傷罪を見直し、被害者が同意していないと認められれば、必ずしも暴行や脅迫がなくても処罰できるようになった点が特徴的です。相手が拒否を明示していない場合でも、力関係や精神的圧迫などで拒否できない状況であれば罪となる可能性があります。
罪が成立するためのポイント
こうした性犯罪で問題となるのは、当時の状況の詳細や、被害者側・加害者側双方の認識がどのように食い違っているかという点です。実務では、以下の要件が特に重視されます。
- 被害者が拒否の意思を示せない状態にあったか(酒に酔っていた、意識がもうろうとしていた、心理的に圧力をかけられていた、など)
- たとえ「嫌だ」と明言されていなくても、客観的に見て同意が取れていないのではないかと判断される状況はなかったか
- 行為そのものがわいせつ・性的な目的をもつ行為と認定できるか
これらの要件を警察・検察が捜査し、証拠を集めながら最終的に犯罪が成立すると判断されれば、刑事手続きが進んでいきます。
具体的な事例:どういったケースで検挙される?
飲食店での出会いから発展するトラブル
バーやクラブなどで初めて出会った相手とお酒を飲み交わし、そのまま性的な行為に及ぶケースは少なくありません。しかし、後日になって相手が「酔っていて判断がつかなかった」「嫌だったが強く拒めなかった」という理由で警察に相談することで捜査が始まることがあります。お酒の場では当事者同士の記憶が曖昧になりがちで、証言が食い違うため、証拠や周囲の証言がカギとなるケースが多いのです。
職場や上下関係を利用した行為
上司と部下、教員と生徒、先輩と後輩など、明らかに立場に差がある関係においては「拒否できないのではないか」という見方が強まります。たとえ口頭で表立って反対しなかったとしても、「立場上強く断れなかった」「断ると人事評価や学業に影響が出ると思った」という訴えが認められると、法的にも処罰の対象となる可能性が高くなります。
ホテルや自宅への誘導
恋人未満の関係や出会ったばかりの相手を自宅やホテルに誘い、「行きたくなかったが断れずに流されてしまった」というケースも警察が扱う案件として増えています。たとえ一緒に宿泊施設に入ったからといって、イコール性的な同意をしたわけではありません。こうした状況でも、被害を受けたと感じた人が後から警察に申告すれば、犯罪として扱われる場合があります。
SNSやマッチングアプリの普及による事例
インターネットを使った出会いは一般的になりましたが、実際に顔を合わせたことがない状態から会うことも多いため、コミュニケーションの食い違いが起こりやすいです。メッセージのやりとりでは“軽いノリ”に見えても、実際に会ってみると考えが変わることは珍しくありません。こうした場合でも一度行為に及んでしまうと、後日警察に訴えられ、捜査対象となるリスクがあります。
逮捕から起訴までの流れ
- 捜査と証拠収集
警察は被害者から事情を聴き、客観的証拠(防犯カメラ映像やSNSのメッセージ履歴など)の収集を行います。ここで、当日の状況や合意の有無について詳しく調べることになります。 - 逮捕・取り調べ
集まった証拠を元に、捜査機関が「犯罪があった」と判断すれば、容疑者として逮捕状が出される場合があります。逮捕後は警察署に連行され、48時間以内に検察官のもとへ送致されます。 - 勾留の判断
検察官がさらに身柄を拘束して取り調べる必要があると考えた場合、裁判所に勾留請求を行います。認められれば最長20日間(10日+延長10日)の拘束が可能です。勾留期間中に、さらなる証拠収集や関係者への聴取が行われ、起訴・不起訴の決定がなされます。 - 起訴・不起訴の決定
検察官が「裁判で有罪が見込まれる十分な証拠がある」と判断した場合は起訴されます。一方で証拠不十分などの理由により不起訴となる場合もあり、その場合でも被害者が民事で損害賠償を請求するケースもあります。
刑罰の内容と量刑の基準
不同意わいせつ罪
前述のとおり、不同意わいせつの法定刑は6か月以上10年以下の懲役です。量刑を決める際には、犯行態様の悪質さや被害者の受けた被害の程度、加害者に前科があるかといった点が重視されます。初犯であっても行為が悪質と判断されれば、実刑になる可能性は十分にあります。
合意のない性交等を処罰する罪(不同意性交等罪)
令和5(2023)年の刑法改正で導入された「合意を欠く性交等に関する罪」は、基本的に3年以上の有期懲役と定められています。以前の強姦罪と異なり、暴行・脅迫の有無にかかわらず、相手の同意が得られていない状況であれば処罰対象が広がるため、その分捜査対象となる件数も増加が見込まれます。法廷で量刑が決定される際は、被害者の心身へのダメージの大きさや犯行に至る経緯などを総合的に考慮して判断されます。
執行猶予の可能性
性犯罪の裁判では、被害者との示談や反省の態度が量刑に影響を与えることがあり、場合によっては執行猶予がつく可能性もあります。しかし近年は被害者保護の観点から、裁判所や検察が厳しく対応する傾向にあるため、「示談すれば必ず執行猶予になる」というわけではありません。再犯リスクや被害者の負ったダメージが大きいと判断されれば、示談していても実刑が科されることがあります。
相談先・サポート機関を利用する必要性
性被害に関する問題は、被害者・加害者のどちらであっても大きな精神的ストレスを伴います。そのため、早期に専門家や支援機関に相談することが望まれます。
- 警察・性犯罪相談窓口
被害を受けたと感じた場合は、まずはためらわず警察に連絡を取るのが重要です。各都道府県警察には性犯罪の相談窓口を設置していることもあります。 - 弁護士
逮捕や起訴のリスクがある、もしくはすでに捜査が進行している場合は、弁護士の助言を早めに受けることが必要です。性犯罪を主に扱う法律事務所や弁護士も存在するため、専門分野の知識と経験がある弁護士に相談すると安心です。 - 医療機関
身体的被害がある場合は、できるだけ速やかに受診して診断書を取得しておくと、後の捜査や裁判で有効な証拠となります。緊急避妊や性感染症の検査なども必要に応じて行うことが推奨されます。 - カウンセリング機関・ホットライン
被害者はもちろん、家族や周囲の人も精神的ショックを受けるケースは少なくありません。民間の支援センターや公的な窓口に設けられたホットラインを活用し、早期に心のケアを受けることが大切です。
被害にあった場合の対処法
身の安全を確保する
加害者から距離を置き、すぐに安全な場所に移動してください。自宅以外にも、信頼できる友人宅や公共施設なども検討しましょう。
医療機関を受診
可能であれば当日中、遅くとも数日以内に医療機関を受診し、必要な処置を受けます。診断書や検査結果は後々の証拠となる場合があるため、必ず保管してください。
警察や弁護士への相談
自分で判断がつかないときは、躊躇せずに警察へ連絡しましょう。警察に行くのを迷う場合は、まず弁護士や性暴力被害者支援センターに相談してみるのも一つの方法です。
証拠保全
事件性があると判断した場合は、当日の衣服や下着、やりとりをしたメッセージ履歴、通話記録などを消さずに保管しておきましょう。些細なことでも後から重要な手がかりになることがあります。
容疑をかけられた場合の注意点
早期に弁護士へ相談
もし身に覚えがない、もしくは誤解からトラブルになっていると思われる場合でも、捜査機関の取り調べや事情聴取を安易に進めるのは危険です。専門家のアドバイスを得ながら、適切な対応を検討しましょう。
証拠や記録の整理
相手とのやりとり、場所や日時などをできる限り詳細に記録し、後からでも確認できるようにしておきます。自分にとって有利な情報が埋もれないよう、SNSのメッセージやメールは保存しておきましょう。
示談交渉とその影響
被害者との間で話し合いを行い、示談を結ぶことで刑事手続きを軽減できる場合があります。しかし、示談が成立しても必ずしも不起訴になるわけではありません。検察や裁判所は示談の有無に加えて、行為の悪質性や社会的影響も踏まえて総合的に判断します。
よくある質問(FAQ)
Q1: 「相手がはっきりと拒否していなかったら大丈夫ですか?」
A1: 相手が口頭で「嫌だ」と言わなかったとしても、心理的圧迫や環境的要因で断れない状況だった可能性もあります。外見的に拒否がわからないからと言って、自動的に合意が認められるわけではありません。
Q2: 「交際中のパートナーや夫婦でも罪になるの?」
A2: たとえパートナーであっても、毎回相手の意思確認は重要です。夫婦間であっても相手が拒否したにもかかわらず行為に及べば、犯罪と認定される場合があります。
Q3: 「お酒の席でお互いに盛り上がっていたので合意があったと思うのですが?」
A3: お酒で酔って正常な判断ができない状態だと、同意の有効性が疑われます。一方が強い酔いだった場合、その時点で本心での同意とは言えない可能性が高くなります。
Q4: 「もし相手が後になって『嫌だった』と主張し始めたらどうすればいいの?」
A4: 当日のやりとりや態度を立証できるような証拠が重要になります。相手とのメッセージや第三者の証言がある場合は、それらをもとに自分の正当性を主張する必要があります。
まとめ
相手の承諾がない性行為にまつわるトラブルは、法改正の影響もあってさらに厳しく対処される傾向にあります。被害を受けた側は、できるだけ早く安全を確保し、医療機関や警察、法律の専門家などに相談することが大切です。一方、疑いをかけられた場合は、まず弁護士を通して正しい手続きにのっとった対応を行い、証拠を整理することが必要となります。
こうした事態を回避するためにも、普段からお互いの意思を尊重し合うことが肝心です。特に飲酒の場面や立場の違いがある状況では、相手が本当に同意しているかどうかを慎重に見極める必要があります。性行為は双方が納得して行われるべきものであり、どちらか一方が拒否しづらい雰囲気や状況を作ってしまうと、後々大きな問題につながる可能性があるのです。
性被害に関する問題は、被害者・加害者ともに人生を大きく左右する深刻な事態です。本記事の情報を参考にしながら、いざというときに冷静な行動がとれるよう備えておくこと、そして普段からトラブルを避ける姿勢を心がけることが何よりも重要だと言えます。
【注意事項】
- 本記事の内容はあくまでも一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスを行うものではありません。具体的なケースについては必ず専門家(弁護士など)に相談してください。
- 記事中で紹介した法律や制度は2023年時点の情報に基づいています。今後の法改正などで内容が変更される可能性があるため、常に最新情報を確認するようにしましょう。
以上が、相手の同意を欠く性的行為に関する法的側面や逮捕に至るまでの流れ、そして被害に遭った場合や疑いをかけられた場合の対処法をまとめた記事となります。周囲で困っている方がいれば、一人で悩まずに専門家や支援機関に連絡を取るよう促してあげてください。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。












