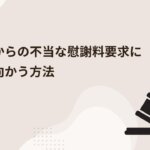相手の収入を正しく見極める!婚姻費用を多くもらうにはどう交渉すべき?
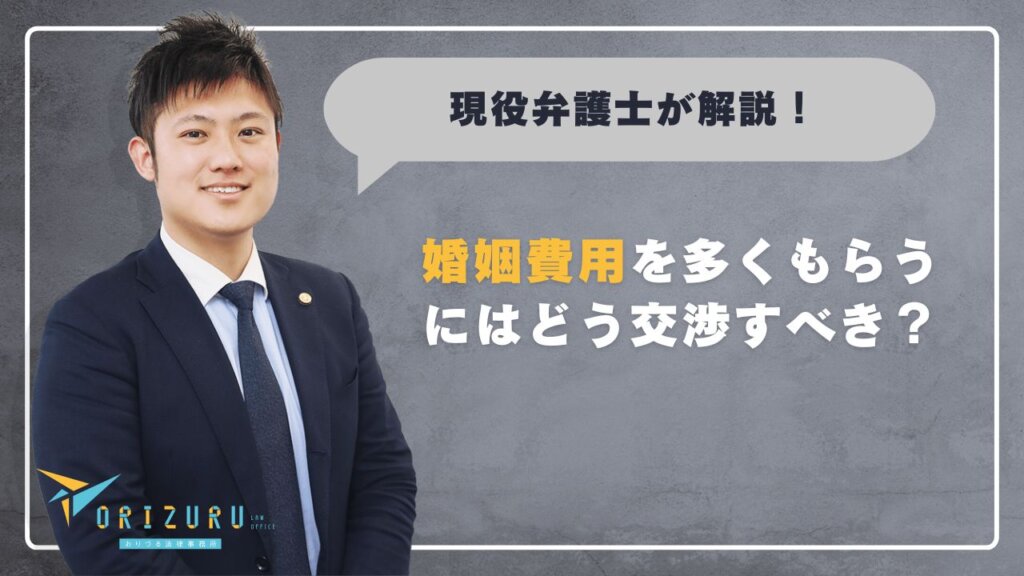
離婚や別居のトラブルが生じたとき、子どもと生活を守るために確保しておきたいのが「婚姻費用」です。婚姻費用とは、夫婦が婚姻関係にある間に必要となる生活費全般を指し、別居後も請求できるケースがあります。しかし、実際には「思っていたよりも金額が少なかった」「試算した額と異なる」といった声が多いのも事実です。
そこで本記事では、婚姻費用をより多く確保するためのポイントや、交渉・調停の際に押さえておきたい注意点を詳しく解説します。子育て中の方や専業主婦(主夫)の方が少しでも不安を減らし、安心して生活基盤を整えられるよう、ぜひ参考にしてください。
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
婚姻費用とは何か? 基礎知識を押さえよう
婚姻費用の定義
婚姻費用とは、法律上の夫婦が共同生活を営むうえで必要となる費用全般を指します。民法上、夫婦は互いに協力・扶助の義務を負うため、たとえ別居中であっても結婚関係が続く限りは、生活費や子どもの養育費などを分担しなければなりません。
対象となる支出項目
婚姻費用に含まれるものは多岐にわたります。例えば、家賃・光熱費・食費・医療費・保険料・教育費など、日常生活に欠かせない出費が該当します。夫婦どちらか一方が高額の収入を得ている場合や、子どもの教育に大きな費用がかかる場合には、求められる金額も相応に増加する傾向があります。
離婚後には「養育費」へ移行
婚姻費用は、あくまでも法律上の夫婦関係が続いている間の生活費です。離婚が成立すると、婚姻費用ではなく「養育費」の支払いが問題となります。もし離婚協議が長引いている場合や、別居が先行している場合には、婚姻費用の取り決めが非常に重要になります。
婚姻費用の算定方法:基礎を押さえる
婚姻費用算定表の存在
家庭裁判所では、過去の判例や統計をもとにした「婚姻費用算定表」を用いて、夫婦それぞれの年収や子どもの人数・年齢などに基づくおおよその目安額を算定しています。これは養育費算定表と同様に、調停や審判の実務で広く使われています。
夫婦双方の収入と生活状況がカギ
婚姻費用を具体的に決める際には、以下のような要素が考慮されます。
- 夫婦双方の年収(源泉徴収票や確定申告書で確認)
- 子どもの年齢や人数
- 子どもの習い事・私立学校など特別な教育費の有無
- 住宅ローンや家賃など住居費の負担状況
特に「どのくらいの住居費が発生しているか」は、婚姻費用の額に大きな影響を与えます。
算定表の金額はあくまで“目安”
算定表は、家庭裁判所の調停や審判でよく用いられる基準ですが、実際には個々の事情を踏まえた上で決定されるため、算定表の金額から増減することもあります。そのため、「自分たち夫婦の状況では、もう少し多くの金額を請求できる可能性があるのでは?」と考える方も少なくありません。
婚姻費用をより多くもらうためのポイント
ここからは、実際に別居中または離婚協議中の方が、婚姻費用を少しでも多く確保するにはどうすればいいのか、その具体的な対策を見ていきましょう。
正確な収入を把握する
相手方(配偶者)が自営業やフリーランスの場合、収入額を低く申告して婚姻費用を抑えようとするケースが散見されます。そこで重要なのが、配偶者の正確な年収を把握することです。
- 会社勤務なら源泉徴収票・給与明細の確認
- 自営業なら確定申告書・決算書などの確認
もし配偶者が書類の提出を拒否する場合は、調停や審判での手続きを通じて証拠開示を求めることも可能です。
子どもの特別な教育費や医療費をアピール
婚姻費用の算定表は一般的な数値をベースにしているため、私立学校の学費や習い事、持病や障がいによる医療費など、特別な出費がある場合にはその事実をしっかり主張することが大切です。具体的な領収書や診断書などを提示することで、裁判所に対して「通常以上の費用がかかっている」ことを明確に伝えられます。
住居費(家賃・住宅ローン)の扱い
婚姻費用の多寡に大きく影響するのが、住居費です。たとえば以下のような状況の場合、相手方へより多くの負担を求められる可能性があります。
- 子どもと一緒に実家や賃貸物件に移り住んだが、家賃が高額になった
- 配偶者が家に居座っているため、新たに家を借りる必要が生じた
- 住宅ローンを配偶者が単独名義で組んでおり、自分には返済義務がないのに住居費の負担が重くなっている
こうした事情を調停や審判で適切に主張することで、婚姻費用の算定に反映される場合があります。
婚姻費用の算定表の“範囲内”を意識する
婚姻費用を多くもらうためには、闇雲に相場とかけ離れた高額を要求するのではなく、算定表の上限に近いラインを狙うなど、現実的な金額設定が欠かせません。相場を無視して交渉しても、調停や審判では採用されにくいからです。算定表の金額帯をよく理解した上で、特別事情を訴えて上乗せを狙うのが王道のアプローチといえます。
婚姻費用分担の合意を早めに取り付ける
別居後、相手が婚姻費用の支払いを拒否していたり、金額を少なく渡してきたりすると、生活に大きな不安が生じます。そのため、できるだけ早期の段階で支払いに関する合意書(公正証書が望ましい)を作成することが理想です。公正証書にしておけば、相手が支払いを滞納した場合でも、強制執行の手続きをとりやすくなります。
実際の交渉・調停で有利に進めるための工夫
専門家(弁護士など)に依頼するメリット
法律の専門家である弁護士は、収入や家計状況、子どもの教育費など、あらゆる要素を踏まえて最適な主張を立てるノウハウを持っています。特に相手が婚姻費用を低く抑えようとする場合や、複雑な資産状況・収入形態を持つ場合には、専門家の助けを借りることで適正な金額を確保できる可能性が高まります。
客観的な裏付け資料をそろえる
口頭で「子どもにお金がかかる」と主張しても、具体的な証拠や資料がないと裁判所は認めにくいものです。
- 習い事の月謝や私立学校の学費の明細
- 医療費・保険料の領収書や契約書
- 家賃・住宅ローンの契約書や支払い明細
- 配偶者の源泉徴収票・確定申告書
これらを整理して提出することで、より説得力のある主張ができるようになります。
冷静かつ着実なコミュニケーション
離婚協議や別居中の夫婦間では、どうしても感情的な対立が生じやすいです。しかし、相手を強く責めるだけでは話し合いがスムーズに進みません。感情は心の内にしまいつつ、データや証拠に基づいて理路整然と話を進めることが、最終的に自分に有利な結果を引き寄せるコツといえます。
調停や審判の流れを理解しよう
調停の申し立て
協議がまとまらない場合や、相手と直接話すのが難しい場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。申立書には双方の収入や子どもの状況などを記入し、証拠書類を添付することが一般的です。
調停委員との面談・話し合い
調停では、調停委員が夫婦それぞれから事情を聞き取り、合意点を見いだすよう努めます。具体的な金額や支払い方法について、話し合いがまとまれば調停調書が作成され、法的に有効なものとなります。
不成立の場合は審判へ
もし調停が不成立となった場合は、裁判官の判断による「審判」が下されます。審判では、裁判官が双方の収入や支出状況、特別事情などを総合的に考慮して婚姻費用を決定します。審判の結果に不服がある場合は、一定期間内に即時抗告という手続きが可能です。
婚姻費用をめぐるよくある疑問Q&A
Q1:別居してすぐに婚姻費用をもらうことはできますか?
A:別居開始時点から請求自体は可能です。ただし、実際に支払われるのは合意や調停で決定した後となるのが一般的です。場合によっては、過去にさかのぼって請求できるケースもありますが、相手が支払いを拒む場合は調停手続きなどが必要になります。
Q2:相手が会社役員で収入を隠しているようです。どう対応すればいいでしょうか?
A:役員報酬や会社の利益配分を低く見せるなどの手法で、実際の収入を隠す人もいます。家庭裁判所での調停・審判を通じて、帳簿類や確定申告書の開示を求めることができる場合があります。悪質なケースでは弁護士に依頼し、証拠収集や財産調査を行うことが考えられます。
Q3:子どもの学費が急に増えた場合、婚姻費用を増額してもらうことはできますか?
A:離婚前であっても、子どもの教育費が大きく変動した場合には、金額の変更(増減)を協議・調停で求めることが可能です。まずは相手と話し合い、それが難しい場合は再度調停を申し立てるのが一般的な流れです。
Q4:配偶者にDVやモラハラを受けており、まともに話し合えません。婚姻費用を多くもらうためにどうしたらいいでしょうか?
A:DVやモラハラがある場合、直接の交渉は非常に困難です。弁護士を代理人として立てるか、早期に調停を利用しましょう。調停・審判の場では、裁判所が安全に配慮して進行するため、直接顔を合わせずに話し合うことも可能です。
離婚後を見据えた長期的な視点も大切
婚姻費用はあくまでも“夫婦関係が続いている間の生活費”であって、最終的には離婚成立のタイミングで「養育費」や「財産分与」などへと移行します。そのため、長い目で見てどのように生活基盤を作るかを考えることも重要です。
- 就職・転職を検討する:自立した収入源を確保する
- 住居の確保:賃貸契約をどう結ぶか、持ち家の場合はローン問題をどうするか
- 子どもの進学や将来設計:教育費の見通しを立て、必要なら学資保険や奨学金制度も検討
婚姻費用をいくら多くもらっても、離婚後の生活が成り立たなくなっては意味がありません。今後の人生設計を考えながら、最適な金額と期間を見極めていくことが大切です。
まとめ:婚姻費用をより多く確保するために押さえるべきポイント
- 配偶者の収入を正確に把握し、隠し収入がないか確認する
- 子どもの特別な教育費や医療費など、特別な事情を具体的に示す
- 住居費(家賃・住宅ローンなど)の実態を整理し、裁判所に正しく伝える
- 算定表の範囲内で現実的な金額を設定し、必要に応じて増額理由を主張する
- 公正証書などによる合意形成を早めに行い、滞納リスクを減らす
- 弁護士や調停を活用して冷静かつ着実に交渉を進める
- 離婚後の生活設計まで見据え、長期的な視点で準備する
「婚姻費用を多く確保したい」と願うのは、子どもや自分の生活を守るために当然のことです。しかし、感情的に大きな額を要求するだけでは、スムーズに合意へ至りにくいのも事実。算定表や特別事情を踏まえ、裁判所や相手方を納得させる根拠を用意することが鍵となります。
もし交渉が難航したり、相手が収入を隠そうとしている疑いがある場合は、遠慮なく専門家に相談しましょう。調停や審判などの法的手続きを踏むことで、客観的な資料に基づいた正当な金額を得られる可能性が高まります。
離婚・別居の局面は精神的にも大きな負担がかかりますが、正しい情報と的確な手順を踏むことで、より安心できる生活の基盤を作れるはずです。本記事が、婚姻費用に関して不安を抱える方々の一助になれば幸いです。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。