子どもを育てる意欲と環境が決め手になる――父親が親権を得るまでの流れと具体的なポイント
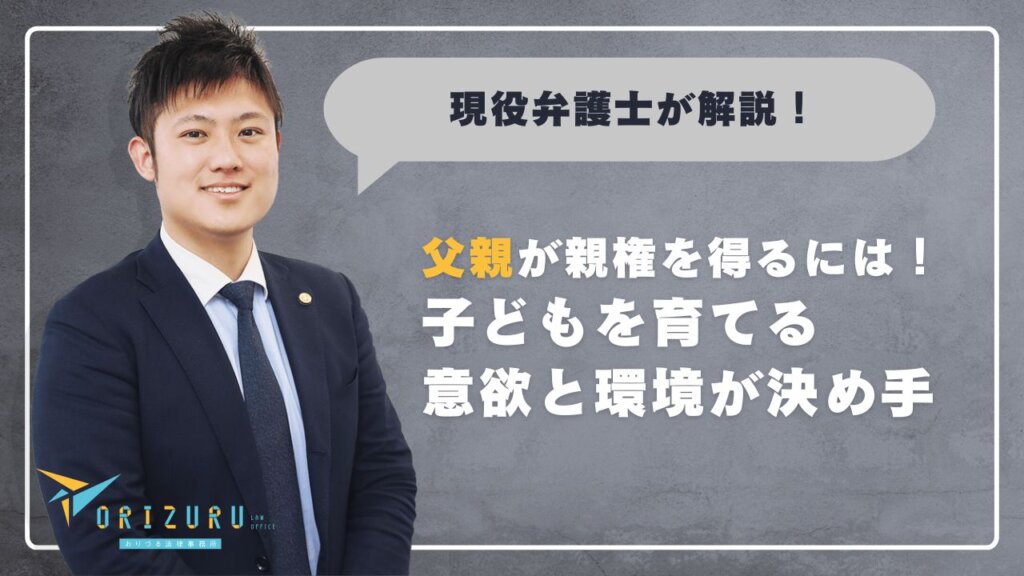
離婚に際して話し合わなければならない重要な事項の一つが、子どもの親権です。従来、子どもを引き取るのは母親というイメージが強いかもしれません。しかし近年では、父親が親権者として選ばれるケースも増加傾向にあります。では実際に、どのような経緯や条件のもとで父親が子どもの親権を得ることができるのでしょうか。
本記事では、父親が子どもの親権を取得するまでの流れ、実際に考慮されるポイント、そして具体的な準備方法を中心に解説していきます。父親としてお子さんを第一に考え、その成長環境を整えたいと願う方にとって、少しでも参考になる情報となれば幸いです。
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
親権とは何か
親権の意味
日本の民法上、未成年の子どもの保護や監督、養育に関する権利義務を「親権」と呼びます。親権者は子どもの衣食住や教育、そして日常的な世話をするだけでなく、財産管理や法的行為の代理を行う責任を負います。つまり、子どもを育てるうえで最も大きな決定権と責任をもつのが親権者なのです。
親権の種類
日本では、父母が離婚する際、父または母のどちらか一方が単独で親権者になることが定められています。共同親権制度を取る国もありますが、日本の法律では、離婚後に父母が共同で親権を行うことは認められていません。
離婚する夫婦は、以下のいずれかの方法で親権者を決定します。
- 協議離婚:夫婦の協議によって親権者を決定する
- 調停離婚:家庭裁判所の調停手続きを利用して話し合う
- 審判離婚・裁判離婚:話し合いで合意できない場合、審判または裁判によって親権者を決定する
離婚手続きの種類を問わず、親権者がどちらになるかは「子どもの最善の利益」という観点を基準に判断されます。
父親が親権を得る主な理由
母親が親権者になるケースが多いのは事実ですが、近年では父親が指定される事例も目にするようになりました。ここでは、父が子どもの養育者として認められやすいとされる理由をいくつか挙げてみましょう。
実際の養育実績がある場合
子どもが生まれてから離婚に至るまでの間、父親が中心となって家事や育児を行ってきた場合、生活環境の継続性が考慮されます。たとえば、母親が仕事などで多忙だったり、家庭を離れていたりして父が事実上の主たる監護者として子どもと過ごしていた場合、そのまま父親を親権者に定めたほうが子どもの生活が安定すると判断されることがあります。
経済的安定が期待できる場合
親権者を決定するうえでは、経済力も無視できません。父親の方が継続的な収入や雇用環境が整っている場合、子どもに十分な生活費や教育費を提供しやすいとみなされることがあります。ただし、経済力だけで判断されるわけではなく、子どもの世話を実際にどの程度できるのかという面もあわせて見られる点に注意が必要です。
母親に問題がある場合
子どもの虐待やネグレクト(育児放棄)、あるいは精神的な疾患や薬物依存など、母親側に深刻な問題があるときは、父親が親権者となる可能性が高まります。家庭内暴力の存在や、子どもの教育に悪影響を及ぼす行為が認められた場合も同様です。
子ども自身の希望
子どもがある程度の年齢(おおむね10歳以上)になっている場合は、その意思や希望が尊重される傾向にあります。子どもが父親との生活を望む場合、面談調査などでその意思が確認されれば、父親が親権者となる後押しとなることがあります。
父親が親権を得るために押さえておくべきポイント
父親が親権を主張する場合、以下のポイントを意識して準備を進めることが大切です。
日々の育児記録を残す
裁判所や調停で「誰が主に子どもの面倒を見ていたか」が争点になることがあります。そのため、以下のような育児に関する記録を残しておくと有利です。
- 毎日の食事や送り迎えの状況
- 宿題や習い事のサポートの度合い
- 休日の過ごし方やレジャーの記録
- お弁当作りや洗濯など家事全般の担当状況
これらの記録があれば、実際に子どもの生活をどの程度支えてきたかを客観的に示すことができます。
経済的・生活環境の安定を示す
親権を獲得するためには、「子どもが安心して暮らせる環境を提供できる」という点が極めて重要です。そのためには、以下の要素をアピールする必要があります。
- 安定した職業や収入を得ているか
- 住環境は子どもに適した広さや安全性を備えているか
- 保育園や学校への通学の利便性はどうか
- 親族や周囲からのサポート体制はあるか
たとえフルタイムで仕事をしていたとしても、祖父母やヘルパー、地域のサポートなどをうまく活用できれば、子どもに十分な世話を行うことが可能になります。
子どもとの良好なコミュニケーション
子どもの発育には、安定した愛情関係が欠かせません。離婚の局面では、どうしても父母の対立が表面化しがちです。しかし、父として親権を望むのであれば、子どもの気持ちや生活を最優先に考え、心理的なサポートをしっかり行う姿勢を示すことが大切です。
- 子どもが抱えている不安を聞き出す
- 学校や習い事の様子をこまめに確認する
- 定期的に面談や相談の場を設ける
子どもの健全な発達を支えるためにも、日頃からのコミュニケーションが大切です。
調停や裁判に備えた心構え
協議離婚でスムーズに話がまとまればよいのですが、親権が争点となった場合には家庭裁判所の調停や裁判に発展することがあります。その場合は、下記の点を意識しておくとスムーズです。
- 弁護士等の専門家に相談:離婚問題や親権問題に強い弁護士を探し、法的なサポートを受ける
- 客観的な証拠の準備:日々の育児記録や家計簿、子どもとの写真など、具体的な裏付け資料をそろえる
- 感情的な対立を避ける:裁判所では両親の対立ではなく、子どもの幸せが最重要視される。過度な誹謗中傷は逆効果となる可能性が高い
実際に父親が子どもの暮らしを引き受けた成功例
ここでは、離婚後に父がメインで子どもの養育を担った事例をいくつか取り上げ、なぜそのような決定が下されたのかを考えてみましょう。
共働き家庭での育児実績が評価されたケース
ある共働き家庭では、母親が長時間労働をしていたため、家事や育児の大半を父親が担当していました。子どもは学校から帰宅後、父親とともに過ごす時間が圧倒的に長く、母親とは週末しか顔を合わせない状態だったそうです。
離婚の話し合いが始まると母親側も親権を主張しましたが、家庭裁判所の調査で、子どもが普段から父親との生活を中心にしていることが明らかになりました。結果として、「環境の継続性」の観点から父を親権者に指定するのが望ましいと判断されました。
子どもの希望が大きく影響したケース
別の事例では、小学生の子どもが「お父さんの家で暮らしたい」とはっきり希望を伝えたことが決め手になりました。母親との関係が悪かったわけではありませんが、子どもが学業や習い事で父親からサポートを受けることが多く、父子で過ごす時間に安心感を覚えていたようです。
裁判所も子どもの意向を尊重し、継続して父が日々の学習や通学を支えることが子どもの利益になると判断しました。子ども本人の強い意思表明が、結果を左右した具体例です。
母親が不安定な状況にあったケース
母親に精神的な問題や経済的な不安が見られる場合は、父親が子どもの暮らしを引き受ける可能性が高まります。たとえば、母親がうつ病の治療を続けていて十分な育児が困難だったり、長期的に離職状態にあるなど、生活基盤が脆弱とみなされるケースです。
裁判所はあくまで「子どもが安心して暮らせるかどうか」を最優先に判断するため、母の体調や環境が整う見通しがない場合、父が親権を得る方向へ話が進むことがあります。
父親が親権を主張する際の注意点
母親を一方的に批判しない
子どもの利益を最優先に考える家庭裁判所では、父母が相互に協力できるかどうかも重要な視点となります。あまりに母親を一方的に批判すると、「他方の親との面会交流を妨げる恐れがある」と見なされる可能性があります。子どもにとっては父母どちらも大切な存在であることを尊重しましょう。
子どもの気持ちを軽視しない
いくら父親が経済的に安定していたとしても、子どもが強く母親との暮らしを希望している場合は、その意向が尊重される可能性が高いです。無理やり子どもの意思をねじ曲げるような働きかけは逆効果となるため、子どもとの対話を大切にする姿勢が求められます。
面会交流への柔軟な対応
父が親権者となった後でも、母親は子どもと会う権利(面会交流権)を持ちます。子どもの心身の健全な成長を考えれば、適切なルールのもとで母子の交流を確保してあげることが望ましいです。相手との関係が悪い場合でも、子どもの立場を最優先し、冷静な対応を心がけましょう。
弁護士・専門家のサポートを活用する
離婚や親権に関する法律は専門的であり、経験や知識が不足しているとスムーズに話を運べないことが多々あります。父親として親権を主張するなら、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談し、書類の準備や調停・裁判の手続きをサポートしてもらうのが賢明です。
- カウンセラーや相談員との連携:子どもの心理的ケアや生活環境の整備に関する専門家と協力する
- 自治体のサービス活用:シングルファーザー向けの情報や支援策を行政が提供している場合がある
- 無料相談の利用:弁護士会や自治体によっては、無料法律相談を実施しているところもある
専門家の意見やサポートを受けることで、父親が取りうる最善の行動を客観的に検証できるようになります。
離婚後の子どもをめぐる手続きを確認しよう
戸籍や苗字の変更手続き
離婚に伴い、子どもの戸籍や苗字の変更が発生する場合があります。親権を得た後も、実際にどの戸籍に入れるのか、旧姓に戻すのかなど、戸籍手続きにおける流れを把握しておきましょう。
養育費と面会交流の取り決め
父親が親権者となった場合でも、母親に対して養育費を請求できるケースがあります。養育費は子どものための費用であり、両親の経済力に応じて公平に分担するという考え方に基づきます。また、子どもと母親との面会交流についても、具体的な回数や方法を文書化し、トラブルを避けるようにしましょう。
学校や習い事の手続き
父子家庭となっても、子どもの学習環境をできるだけ変えないほうが精神的にも安定します。学校の先生や習い事の担当者にも、家庭状況が変わることを早めに伝えておきましょう。事前に説明しておくことで、必要な対応や配慮を受けやすくなります。
父親としての心構え―子どもを第一に考える
子どもの親権を勝ち取ることがゴールではなく、その後の生活が本番です。離婚による環境の変化は、子どもにとっても大きな負担となる可能性があります。
- 愛情を言葉や行動でしっかり示す:忙しいからといって放置せず、スキンシップや会話を大切にする
- 定期的な健康管理と学業チェック:仕事で忙しい中でも、定期健診や家庭学習の状況をこまめに確認する
- 周囲のサポートを積極的に活用:祖父母や友人、地域の子育て支援施設など、頼れるものは遠慮なく活用する
父親が一人ですべてを背負い込むと、肉体的にも精神的にも限界が来てしまいがちです。家族や専門機関と協力しながら、子どもが安心して暮らせる環境を作り上げていきましょう。
まとめ
かつては母親が子どもの親権を得ることが多かった日本ですが、最近は父がメインで子どもを育てる事例も確実に増えています。家庭裁判所は父と母どちらかに肩入れするわけではなく、「子どもの最善の利益」を見極めるために、実際の養育実績や経済状況、子どもの意向などを総合的に判断します。
父親が親権を主張する際には、子どもの生活基盤をきちんと整え、そのために必要な証拠や準備を怠らないことが大切です。育児記録の収集や専門家への相談、子どもとのコミュニケーションを重ねることによって、子どもが幸せに暮らせる道を切り拓くことができます。
離婚後の人生は、子どもにとっても親にとっても大きな転換期です。しかし、親権を得たとしてもそれはスタートラインに過ぎません。父親として、子どもの成長を第一に考え、生活面・精神面で力強く支えていく覚悟が求められます。父と子で手を携えながら新たな家庭を築いていく――その過程で生まれる絆は、きっとかけがえのないものとなるでしょう。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。












