熟年離婚の慰謝料|請求できる条件と金額の相場
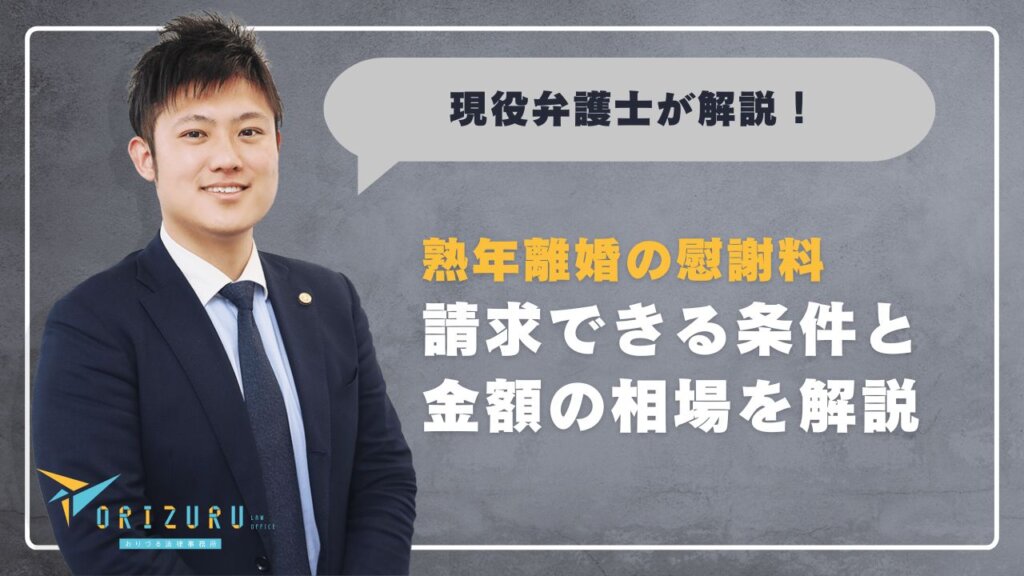
長年連れ添った夫婦が離婚を選択する「熟年離婚」。近年、その数は増加傾向にあり、それに伴い熟年離婚における慰謝料の問題も注目されています。若い世代の離婚とは異なる特徴や考慮すべき点があり、慰謝料の請求条件や金額にも独自の傾向があります。
本記事では、熟年離婚における慰謝料の基本的な考え方や請求できる条件、相場金額などについて詳しく解説します。熟年離婚を検討されている方や、すでに手続きを進めている方の参考になれば幸いです。
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
熟年離婚における慰謝料の基本
慰謝料とは
- 離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)が、精神的苦痛を受けた配偶者に対して支払う損害賠償金のこと
- 民法709条(不法行為による損害賠償)および民法710条(財産以外の損害の賠償)に基づく
熟年離婚の特徴
- 婚姻期間が長期(20年以上)にわたる
- 子どもが成人していることが多い
- 退職金や年金が主な収入源となる
- 再就職が難しい年齢である
- 住宅ローンが完済していることが多い
- 健康問題を抱えていることがある
これらの特徴は、慰謝料の請求条件や金額にも影響を与えます。
熟年離婚で慰謝料を請求できる条件
法律上の離婚原因の存在
慰謝料を請求するためには、民法770条に定められた離婚原因が必要です。主な離婚原因は以下のとおりです。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 配偶者が第三者と肉体関係を持った場合
- 配偶者が第三者と肉体関係を持った場合
- 悪意の遺棄
- 正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を放棄した場合
- 正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を放棄した場合
- DV(暴力)・暴言
- 身体的・精神的暴力を振るった場合
- 身体的・精神的暴力を振るった場合
- 重大な侮辱
- 人格を否定するような言動を繰り返した場合
- 人格を否定するような言動を繰り返した場合
- 性格の不一致
- 婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
- 婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
熟年離婚特有の慰謝料請求条件
一般的な離婚原因に加えて、以下のような特有の事情が慰謝料請求の条件となることがあります。
定年退職後の夫の言動
- 退職後、家事に非協力的で妻に過度な負担をかける
- 「亭主関白」的な態度で妻を支配しようとする
- 趣味や外出ばかりで家庭を顧みない
長年の精神的苦痛の蓄積
- 長年にわたる無視や冷遇
- コミュニケーション不足による精神的孤独
- 家庭内別居状態の長期化
経済的な問題
- 退職金や年金の使い方を一方的に決める
- 生活費を渡さない
- 浪費や賭博などで家計を圧迫する
介護の問題
- 病気や障害を抱えた配偶者の介護を拒否する
- 親の介護に非協力的で、一方に過度な負担をかける
慰謝料請求権の消滅時効
- 損害および加害者を知った時から3年
- 不法行為の時から20年
熟年離婚の場合、長年の苦痛の蓄積が離婚原因となることが多いため、どの時点から時効を計算するかが問題になることがあります。一般的には、最後の不法行為から時効が進行すると考えられています。
熟年離婚における慰謝料の相場
一般的な慰謝料の相場
離婚原因や婚姻期間、有責性の程度などによって大きく異なりますが、一般的には以下のような範囲になります。
- 軽度の有責性(性格の不一致など):0~100万円程度
- 中程度の有責性(悪意の遺棄など):100万円~300万円程度
- 重度の有責性(DV、長期間の不貞行為など):300万円~500万円程度
- 極めて重度の有責性(重大なDV、長期間の不貞行為と経済的損害の併発など):500万円以上
熟年離婚特有の要素による増減
熟年離婚では、以下のような特有の要素によって慰謝料が増減する可能性があります。
増額要素
- 長期間の婚姻関係(30年以上など)
- 専業主婦(主夫)の経済的自立の困難さ(高齢で再就職が難しいなど)
- 健康上の問題(離婚後の生活に支障がある場合)
- 住居の問題(離婚により住居を失う場合)
- 長期間の精神的苦痛(長年にわたり精神的苦痛を受けてきた場合)
減額要素
- 双方に有責性がある
- 既に別居期間が長い(精神的苦痛が軽減されているとみなされる)
- 財産分与や年金分割で十分な経済的保障がある
具体的なケース別の慰謝料相場
ケース1:定年退職後の夫の態度変化による離婚
- 状況:結婚30年。夫が定年退職後、家事に非協力的で、妻を無視するようになった。外出ばかりで家庭を顧みず、妻は精神的に孤独な状態が5年続いた。
- 慰謝料相場:100万円~200万円程度
- 理由:悪意の遺棄や重大な侮辱に該当する可能性があるが、身体的暴力や不貞行為などの重大な有責事由がないため。
ケース2:長年のDVや暴言による離婚
- 状況:結婚35年。夫から長年にわたり暴言や時折の暴力があった。子どもの独立を機に妻が離婚を決意。
- 慰謝料相場:200万円~300万円程度
- 理由:DVや暴言は重大な有責事由であり、長期間継続していたため。
ケース3:熟年期の不貞行為による離婚
- 状況:結婚25年。夫が定年退職後に不貞行為に及び、それが発覚して離婚。不貞期間は2年程度。
- 慰謝料相場:200万円~300万円程度
- 理由:不貞行為は重大な有責事由だが、期間が比較的短いため。
ケース4:経済的虐待による離婚
- 状況:結婚40年。夫が退職金を妻に黙って使い込み、年金も生活費として十分に渡さない状態が続いた。
- 慰謝料相場:200万円~300万円程度
- 理由:経済的虐待は悪意の遺棄に該当する可能性があり、長期間の婚姻関係があるため。
ケース5:介護疲れによる離婚
- 状況:結婚30年。夫が病気になり、妻が10年間介護したが、夫は感謝の気持ちを示さず、暴言を吐くようになった。
- 慰謝料相場:100万円~200万円程度
- 理由:病気という事情があるものの、長期間の暴言は精神的苦痛を与えるため。
慰謝料の増額を求める際のポイント
証拠の収集
- DVや暴言の証拠:診断書、録音、写真、目撃者の証言など
- 不貞行為の証拠:メール、LINE、写真、目撃者の証言など
- 経済的虐待の証拠:通帳の記録、生活費のメモ、借金の証拠など
- 精神的苦痛の証拠:診断書、カウンセリングの記録など
具体的な精神的苦痛の主張
- うつ病などの精神疾患の発症
- 睡眠障害や食欲不振
- 社会生活に支障が出る程度のストレス
- 自殺を考えるほど追い詰められた状況
長期間の婚姻関係の強調
- 長年にわたる家事・育児への貢献
- 配偶者の仕事や社会的地位向上への協力
- 親の介護などへの貢献
- 我慢して婚姻関係を継続してきた事実
離婚後の生活への影響の説明
- 高齢による再就職の困難さ
- 住居の確保の問題
- 健康上の問題と医療費の負担
- 老後の生活不安
慰謝料と他の離婚給付との関係
財産分与との関係
- 慰謝料と財産分与は別個の制度だが、総合的な離婚条件として関連付けて協議されることが多い
- 財産分与が多い場合、慰謝料が減額されることがある
- 逆に、財産分与が少ない場合、慰謝料で補完することがある
- 一括して「解決金」として合意するケースもある
年金分割との関係
- 年金分割が行われると、慰謝料額に影響を与える場合がある
- 年金分割で十分な経済的保障がある場合、慰謝料が減額されることがある
- 年金分割の対象とならない期間が長い場合、慰謝料で補完することがある
婚姻費用との関係
- 別居中の婚姻費用の支払い状況も慰謝料額に影響
- 婚姻費用が適切に支払われていた場合、慰謝料が減額される可能性がある
- 支払われていなかった場合は増額要素となることもある
慰謝料請求の方法
協議離婚での慰謝料請求
メリット
- 時間と費用を節約できる
- 互いの事情を考慮した柔軟な解決が可能
- プライバシーが守られる
デメリット
- 交渉力の差により不利な条件で合意してしまう可能性がある
- 感情的になりやすく、冷静な判断が難しい場合がある
進め方
- 慰謝料の請求理由と金額を明確にする
- 相手方と直接または弁護士を通じて交渉する
- 合意内容を「離婚協議書」として文書化する
- 公正証書にしておくと強制執行が可能
調停での慰謝料請求
メリット
- 調停委員が間に入るため冷静な話し合いができる
- 裁判より費用と時間を抑えられる
- 調停成立後の調停調書には執行力がある
デメリット
- 相手が非協力的だと調停不成立になる可能性がある
- 完全な合意がなければ決着しない
進め方
- 家庭裁判所に調停を申し立てる
- 調停期日に出席し、主張と証拠を提示する
- 調停委員の仲介で話し合いを進める
- 合意に達すれば調停調書が作成される
裁判での慰謝料請求
メリット
- 裁判所の判断で決着するため、相手の協力が不要
- 証拠に基づく客観的な判断が期待できる
デメリット
- 時間と費用がかかる
- プライバシーが守られにくい
- 感情的な満足が得られないことがある
進め方
- 弁護士に依頼して訴状を作成・提出する
- 口頭弁論で主張と証拠を提示する
- 判決が出されれば、それに基づいて慰謝料が支払われる
弁護士に依頼するメリット
専門的なアドバイス
- 慰謝料請求が可能かどうかの判断
- 適切な慰謝料額の提案
- 証拠収集の方法
- 他の離婚給付(財産分与、年金分割など)との総合的な調整
交渉力の強化
- 感情的にならない冷静な交渉
- 法的根拠に基づく説得力のある主張
- 相手方弁護士との専門的な交渉
手続きのサポート
- 離婚協議書や公正証書の作成
- 調停や裁判の申立書類の作成
- 調停や裁判での代理
- 慰謝料の回収手続き
精神的負担の軽減
- 直接交渉を回避できるため精神的ストレスが軽減
- 専門家に任せることによる安心感
- 客観的なアドバイスによる冷静な判断
まとめ
熟年離婚における慰謝料は、長年の結婚生活の中で生じた精神的苦痛に対する賠償であり、離婚後の生活を支える重要な要素の一つです。
- 慰謝料を請求するためには、不貞行為、DV、悪意の遺棄などの法律上の離婚原因が必要
- 熟年離婚特有の事情として、定年退職後の夫の言動、長年の精神的苦痛の蓄積、経済的問題、介護の問題などが考慮される
- 長期間の婚姻関係、専業主婦(主夫)の経済的自立の困難さ、住居の問題などは増額要素になりうる
- 双方に有責性がある場合や別居期間が長い場合、財産分与や年金分割で十分な経済的保障がある場合などは減額要素となる
- 慰謝料請求の方法としては、協議離婚、調停、裁判の3つがある
- 慰謝料請求には専門的な知識が必要となるため、弁護士に依頼することをお勧め
おりづる法律事務所では、熟年離婚における慰謝料請求について、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
よくある質問
Q1: 熟年離婚で「性格の不一致」を理由に慰謝料は請求できますか?
A1: 「性格の不一致」だけでは慰謝料請求は難しいですが、その背景に暴言、無視、経済的虐待などの具体的な有責行為があれば請求できる可能性があります。長年の婚姻関係の中で蓄積された精神的苦痛を具体的に主張し、証拠を示すことが重要です。
Q2: 熟年離婚で子どもは既に独立していますが、慰謝料に影響はありますか?
A2: 子どもが独立していることで、養育費の問題はなくなるものの、慰謝料自体には直接的な影響はありません。ただし、子どもの独立を機に我慢していた問題が表面化したケースでは、長年の精神的苦痛として考慮される可能性があります。
Q3: 長年の「セックスレス」を理由に慰謝料は請求できますか?
A3: セックスレスだけでは慰謝料請求は難しいですが、正当な理由なく長期間にわたって性的関係を拒否し続け、それが「悪意の遺棄」と評価できる場合は請求可能性があります。ただし、高齢や健康上の理由がある場合は難しくなります。
Q4: 熟年離婚で慰謝料を請求する場合、証拠はどのように集めればよいですか?
A4:
- DVや暴言:診断書、録音、写真、目撃者の証言
- 不貞行為:メール、LINE、写真、目撃者の証言
- 経済的虐待:通帳の記録、生活費のメモ
- 精神的苦痛:日記、カウンセリングの記録
いずれも相手のプライバシーを侵害しない範囲で行う必要があります。
Q5: 熟年離婚の慰謝料は分割払いにできますか?
A5: 当事者間で合意があれば分割払いも可能です。ただし、支払いが滞るリスクがあるため、公正証書を作成して強制執行認諾文言を入れておくことをお勧めします。分割払いの場合は利息を付けることも検討しましょう。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。












