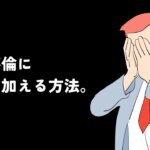執行猶予はつくのか?「同意のない接触行為」で有罪になったときの現実と可能性
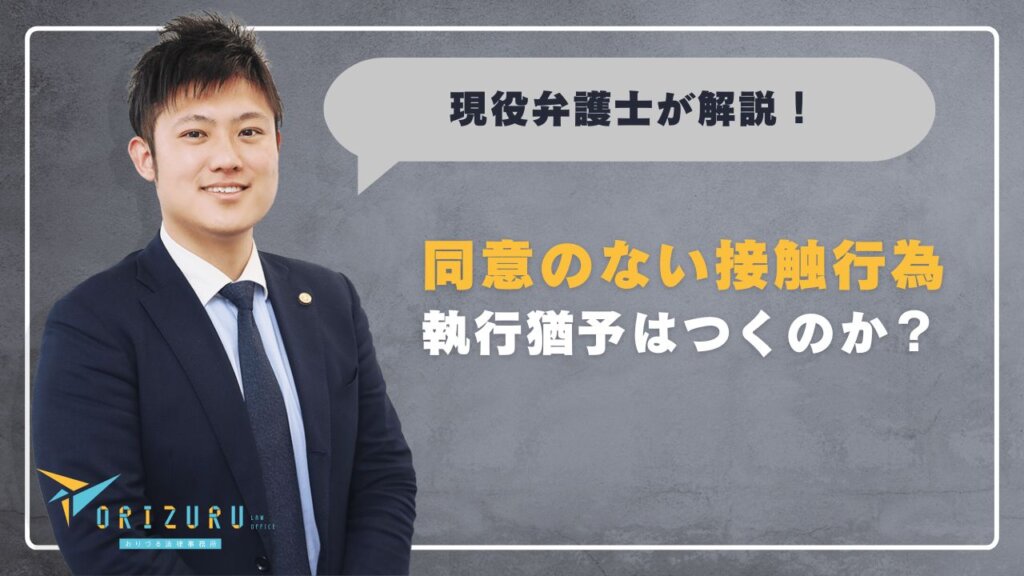
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
有罪判決を受けても、人生は終わりではない
性的な同意のない接触行為に対する社会の姿勢は年々厳しさを増し、ちょっとした気の緩みや誤解でも、刑事事件に発展するリスクが現実のものとなっています。
裁判になり、有罪となった場合でも、すべてのケースで直ちに刑務所に入らなければならないわけではありません。状況によっては「執行猶予」が付され、一定の条件のもとで社会生活を継続できる可能性もあります。
この記事では、その「執行猶予」という制度が実際にどういう場面で認められるのか、そしてそれがどのような意味を持つのかを、丁寧に解説していきます。
執行猶予とはなにか?制度の基本を押さえる
刑事裁判において、有罪が確定しても、刑の執行を一定期間保留し、その間に問題行動がなければ服役を免れる制度――それが執行猶予です。
つまり、判決としては懲役や禁錮が言い渡されても、実際には刑務所に入ることなく、社会で生活を続けることができます。ただし、この制度はあくまで「執行を一時的に猶予する」ものであり、罪がなかったことになるわけではありません。
執行猶予が認められる条件とは?
性的事件であっても、すべてが即実刑になるわけではありません。執行猶予が認められるかどうかには、いくつかの判断基準があります。
【執行猶予が付される可能性が高い条件】
- 初めての刑事事件である(前科がない)
- 犯行に計画性がなく、突発的だった
- 被害者と示談が成立し、処罰意思が示されていない
- 加害者が深く反省し、更生に向けた姿勢を示している
- 社会的制裁(退職、報道など)をすでに受けている
これらの条件を満たせば、実刑を回避し、執行猶予付きの判決が下される可能性があります。
執行猶予が付くことのメリットと制限
有罪となっても、執行猶予が付されれば、刑務所には行かずに済みます。社会生活を続けられるという点で、そのメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
ただし、自由が保証されるわけではありません。執行猶予期間中は、再び犯罪を犯せば以前の判決が直ちに執行されるというリスクを背負います。
また、以下のような制限・注意点があります。
- 前科が付くことは避けられない(前歴ではなく前科)
- 海外渡航や就労の制限が発生する場合がある
- 一部の資格や免許に影響を及ぼす可能性がある
- 公的な信用の回復には時間がかかる
つまり、執行猶予は「自由への免罪符」ではなく、「一定期間の“猶予付き監視”」とも言える制度です。
判決までの態度が結果を左右する
裁判所は、事件の内容だけでなく、加害者の人柄や態度を総合的に評価します。反省しているか、誠意をもって償っているか、社会復帰への意欲があるか――これらはすべて量刑に影響を与える重要な要素です。
裁判に臨む際には、ただ事実を並べるだけでなく、気持ちをどのように表現し、行動で示すかが極めて重要になります。そのため、本人だけで対応するのではなく、法廷での振る舞い方を含めた専門家のサポートが不可欠です。
執行猶予中に注意すべきこと
判決後、晴れて執行猶予が付いたとしても、気を緩めるのは禁物です。少しのトラブルが命取りになりかねない期間が始まります。
【執行猶予期間中に絶対に避けるべき行動】
- 交通違反や軽犯罪でも警察沙汰になるような行為
- 被害者や関係者への連絡や接触
- 飲酒トラブルや暴力的な言動
- ネット上での誹謗中傷や炎上行為への関与
「些細なこと」と思っていたことが、猶予取り消しの引き金になることもあります。執行猶予中は、社会的信用の再構築期間であると同時に、再犯を防ぐ“観察期間”でもあるのです。
執行猶予の後、その記録はどうなるのか
執行猶予期間を無事に終えれば、刑の執行は取り消されますが、有罪判決の事実は記録として残ります。これは、就職活動や資格取得、ローン審査などに影響することもあります。
とはいえ、過去を乗り越え、誠実に生き直している人を受け入れる社会の風潮も徐々に広がっています。未来をどう築くかは、その後の行動にかかっているのです。
まとめ:執行猶予は再起への猶予期間
同意のない接触行為で刑事責任を問われ、有罪となってしまっても、それがすべての終わりではありません。執行猶予がつくことで、社会の中で自分を見つめ直し、再スタートを切るチャンスが与えられます。
大切なのは、その猶予を「与えられた時間」として受け止めるか、「ラッキー」として消費してしまうかです。前者であれば、社会は少しずつあなたの歩みを見守ってくれるはずです。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。