【現役弁護士が徹底解説!】家を相続したら必ず知っておくべきこと
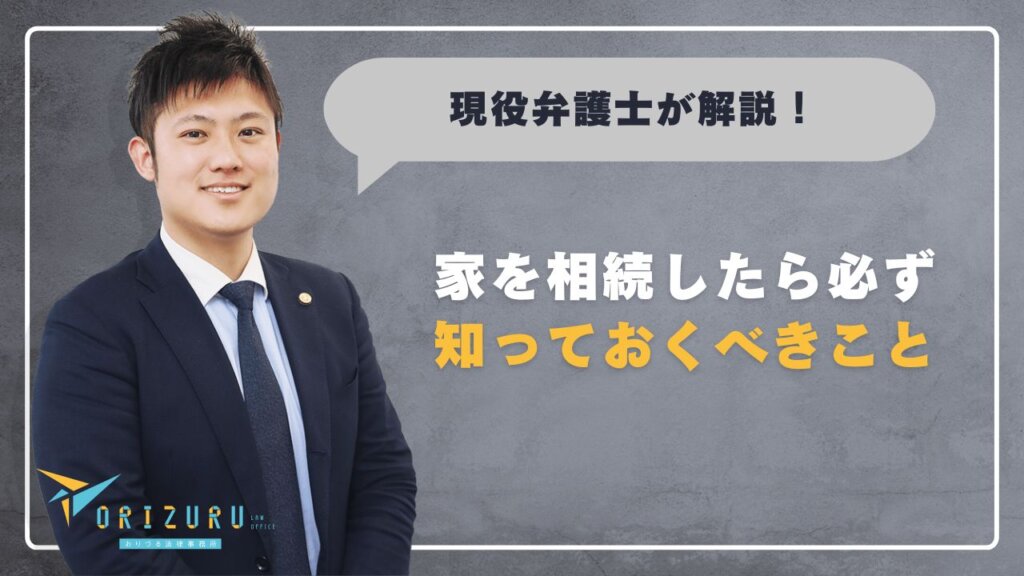
「実家を相続したはいいけれど、何をすればいいか分からない…」そんなお悩みを抱えていませんか? 家を相続すると、名義変更や税金の手続き、さらには維持管理まで、想像以上にやることがたくさんあります。加えて、相続する家が遠方にある場合や、親族の意見が対立する場合など、予期せぬトラブルも発生しがちです。
本記事では、家を相続するときに押さえておくべき基本知識を、現役弁護士の視点からわかりやすく解説します。メリット・デメリット、スムーズな手続き方法、税金の節約ワザ、さらには家族やご近所とのトラブルが起きた場合の対処法まで、重要なポイントを幅広く網羅しました。賃貸活用やリフォームなどの具体策も紹介しながら、あなたがベストな判断をするためのお役立ち情報をお届けします。ぜひ最後まで読んで、相続した家を上手に活用し、新たな生活の一歩を踏み出してください。
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
家を相続するとどうなる?
メリット:家を相続して得られる価値
実家を相続することには、経済的にも精神的にも大きな価値があります。資産価値のある不動産を取得できるだけでなく、思い出の詰まった家を守り継ぐことができるからです。
たとえば、住宅ローンを組まずに住める場所が確保できたり、賃貸収入を得られたりする可能性があります。また、子どもの頃から慣れ親しんだ環境で暮らし続けることもできます。実際に、相続した家を賃貸に出して安定した収入を得ている方や、実家をリノベーションして快適に住み続けている方も多くいらっしゃいます。
デメリット:想定される負担と課題
しかしながら、家の相続には様々な負担や責任が伴います。相続税や固定資産税などの税負担に加えて、維持管理にかかる手間やコストも考慮する必要があるためです。
具体的には、古い家屋の場合、修繕費用や光熱費、保険料などの固定費が重くのしかかることがあります。さらに、遠方に住んでいる場合は、定期的な見回りや庭の手入れなども必要になってきます。特に築年数が経過した家屋では、毎年数十万円単位のメンテナンス費用がかかるケースも少なくありません。
このように、家の相続には光と影の両面があることをご理解いただいた上で、ご自身の状況に合わせて判断していくことが大切です。
相続の進め方
所有者の名義変更
相続が始まったら、まず大切なのが相続登記です。相続を知ってから3年以内に手続きを済ませる必要があります。必要な書類は、戸籍謄本や登記簿謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などです。固定資産評価証明書も忘れずに用意しましょう。
お金の面では、司法書士に依頼すると10万円から30万円くらいかかります。手続きは少し複雑なので、専門家に相談するのがおすすめです。一人で抱え込まず、気軽に相談してみましょう。
必要な届出と手続き
名義変更が済んだら、次は生活に関する手続きです。まずは市役所や区役所で固定資産税の納税者を変更します。引っ越す予定がある場合は、住民票の手続きも忘れずに。
その後は、普段の生活に必要な電気・ガス・水道の契約名義を変更します。インターネットや火災保険の名義変更も大切です。町内会への挨拶や、公共料金の引き落とし口座の変更なども必要になってきます。
これらの手続きは早めに済ませておくと安心です。「あとでいいか」と後回しにすると、思わぬトラブルの原因になることも。一つずつ確実に進めていけば、きっと順調に手続きを終えることができますよ。
税金と賢い節約方法
相続税の仕組み
相続税は、一定額以上の財産を相続したときにかかる税金です。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に課税されます。例えば、配偶者と子ども2人の場合、4,800万円までは相続税がかかりません。
気をつけたいのは、不動産だけでなく、預貯金や生命保険金なども課税対象になること。でも、配偶者には特別な控除があり、法定相続分までなら税金がかからないんです。
税金の計算方法
相続税の計算は少し複雑です。まず、相続財産の評価額を算出します。不動産の場合、路線価や固定資産税評価額をもとに計算します。
相続税の税率は、10%から最高50%まで段階的に上がっていきます。例えば、課税対象額が1,000万円なら10%、3,000万円を超えると20%というように変わっていきます。
節税対策
賢く節税するポイントがいくつかあります。特に使える特例が「小規模宅地等の特例」です。自宅として使っている土地は、最大80%も評価額を下げられます。
他にも以下のような方法があります:
- 生前贈与を活用して、計画的に財産を移す
- 相続時精算課税制度を使う
- 配偶者の税額軽減制度を活用する
専門家に相談しながら、自分の状況に合った節税方法を見つけることが大切です。早めの準備で、かなりの節税効果が期待できますよ。
家をもらった後やるべきこと
固定資産税を納める
新しく家を相続された皆さんにとって、固定資産税は大切な支払いです。土地と建物の評価額に基づいて計算され、通常は評価額の1.4%程度となります。6月・9月・12月・翌年2月の年4回に分けて納められるため、計画的な支払いができます。
納税通知書は毎年4月頃に市区町村から届きます。口座振替にすれば自動引き落としになり、支払い忘れの心配もありません。また、一括納付では小額の割引が受けられる自治体もあるので、確認してみるとよいでしょう。
保険に入る
火災保険は、火事だけでなく、台風や水漏れなどの日常的な災害もカバーする心強い味方です。建物の構造や築年数によって保険料は変わりますが、月々数千円から数万円程度です。補償内容は保険会社によって異なるため、複数の見積もりを比較検討すると良いでしょう。
地震保険は火災保険とセットで加入できます。火災保険の保険金額の30~50%の範囲で設定でき、地震や津波による損害を補償します。保険料の半額が所得税の控除対象になるメリットもあります。
修理やリフォーム
相続した家の状態を知るため、まずは専門家による建物診断をおすすめします。屋根・外壁・基礎・配管などの重要箇所をチェックし、優先順位をつけて修繕計画を立てましょう。
水回りは特に注意が必要です。キッチンやお風呂、トイレの配管は目に見えない劣化が進んでいることも。早めの対処で大きな工事を防げます。リフォーム減税や住宅ローン控除などの制度も利用できるので、費用面での相談も専門家としっかりしましょう。
空き家にしない工夫
空き家の管理は防犯・防災の観点から重要です。月1回程度の換気や清掃、庭の手入れが基本となります。ご近所付き合いを大切にし、異変があれば連絡してもらえる関係を築くことも大切です。
賃貸活用する場合は、一般の賃貸以外にも選択肢があります。シェアハウスや民泊、高齢者向け住宅など、地域のニーズに合わせた活用方法を検討できます。不動産会社に相談して、物件の特徴を活かした運用プランを立てるのもおすすめです。
困ったときの解決方法
家族間でもめた場合
相続での家族間の意見の違いは珍しいことではありません。大切な実家の行く末について、それぞれの思いがあるのは自然なことです。
まずは家族で話し合いの場を設けましょう。オンラインでも対面でも構いません。それぞれの立場や気持ちを共有し、互いを理解することが第一歩です。
話し合いが難しい場合は、裁判所の親族間調停制度が心強い味方になります。中立な立場の調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら解決策を探ってくれます。費用も比較的抑えられ、早期解決が期待できます。
弁護士への相談も有効です。法的な観点からアドバイスをもらえ、より冷静な判断ができるようになります。
相続を断りたい場合
相続には権利だけでなく、借金なども含めたすべての責任が伴います。相続を受けることに不安を感じるのは当然のことです。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内なら可能です。手続きは家庭裁判所で行い、戸籍謄本などの書類が必要になります。一度放棄すると取り消すことはできないので、十分な検討が必要です。
放棄を考える前に、相続財産や債務の状況を確認することをおすすめします。専門家に相談することで、より良い選択ができるかもしれません。
税金の手続きミス
相続税の手続きは複雑で、誰でもミスの可能性があります。でも、気づいた時点での対応が重要です。
申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。期限を過ぎても、修正申告や更正の請求で対応できます。自主的な申し出は、税務署も好意的に受け止めてくれることが多いです。
不安な場合は、税理士に相談するのがベストです。専門家のチェックを受けることで、新たな控除や特例が見つかることも。一人で抱え込まず、気軽に相談してみましょう。
ご近所とのトラブル
古くからの住宅には、境界線や日照権など、様々な問題が潜んでいます。でも、ほとんどの場合、話し合いで解決できます。
まずは穏やかに対話することから始めましょう。些細な誤解が問題を大きくしていることも少なくありません。市区町村の無料相談窓口や法テラスでは、専門家が親身になって相談に乗ってくれます。
境界線の問題は土地家屋調査士に依頼するのが確実です。測量により客観的なデータが得られ、スムーズな解決につながります。良好な関係を保ちながら、専門家の力も借りて解決を目指しましょう。
まとめ
相続で家を引き継ぐ際の重要なポイントをまとめました。
まず、家を相続することで得られる大きなメリットは、住む場所の確保や賃貸収入の可能性です。一方で、相続税や固定資産税、維持管理費用などの負担も考慮が必要です。
相続手続きは、法定期限内の相続登記が基本となります。必要書類を整え、名義変更や各種届出を進めていきます。特に固定資産税の納税者変更や水道・電気などの契約変更は重要です。
税金面では、基礎控除額を超える財産には相続税がかかります。ただし、小規模宅地等の特例など、様々な節税対策があります。早めに専門家に相談し、適切な対策を検討しましょう。
相続後は、固定資産税の納付や保険加入、必要な修繕やリフォームなど、継続的な管理が必要です。空き家にしない工夫も大切で、賃貸活用なども検討できます。
最後に、家族間の意見対立や近隣とのトラブル、税務上の問題など、様々な課題が生じる可能性があります。そんな時は、専門家の助言を得ながら、冷静に解決策を探ることが大切です。早めの対応と周囲への配慮で、多くの問題は解決できます。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。












