【保存版】ハラスメント研修の目的とは?会社がやる意味と期待できる効果
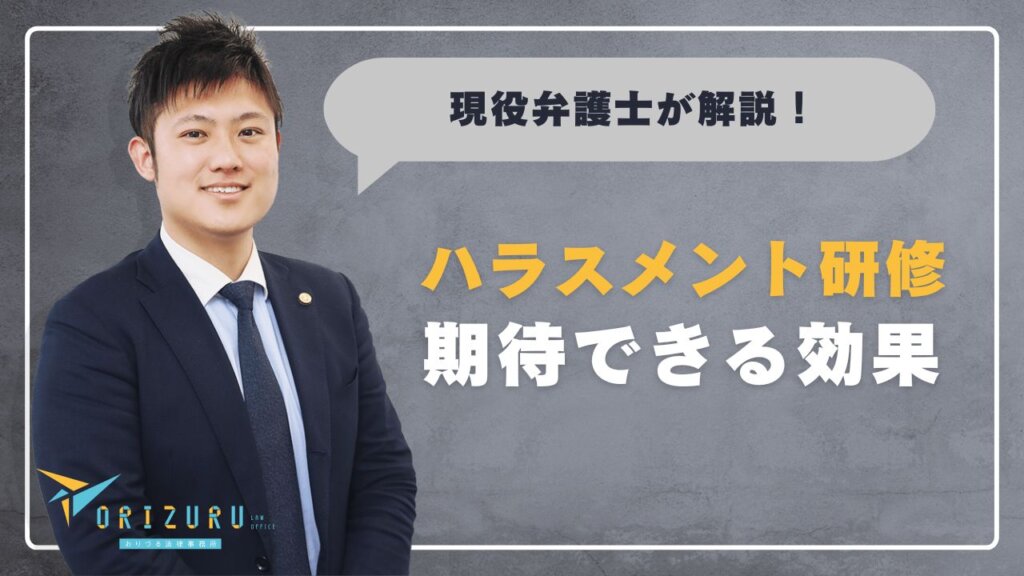
社内研修の中でも、ここ数年で存在感が急上昇しているのが「ハラスメント研修」です。ニュースやSNSでパワハラやセクハラの話題を見かけない日はなく、世の中の関心は確実に高まっています。
ただ、「目的って何?」と聞かれたときに、すぐ答えられる人は意外と少ないものです。法律のため?企業の評判を守るため?
実際には、もっと幅広くて実務的な意味が含まれています。
この記事では、現場目線も交えて、ハラスメント研修の目的や意味を整理してお伝えします。
目次 [閉じる]
研修の目的をひと言で言うと
簡単にいえば、「職場でハラスメントが起きないようにするための空気とルールづくり」です。
ハラスメントは起きてからでは遅く、被害者の心身へのダメージ、加害者の懲戒、会社の信用失墜と、すべての関係者にとって大きなマイナスになります。だからこそ、事前の予防が何より重要です。
研修は、社員一人ひとりに「どこからがアウトか」を理解してもらい、無意識のうちに誰かを傷つけるリスクを減らすための入口になるのです。
法律だけでは測れない「研修の意義」
もちろん、法律的な背景はあります。労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法などが、企業に防止策を求めています。
ですが、「やれと言われたからやる」では効果が薄くなります。
たとえば、上司と部下の距離が近すぎたり、逆に遠すぎたりする職場では、冗談や注意が誤解されやすくなります。研修はこうした社内の文化や雰囲気も踏まえて、適切な行動や伝え方を全員で共有する場でもあります。
ハラスメント研修をやる理由は大きく3つ
正しい知識を浸透させる
そもそも何がハラスメントにあたるのか、境界線があいまいなまま働いている人は少なくありません。研修を通じて共通の基準を持てば、無意識のうちにしてしまう不適切な言動を減らすことができます。
安心して働ける環境をつくる
被害に遭ったときに声を上げやすい雰囲気や、加害を許さない空気は、一朝一夕にはできません。研修はその土台づくりにあたります。
企業の信頼と持続性を守る
社内の安心感は外からの印象にも直結します。「この会社は社員を大事にしている」と思われれば、採用や取引にもプラスの効果があります。
対象によって変わる目的
研修の目的は、対象者ごとに微妙に変わります。
- 一般社員:自分の言動を振り返り、相手がどう感じるかを意識する習慣をつける
- 管理職:部下への指導が適正範囲に収まるよう判断基準を身につけ、相談対応ができるようにする
- 経営層:会社全体の風土づくりと方針決定に直結する視点を持つ
- 人事・総務:トラブル時の初動対応や証拠保全など、実務的なスキルを習得する
研修がもたらす職場への効果
目的を持って研修を実施すると、職場にはいくつかの変化が見えてきます。
社員同士の距離感が適切になり、業務中のやり取りがスムーズになる。万が一問題が起きても、早期に相談が入りやすくなり、大事になる前に対応できる。
さらに外部から見た印象も良くなり、「この会社は社員を大事にしている」という評価につながります。これは採用活動や取引にもプラスに働きます。
効果的にするための工夫
実際の事例を取り入れる
法律や定義を読むだけではピンとこない人も多いです。研修では、現場で起きそうなリアルなケースや裁判例を取り上げ、「これってどう思う?」と考えさせる場面を作ることで理解が深まります。
参加型の進め方にする
一方的な講義よりも、ディスカッションやロールプレイを入れることで、自分事として考えられるようになります。発言しやすい雰囲気づくりもポイントです。
継続的な学びにする
一度きりの研修では定着しません。短時間でも構わないので、定期的に振り返る機会をつくり、知識と意識を更新していくことが大切です。
研修料金・お問い合わせ

ハラスメント研修は「知識を伝えるだけのセミナー」では意味がありません。
当事務所では、労務問題に精通した弁護士が直接登壇し、最新の法律・裁判例や実際のトラブル事例を交えながら、会社の現場に即した研修を行います。
基本料金:1回(90分) 77,000円(税込)+交通費
追加料金:1コマ増えるごとに 33,000円(税込)
「弁護士がやるからこそ安心できる研修」をぜひご体感ください。
法律的な知識だけでなく、「これをやったらパワハラになるのか?」という実務的な線引きや、相談を受けたときの具体的な対応方法まで踏み込んで解説します。
「管理職にしっかり意識づけをしたい」
「相談窓口を設けたけど、うまく機能していない」
「裁判になったら…と考えると不安」
そんな企業様にこそおすすめです。
まずはお気軽にお問い合わせください。
御社の現状をヒアリングし、最適な研修プランをご提案いたします。
まとめ
ハラスメント研修の目的は、法律を守ること以上に、会社の未来と社員の働きやすさを守ることにあります。
「目的を理解し、対象ごとに最適な内容を届ける」ことで、研修は単なる義務ではなく、職場をより良くするための実践的な仕組みに変わります。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。












