外部委託によるパワハラ相談窓口の導入で変わる職場環境
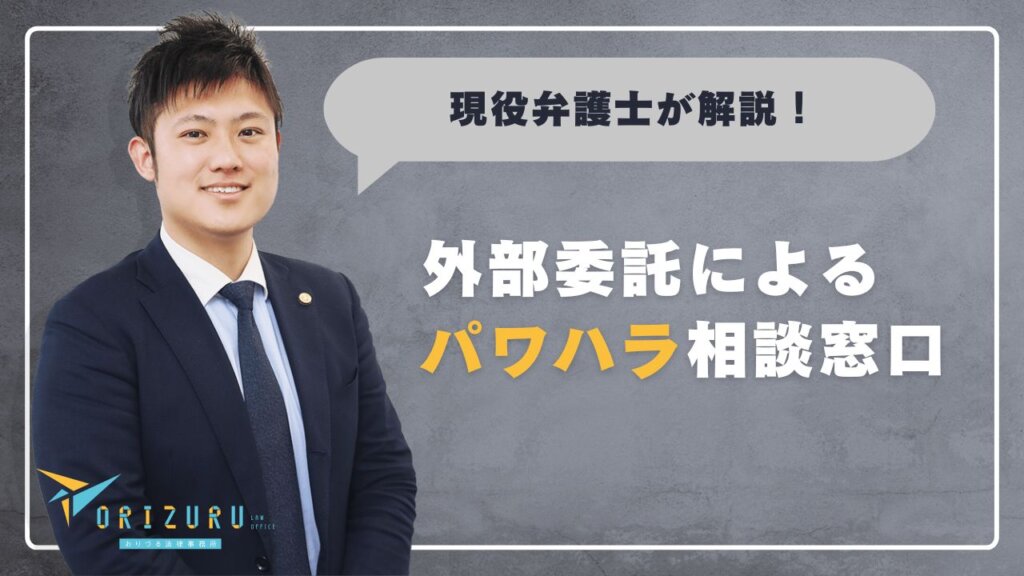
かつては職場での叱責や強い指導が「当たり前」とされていた時代もありました。しかし、社会全体の意識が変化し、働く人の尊厳や心理的安全性を守ることが企業の義務として明確になった今、パワハラは単なる「職場の問題」ではなく、企業の存続にも関わる重大なリスクとなっています。
特に2020年のパワハラ防止法施行(中小企業は2022年4月から適用)により、相談窓口の設置は法的にも必須となりました。これは単なる制度対応ではなく、職場の安心感や人材定着率を左右する大きな要素です。
目次 [閉じる]
社内相談窓口だけでは対応しきれない現実
「うちは人事部が窓口だから大丈夫」と考える企業もありますが、実際に機能していないケースは少なくありません。背景にはいくつかの課題があります。
社内の人間関係が壁になる
社内窓口は同じ会社の人間が対応するため、どうしても相談内容が知られてしまうのではないかという不安が残ります。とくに上司や同僚との関係が悪化するリスクを考え、相談そのものを諦めてしまう社員も少なくありません。
専門知識や経験不足の問題
人事担当者が必ずしもハラスメント対応のプロであるとは限りません。法律的な知識や、心理的なケアに関する経験が不足している場合、相談者が納得できる助言や解決策が提示できないことがあります。
二次被害の危険性
相談内容の扱いを誤ると、加害者への情報伝達や不適切な対応によって、相談者がさらに不利益を被る可能性があります。これは相談文化そのものを損ない、職場全体の信頼を失わせる原因になります。
外部委託のパワハラ相談窓口が注目される理由
こうした課題を背景に、社外の第三者機関に相談窓口業務を委託する企業が増えています。外部委託が選ばれる理由には、以下のようなポイントがあります。
- 中立性の確保
外部機関は企業と一定の距離を保ちながら相談に応じるため、相談者は安心して本音を話すことができます。社内の利害関係や評価への影響を気にせず話せるという点は、心理的ハードルを大きく下げます。 - 専門性の高さ
ハラスメント対応に精通した専門スタッフが、法的観点や心理的ケアの視点から助言します。これにより、相談の質が向上し、企業側も的確な改善策を得られます。 - 企業の負担軽減
相談受付、記録、一次対応といった手間を外部に任せることで、人事や総務部門は本来の業務に集中できます。また、ケースによっては外部委託先が弁護士やカウンセラーと連携してくれるため、企業側の対応がスムーズになります。
外部委託のパワハラ相談窓口がもたらす主なメリット
従業員が声を上げやすくなる環境づくり
外部の相談窓口は「話しても安全」という感覚を社員に与えます。たとえ小さな違和感や不満であっても、早期に相談されることで大きなトラブルに発展する前に対応できます。結果的に、職場全体の空気が柔らかくなり、安心感が高まります。
迅速かつ正確な初期対応
外部委託先は、事案の性質や緊急度を迅速に見極め、必要に応じて即時対応のアドバイスや社内への報告を行います。このスピード感は、事態の悪化を防ぐうえで極めて重要です。
根本的な改善策へのつなぎ
相談内容を分析し、職場の構造的な課題や人間関係のパターンを把握したうえで、再発防止のための研修や制度改善の提案まで行えるのは、専門性を持った外部委託先ならではの強みです。
委託先を選ぶ際に押さえておくべきポイント
実績と専門性
委託先が過去にどのような業種・規模の企業で相談窓口を運営してきたかは重要です。例えば製造業では現場での指示系統が問題になるケースが多く、IT業界ではリモートワーク下でのコミュニケーション不全が目立つなど、業界によって事情が異なります。自社と似た事例を扱った経験があれば、より的確な対応が期待できます。
対応範囲と柔軟性
電話・メール・オンライン面談など、多様な相談手段が用意されているかを確認しましょう。相談者によって話しやすい媒体は異なり、選択肢の多さが相談件数や満足度に直結します。
法的・心理的サポート体制
単なる窓口業務だけでなく、労働法に詳しいスタッフや、カウンセリング経験のある担当者が在籍しているかは非常に重要です。法的視点と心理的ケアが両立してこそ、安心感と信頼性が生まれます。
報告・フィードバックの仕組み
相談内容は企業に適切にフィードバックされなければ改善につながりません。個人が特定されない形で要点をまとめ、定期的に報告してくれる体制があるかを確認しましょう。
導入から運用までの流れと社内浸透のコツ
- 委託先の選定と契約
企業の規模や業種、相談の傾向に合う委託先を選び、業務範囲や費用、報告方法などを明確にします。 - 社内への周知
窓口の存在や利用方法を全社員に周知することが不可欠です。社内掲示やメール配信、説明会など複数の手段を使い、「誰が・どうやって」相談できるかを具体的に伝えます。 - 相談受付と初期対応
外部窓口が相談を受け、必要に応じて企業の担当部署に報告します。この段階で迅速な対応ができるかが、信頼構築のカギです。 - 定期的な報告と改善
半年や1年ごとに相談状況を分析し、課題や改善点を共有します。この情報をもとに研修や制度の見直しを行うことで、継続的な改善が可能になります。
運用時に注意すべき落とし穴
- 設置しただけで周知不足
せっかく外部窓口を導入しても、社員が存在を知らなければ意味がありません。定期的な周知と利用促進の工夫が必要です。 - 報告を軽視する
外部からの報告内容を「大げさだ」と受け流すと、相談者は再び沈黙します。報告は真摯に受け止め、必ず何らかの対応を行うべきです。 - 社内対応との連携不足
外部窓口だけでは解決できない事案もあるため、社内の責任者や人事との連携体制を事前に整えておくことが欠かせません。
中小企業こそ外部委託を活用すべき理由
中小企業では、人事部門が少人数で兼務しているケースが多く、専門人材を社内に置くのは現実的ではありません。外部委託なら、比較的低コストで高い専門性と中立性を確保できます。
また、パワハラ防止法は中小企業にも適用されているため、法令遵守の面からも外部委託は現実的な選択肢です。
研修料金・お問い合わせ

ハラスメント研修は「知識を伝えるだけのセミナー」では意味がありません。
当事務所では、労務問題に精通した弁護士が直接登壇し、最新の法律・裁判例や実際のトラブル事例を交えながら、会社の現場に即した研修を行います。
基本料金:1回(90分) 77,000円(税込)+交通費
追加料金:1コマ増えるごとに 33,000円(税込)
「弁護士がやるからこそ安心できる研修」をぜひご体感ください。
法律的な知識だけでなく、「これをやったらパワハラになるのか?」という実務的な線引きや、相談を受けたときの具体的な対応方法まで踏み込んで解説します。
「管理職にしっかり意識づけをしたい」
「相談窓口を設けたけど、うまく機能していない」
「裁判になったら…と考えると不安」
そんな企業様にこそおすすめです。
まずはお気軽にお問い合わせください。
御社の現状をヒアリングし、最適な研修プランをご提案いたします。
まとめ
外部委託型のパワハラ相談窓口は、単なる制度対応ではなく、企業の信頼性や従業員の安心感を守る重要な仕組みです。中立性と専門性を兼ね備えた窓口は、問題を早期に発見し、再発防止につなげる力を持っています。
大切なのは、導入して終わりではなく、社員が安心して利用できる環境づくりと、相談後の迅速かつ適切な対応です。この積み重ねこそが、健全で信頼される職場文化を築く第一歩になります。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。












