不起訴という希望はあるのか?「同意なき接触」で疑われたときの対応とその後
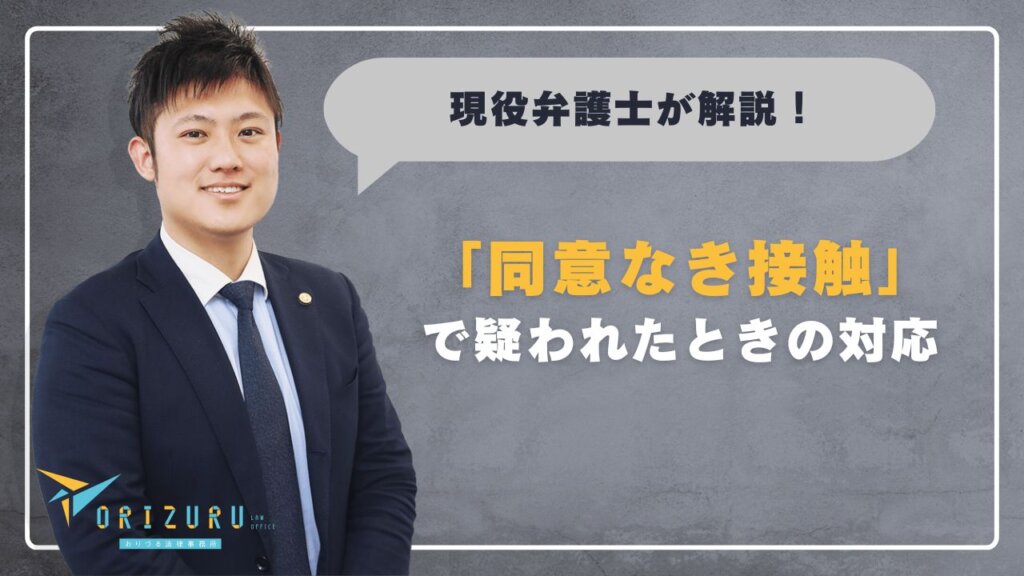
一人で悩んでいませんか?
弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてきます。
- ✓ 初回相談無料
- ✓ 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
- ✓ 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。

目次 [閉じる]
無実か過失かにかかわらず、不安は突然やってくる
ある日突然、警察からの連絡で日常が一変する。「事情を伺いたい」「任意でお越しください」──その言葉の重みは、想像以上です。
性的同意がない状態での接触行為が社会的に厳しく問われる中、「自分はそんなつもりじゃなかった」と思っても、相手の認識が異なれば、法的な問題へと発展する可能性があります。
そうした状況下で多くの人が気にするのが、「不起訴にならないだろうか」という望みです。起訴されれば、前科がつく。人生において重大な転機になる。だからこそ、「起訴されるかどうか」は事件そのもの以上に重たい意味を持ちます。
起訴と不起訴の違いとは?
刑事事件では、警察の捜査を経て検察が判断を下します。ここで検察官が「起訴する」と判断すれば、裁判へと進みます。逆に、「起訴しない(不起訴)」と判断されれば、その時点で刑事手続きは終了します。
つまり、不起訴とは「無罪判決を受けた」という意味ではありませんが、「裁判にすらならなかった」という点で、社会的・精神的なダメージを大きく回避できる選択肢なのです。
不起訴となるパターンはいくつかある
不起訴の理由にはさまざまな種類があります。単に証拠が不十分というだけでなく、加害者の事情や被害者の意向など、複合的な要素が考慮されます。
【不起訴が決定される主な理由】
- 証拠が足りず、立証が困難な場合
- 被害者が処罰を望んでいない(宥恕)
- 示談が成立し、社会的制裁も受けている
- 加害者に強い反省と更生の兆しがある
- 事件の悪質性が低いと判断されたとき
これらのいずれか、または複数が重なったときに、検察は「裁判にする必要はない」と判断することがあります。
不起訴になるために重要な視点とは?
不起訴を目指すためにできることは、限られているようでいて、実は非常に多くあります。とくに逮捕後すぐの段階から、行動のひとつひとつが結果に影響します。
- 捜査には誠実に協力する姿勢を見せる
- 認識の相違があったとしても感情的にならず、丁寧に説明する
- 自分の主張に固執せず、相手の感情や立場を理解しようと努める
- 早期に専門家と連携し、示談交渉や法的対応を整える
これらの点を意識することで、検察の心証にも良い影響を与えやすくなります。
示談の有無と不起訴との関係
加害者とされる側からすると、示談が成立するかどうかは、不起訴を勝ち取る上で非常に重要なポイントとなります。
しかし、「示談さえできれば不起訴になる」という短絡的なものではありません。そこには、被害者の納得、謝罪の真意、再発防止の姿勢など、示談の“質”が問われる側面があります。
逆に言えば、金銭のやり取りだけで済まそうとすれば、検察や裁判所にかえって「反省していない」と受け取られるリスクもあります。
不起訴になったからといって油断できないこと
不起訴は「刑事責任が問われないこと」を意味しますが、社会的な目まで消えるわけではありません。事件として名前が出ていれば、ネットに半永久的に残る可能性もありますし、関係者の記憶には残り続けるでしょう。
また、不起訴になったからといって、会社や学校がそれを理由に処分を行わないとは限りません。あくまで「法的には終わった」というだけで、信頼回復や人間関係の修復には時間が必要です。
法的サポートがもたらす大きな差
不起訴を目指すうえで、最も頼りになるのは法律の専門家の存在です。経験のある支援者がいれば、どのようなアプローチを取るべきか、証拠の扱いや供述の組み立て方、検察への働きかけ方まで、状況に応じて適切な戦略を立てられます。
弁護士の存在によって、次のような利点が生まれます。
- 被害者との間に感情のクッションが生まれる
- 証拠の不備や誤解を丁寧に解消できる
- 法的に整った示談書を用意できる
- 検察に対して説得力ある意見書を提出できる
適切な支援を得ることが、「不起訴」という未来へのルートを現実に引き寄せる鍵になります。
まとめ:起訴されないという選択肢を本気で掴むには
疑いをかけられた瞬間から、すべてが終わるわけではありません。最終的に起訴されるのか、それとも不起訴で済むのかは、対応と準備次第です。
不起訴になる可能性を少しでも高めたいと思うのであれば、焦らず、誠実に、そして正しい知識をもって一歩ずつ対応していくことが何よりも重要です。
この問題は「その場しのぎ」では乗り越えられません。自分の人生を守るという強い意志をもって、信頼できる支援者とともに正面から向き合ってください。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。












