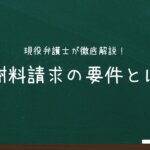少年審判の「処分」とは? その種類と意味、お子さんの未来への影響を徹底解説
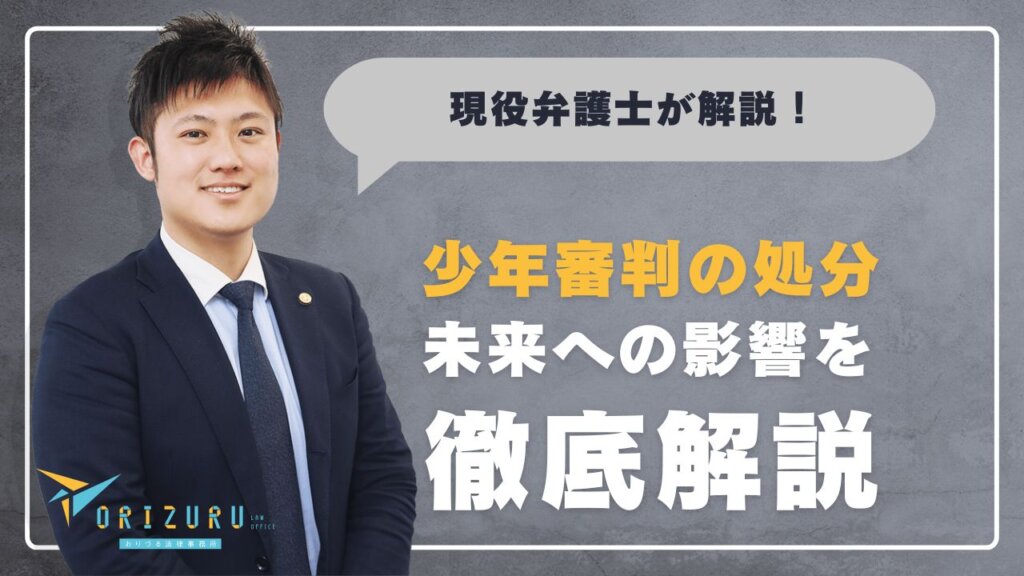
もし、あなたのお子さんが何らかの事件に関わってしまい、少年審判に臨むことになったとしたら、ご家族は計り知れない不安の中にいることでしょう。その中でも、「最終的にどのような処分が下されるのだろうか?」「その処分は、うちの子の将来にどう影響するのだろうか?」という疑問は、最も気がかりなことかもしれません。
少年審判は、大人を対象とする刑事裁判とは異なり、「刑罰」ではなく「保護処分」と呼ばれる特別な処分が下されます。この違いを理解することは、お子さんの未来を考える上で非常に重要です。
しかし、少年事件の手続きは複雑であり、それぞれの処分が具体的に何を意味し、どのような影響をお子さんの生活や将来に与えるのか、詳しく知る機会は少ないかもしれません。
この記事では、少年審判で下される様々な「処分」について、その種類と内容、目的、そしてお子さんやご家族の生活に与える具体的な影響を、一つ一つ丁寧に解説していきます。お子さんの更生を願い、最善の選択をするために、この情報が少しでもお役に立てれば幸いです。
目次 [閉じる]
少年事件と「処分」の基本的な考え方 – 大人とは異なる少年法の理念
まず、少年事件が大人を対象とする刑事事件と根本的に異なる点を理解することが重要です。この違いが、「処分」という独特の考え方を生み出しています。
少年法の「保護主義」とは何か
少年法において「少年」とは、20歳に満たない者を指します。少年法が目指すのは、罪を犯した少年を「罰すること」ではなく、**「健全な育成を目的として保護・教育すること」**です。これを「保護主義」と呼びます。
この保護主義の理念に基づき、少年事件の手続きは以下のような特徴を持っています。
- 「刑罰」ではなく「処分」:大人の刑事裁判では懲役や罰金といった「刑罰」が科せられますが、少年審判では「保護処分」と呼ばれる措置が取られます。これは、少年の特性や再非行の可能性を考慮し、その更生を促すための教育的・指導的な意味合いが強いものです。
- 非公開主義:少年審判は原則として非公開で行われます。これは、少年のプライバシーを保護し、社会的な烙印が押されることで更生が妨げられることを防ぐためです。
- 家庭裁判所の専属管轄:少年事件は、原則としてすべて家庭裁判所が担当します。少年自身が罪を認めるか否かにかかわらず、家庭裁判所が事件の背景や少年の状況を総合的に判断し、適切な処分を決定します。
この理念を理解することは、お子さんが「犯罪者」として扱われるのではなく、「保護すべき少年」として、その未来をどうしていくかを真剣に検討する場なのだと認識することに繋がります。
「処分」に至るまでの基本的な流れ
家庭裁判所が処分を決定するまでの流れは、一般的に以下のようになります。
- 事件発生・捜査:警察が事件を認知し、捜査を開始します。少年が逮捕・補導されることもあります。
- 送致(そうち):捜査が終わると、事件はすべて家庭裁判所に送致されます。これは、大人事件のように検察官が起訴・不起訴を判断するのではなく、家庭裁判所が処遇を判断する主体となるためです。
- 家庭裁判所調査官による調査:家庭裁判所に送致された事件は、まず家庭裁判所調査官(調査官)による詳細な調査が行われます。調査官は、少年の生育環境、性格、交友関係、事件の背景、反省の度合いなどを多角的に調査し、少年の現状と更生に必要な処遇についての意見書を作成します。この調査は、少年の処分を決定する上で極めて重要な要素となります。
- 観護措置(かんごそち):調査の結果、必要と判断された場合、少年は少年鑑別所に一時的に収容されることがあります。これを「観護措置」と呼びます。原則として2週間ですが、延長されることもあります。鑑別所では、専門家による行動観察や心理テストなどが行われます。
- 少年審判:調査や観護措置を経て、家庭裁判所が最終的な処分を決定する場が「少年審判」です。非公開で行われ、裁判官、調査官、少年、そして弁護士(付添人)が同席します。少年本人や保護者の意見も聞かれます。
そして、この少年審判を経て、裁判官が少年の「処分」を決定します。
少年審判で下される「処分」の種類と具体的な内容
少年審判で下される処分は、大きく分けていくつかの種類があります。それぞれの処分が持つ意味合いと、お子さんの生活に与える影響を詳しく見ていきましょう。
不処分 – 「処分しない」という決定
「不処分」とは、家庭裁判所が保護処分を科さないと決定することです。これは、少年審判で最も有利な処分と言えます。
- 不処分となるケース:
- 非行事実が認められない場合:事件の事実関係が認定できない場合。
- 非行性が認められない場合:事件はあったものの、その原因が少年の性格や環境に起因するものではなく、再非行の可能性が低いと判断された場合。
- すでに更生が進んでいる場合:事件後、少年が深く反省し、被害者への謝罪や償いを済ませ、家族のサポート体制も整っており、すでに十分な更生が進んでいると判断された場合。この場合、あえて保護処分を科す必要がないと判断されます。
- 事件が極めて軽微な場合:非行の内容が非常に軽微で、保護処分を科すまでもないと判断された場合。
- 不処分の意味合い: 不処分は、少年院送致や保護観察といった保護処分とは異なり、家庭裁判所による直接的な指導・監督を受けないことを意味します。これにより、少年は社会生活を中断することなく、通常の生活を続けることができます。しかし、だからといって「無罪放免」というわけではありません。少年が自らの過ちを認識し、再非行防止に向けて努力を続けることが求められます。
保護観察 – 社会の中で更生を目指す処分
「保護観察」とは、少年が社会の中で生活しながら、保護観察官や保護司の指導・監督を受ける処分です。少年審判で最も多く選択される処分の一つです。
- 保護観察の内容:
- 保護観察官・保護司との面談:少年は、定期的に保護観察官(国の職員)や保護司(地域のボランティア)と面談し、生活状況や課題について報告します。
- 遵守事項:保護観察期間中は、少年が守るべきルール(遵守事項)が定められます。例えば、犯罪行為をしない、健全な生活を送る、被害者との接触を避ける、特定の場所へ立ち入らない、外出の許可を得るなど、個々の少年の状況に応じて具体的な指示が出されます。
- 指導・助言:保護観察官や保護司は、少年の学習、就職、交友関係などについて指導・助言を行い、少年の更生を支援します。
- 期間:保護観察の期間は、少年の更生状況によって異なり、通常は数ヶ月から数年程度です。改善が見られれば早期に解除されることもありますが、遵守事項違反があった場合は、少年院送致などの重い処分に変更される可能性もあります。
- 保護観察のメリット・デメリット:
- メリット:社会生活を中断することなく、学校や職場に通いながら更生を目指せる点です。家族や友人との関係を維持しながら、地域社会の中で更生の機会を得られます。
- デメリット:定期的な面談や遵守事項があり、生活に一定の制約が加わります。遵守事項違反があった場合、より重い処分に変更されるリスクがあります。
少年院送致 – 施設に収容され矯正教育を受ける処分
「少年院送致」とは、少年が少年院に収容され、矯正教育を受ける処分です。これは、少年審判で下される保護処分の中でも、比較的重い処分と言えます。
- 少年院送致となるケース:
- 非行内容が比較的重く、かつ再非行の可能性が高いと判断された場合。
- 少年の家庭環境が改善されず、社会内での更生が困難であると判断された場合。
- 保護観察処分では改善が見込めないと判断された場合など。
- 少年院の目的と内容: 少年院は、刑務所とは異なり、少年の心身を健全に育成し、社会に復帰させることを目的とした教育施設です。
- 矯正教育:学習指導(義務教育の修了や高校卒業資格の取得支援)、職業指導(各種資格の取得支援)、生活指導、体育指導など、少年の特性に応じた多様なプログラムが提供されます。
- 期間:少年院の収容期間は、原則として少年が20歳になるまでですが、個々の少年の更生状況によって異なり、通常は数ヶ月から数年程度です。最長で20歳まで収容されます。
- 面会・通信:家族との面会や手紙のやり取りは可能ですが、一定の制限があります。
- 少年院送致のメリット・デメリット:
- メリット:少年の問題行動の原因となっている環境から一時的に離れ、専門的な矯正教育を受けることで、集中的に更生に取り組める点です。規律ある生活を送ることで、生活習慣が改善されることも期待できます。
- デメリット:学校や職場を休学・休職せざるを得ず、社会生活が中断されます。長期的な収容は、社会復帰後の適応に一定の困難を伴う可能性もあります。
検察官送致(逆送) – 大人と同じ刑事裁判へ
「検察官送致(逆送)」とは、少年が大人と同じ刑事裁判を受けることになる処分です。少年法で定められた特別なケースでのみ行われる、最も重い決定と言えます。
- 逆送となるケース:
- 対象年齢:原則として、16歳以上の少年が対象となります。
- 重大な犯罪:殺人、強盗致傷、強制性交等(性犯罪)など、死刑、無期または短期1年以上の懲役・禁錮にあたるような重大な犯罪を犯し、かつ、その犯罪の情状や少年の性格、行為の傾向などから見て、刑事処分が相当であると家庭裁判所が判断した場合に逆送されます。
- 特定少年への特則:2022年4月の少年法改正により、18歳・19歳の少年は「特定少年」として扱われ、原則として逆送の対象が拡大されました。特定少年が犯した死刑、無期または短期1年以上の懲役・禁固にあたる罪については、原則逆送となります。
- 逆送の意味合いと影響: 逆送となれば、少年は検察官によって起訴され、地方裁判所などで大人と同じ刑事裁判を受けることになります。
- 公開の裁判:少年審判と異なり、刑事裁判は原則として公開で行われます。少年の氏名や事件の内容が報道される可能性もあります。
- 「刑罰」の可能性:有罪となれば、懲役や罰金といった「刑罰」が科せられます。実刑判決の場合、少年刑務所ではなく、刑務所に収容されることもあります。
- 前科:刑事裁判で有罪判決を受ければ、「前科」がつきます。これは、その後の就職、資格取得、海外渡航など、人生のあらゆる面で大きな制約となり、一生涯にわたって影響を及ぼします。
逆送は、少年の更生を目的とする少年法の理念から逸脱する例外的な措置であり、少年の未来に最も大きな影響を与える処分と言えます。
「処分」が少年と家族の未来に与える具体的な影響
少年審判で下される処分は、少年本人の生活だけでなく、ご家族の生活、そして少年の長期的な未来にまで、様々な形で影響を及ぼします。
学校生活・学業への影響
- 不処分・保護観察: 学校に通い続けることは可能ですが、事件の内容によっては、学校側からの指導や、クラスメイトからの偏見に直面する可能性があります。保護観察期間中は、学校との連携も必要となることがあります。
- 少年院送致: 原則として学校を休学・退学することになります。少年院内で学習指導を受けることはできますが、卒業時期が遅れる、あるいは高校卒業資格の取得が困難になる可能性があります。
- 逆送: 刑事裁判で有罪となり、実刑判決を受ければ、学校を中退することになります。少年院よりも長い期間社会から隔離される可能性もあり、学業への復帰はさらに困難になるでしょう。
就職・キャリアへの影響
- 不処分・保護観察: 直接的な「前科」はつきませんが、事件の事実自体が就職活動に影響を与える可能性はあります。特に、公務員や一部の資格職では、採用時に過去の経歴を問われることがあります。保護観察中の場合は、保護観察官や保護司の指導・助言を受けながら就職活動を進めることになります。
- 少年院送致: 少年院を退院した後も、就職活動において少年院での経験が不利に働く可能性があります。しかし、少年院での職業訓練や、退院後の就労支援を活用することで、就職の道は開かれます。
- 逆送: 刑事裁判で有罪判決を受ければ「前科」がつきます。これは、就職活動において極めて不利な要素となります。特に、大企業や安定した職種への就職は非常に困難になり、職業選択の幅が大きく狭まる可能性があります。
家族関係・社会生活への影響
- 共通する影響: どの処分になったとしても、事件が起きたことで家族関係に緊張が生じたり、地域社会や友人関係の中で偏見や誤解に直面したりする可能性があります。ご家族も精神的なサポートが必要となることがあります。
- 保護観察: 家族は、少年が遵守事項を守り、更生できるように積極的に協力する必要があります。保護観察官や保護司との連携も求められます。
- 少年院送致: 少年が少年院にいる間、家族は定期的な面会や手紙のやり取りを通じて少年との繋がりを保つことが重要です。退院後の少年の生活を支える準備も必要となります。
- 逆送: 少年の氏名や事件が報道される可能性があり、家族も社会的な非難や偏見にさらされるリスクが高まります。また、少年が刑務所に収容された場合、家族関係の維持もより困難になることがあります。
戸籍・住民票などへの影響
少年審判の処分は、戸籍や住民票に記載されることはありません。これは、少年法の保護主義の理念に基づき、少年の社会復帰を妨げないための配慮です。
ただし、逆送され、刑事裁判で有罪判決を受ければ「前科」がつき、これは刑事記録として残ります。戸籍や住民票に直接記載されるわけではありませんが、公的な身分証明書や履歴書には記載されずとも、特定の職業(公務員、教員、弁護士など)に就く際には、採用条件として犯罪歴の有無が問われることがあります。
適切な「処分」を得るために家族ができること – 弁護士の重要性
少年審判で最も望ましい処分(不処分や保護観察)を獲得するためには、少年自身の反省と努力はもちろん、ご家族の協力と、そして弁護士(付添人)の専門的なサポートが不可欠です。
弁護士(付添人)が「処分」に与える影響
少年審判において、弁護士(付添人)は、単に少年の権利を守るだけでなく、少年の更生を「付添い」、最も適切な処分を得るために、以下のような重要な役割を果たします。
- 早期の介入による不利益の回避: 少年が警察に逮捕された直後から弁護士が介入すれば、取り調べに関する適切なアドバイスを与え、不適切な供述を防ぐことができます。これにより、少年に不利な事実認定がされることを避け、後の処分判断に良い影響を与えます。
- 家庭裁判所調査官への働きかけ: 調査官は処分の意見書を作成しますが、弁護士は少年や家族から詳しく話を聞き、少年の真の姿、反省の状況、再非行防止に向けた具体的な努力(例:被害者への謝罪、学習意欲、家族のサポート体制など)を調査官に正確に伝え、少年に有利な調査報告書作成に繋がるよう働きかけます。
- 被害者との示談交渉: 被害者との示談が成立しているかどうかは、少年の処分に大きく影響します。弁護士は、被害者の心情に配慮しつつ、示談交渉を代理します。誠意ある謝罪と被害弁償を行うことで、少年の反省の姿勢を示し、被害者からの理解を得ることができれば、少年に有利な処分に繋がる可能性が高まります。示談が成立すれば、不処分や保護観察となる可能性が格段に高まります。
- 環境調整活動の実施とアピール: 弁護士は、少年の非行の背景にある環境問題を特定し、家族と協力して家庭環境の改善、学校との連携、適切な交友関係の形成など、少年の健全な育成に資する環境調整活動を具体的に提案し、その努力を家庭裁判所に積極的にアピールします。これにより、社会内での更生が可能であると判断されやすくなります。
- 少年の反省・更生状況の客観的な証明: 弁護士は、少年が事件後、どのように反省し、具体的に更生に向けて努力しているかを家庭裁判所に積極的にアピールします。反省文、日記、ボランティア活動への参加、学校での努力など、客観的な証拠を提出し、少年の真摯な更生への意欲を伝えます。
- 重い処分(逆送・少年院送致)の回避に向けた弁護: 特に、少年が16歳以上で重大な事件を起こした場合の「逆送」や、少年院送致を回避するために、弁護士は少年の更生の可能性を最大限に主張します。少年法の保護主義の理念に基づき、少年の将来を奪わないための最も適切な処分が何かを、専門的な立場から説得力を持って訴えます。
家族が弁護士と連携してできること
弁護士を付添人として選任したら、ご家族は弁護士と密に連携を取り、お子さんの更生に向けた具体的な計画を立て、実行していくことが重要です。
- 弁護士への情報提供: 弁護士が状況を正確に把握できるよう、ご家族が知っている事件の事実関係、少年の生育環境や特性(性格、過去の行動、家族関係、学校での様子、友人関係、非行の背景など)をすべて正直に伝えましょう。どんな些細な情報でも弁護士にとっては重要な判断材料となります。
- 環境調整への積極的な協力: 弁護士から提案される、家庭環境の改善策(例:家族の協力体制の強化、生活習慣の見直し、ルール作りなど)、少年の生活習慣の見直し、新たな居場所作りなど、具体的な環境調整活動に積極的に協力しましょう。ご家族の協力は、少年の更生に対する家庭裁判所の評価にも繋がります。
- 少年の反省と更生努力のサポート: お子さんが反省文を書く、被害者への謝罪の気持ちを伝えるための準備をする、ボランティア活動に参加する、学習意欲を高めるなど、更生に向けた具体的な努力をサポートしましょう。その努力の過程や成果を、弁護士を通じて家庭裁判所に伝えることが重要です。
- 精神的なサポートも忘れずに: ご家族自身も、お子さんの事件によって大きなストレスを抱えることがあります。必要であれば、ご家族自身もカウンセリングを受けるなど、精神的なサポートを検討してください。ご家族が心身ともに健康であることが、お子さんを支える上で不可欠です。
少年事件の「終わり」は、新たな「始まり」
少年審判の処分が決定しても、それが少年の事件の終わりではありません。特に、保護観察や少年院送致の処分が下された場合は、そこからが少年の本当の更生に向けた「始まり」となります。
- 保護観察処分の場合: 保護観察官や保護司の指導・監督を真摯に受け、定期的な面談や指示に従う必要があります。ご家族も協力し、少年の社会内での生活を支援していくことになります。定められた遵守事項を破ると、より重い処分に変更される可能性があることを理解し、注意深く生活することが求められます。
- 少年院送致処分の場合: 少年院に送致された場合は、少年院での矯正教育に真剣に取り組むことが求められます。ご家族は、面会などを通じて少年との関係を維持し、退院後の社会復帰に向けた準備(住居、就職先、学校など)を協力して行うことになります。退院後の社会復帰支援も重要です。
弁護士は、処分が決定した後も、必要に応じて少年の更生をサポートする役割を担うことがあります。少年審判の期間だけでなく、その後も弁護士との繋がりを保つことで、少年の再非行防止に向けた道筋をより確かなものにできるでしょう。
まとめ:お子さんの未来のために、適切な「処分」の理解と行動を
お子さんが直面している「処分」は、大人にとっての「刑罰」とは異なり、その目的はあくまで少年の「保護と教育」にあります。しかし、だからといって、その影響が軽微であるわけではありません。
それぞれの処分が持つ意味合い、お子さんの生活や将来に与える影響は大きく異なります。特に、少年院送致や逆送といった重い処分は、お子さんの社会生活を大きく制約し、その未来に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
このような状況において、少年法や少年審判手続きに精通し、お子さんの権利を守り、更生に向けた最適な道筋を示すことができるのは、**少年事件に特化した弁護士(付添人)**の他にはありません。弁護士は、少年の精神的負担を軽減し、家庭裁判所調査官や裁判官に少年の真の姿や反省の状況を正確に伝え、被害者との示談交渉を通じて、お子さんにとって最も望ましい処分(不処分や保護観察)を獲得するために、全力で活動します。
お子さんの未来は、今、ご家族と、そして選任される弁護士の手にかかっています。計り知れない不安と混乱の中で、一人で悩みを抱え込まず、今すぐ少年事件に強い弁護士に相談してください。適切な「処分」の理解と、そこに向けた家族の協力、そして弁護士の専門的なサポートが、お子さんが再び社会の一員として健全に生きていけるための、最も確かな道筋となるでしょう。
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 平田裕也(ひらた ゆうや)
所属弁護士が150名程度いる大手法律事務所にて、約2年間にわたり支店長を務め、現在に至る。 大手法律事務所所属時代には、主として不貞慰謝料請求、債務整理及び交通事故の分野に関して,通算1000件を超える面談を行い、さまざまな悩みを抱えられている方々を法的にサポート。 その他弁護士業務以外にも、株式会社の取締役を務めるなど、自ら会社経営に携わっているため、企業法務及び労働問題(企業側)にも精通している。